
観葉スタイル・イメージ
ポトスを元気に育てたいと考えたとき、「ポトスの土の配合」は非常に重要なポイントになります。ポトスは「初心者向け」と言われるほど丈夫な植物ですが、市販の観葉植物用の土で育てていても、なぜか元気がなくなったり、根腐れを起こしてしまったりすることがあります。
そのような経験から、もっとポトスの生育環境にこだわりたい、あるいはコバエの発生を防ぎたいという方が、ご自身での土の配合を検討されることが多いようです。
もしかしたら、今まさに育てているポトスの葉が黄色くなったり、土が常に湿っていたりするのを見て、植え替えが必要だと感じているのかもしれません。
この記事では、ポトスに最適な土の基本的な考え方から、具体的な育て方、適切な施肥の方法、そして失敗しない植え替えの手順まで、詳細に解説します。
さらに、赤玉土のみや鹿沼土のみといった単一の用土で管理する方法、100均の材料を活用する際の注意点、土を使わないクリーンな栽培方法についても掘り下げます。
肥料の成分がポトスにどう影響するのか、そしてポトスの寿命を延ばす長期的な管理方法についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
ポイント
- ポトスに最適な土の配合比率がわかる
- 赤玉土や鹿沼土のみで育てる場合の注意点がわかる
- 土を使わないハイドロカルチャーの管理方法がわかる
- 根腐れを防ぐ植え替えの手順と育て方がわかる
コンテンツ
ポトスの土の配合と基本用土の役割

観葉スタイル・イメージ
参考
- 赤玉土のみで育てる注意点
- 鹿沼土のみで育てる場合
- 100均で揃う土の材料
- 土を使わない栽培方法とは?
- 肥料の成分と土の関係
赤玉土のみで育てる注意点

観葉スタイル・イメージ
結論から言うと、ポトスを赤玉土のみで育てることは可能です。ただし、この方法を選択するには、赤玉土の特性を理解し、いくつかの重要な注意点を守る必要があります。
赤玉土は、関東ローム層の赤土を乾燥させ、粒状にふるい分けたもので、園芸の「基本用土」として最も広く使われています。最大の特徴は、粒が多孔質(目に見えない小さな穴がたくさん開いている)であることです。
この構造により、「通気性(根が呼吸するための空気を通す力)」「排水性(余分な水を排出する力)」「保水性(適度な水分を保持する力)」という、土に求められる相反する要素を高いレベルで両立しています。
特に室内で育てる場合、腐葉土や堆肥などの有機質をエサにするコバエの発生は悩みの種です。赤玉土は栄養分を含まない無機質であるため、これだけを使えば害虫の発生源を断つことができ、室内でも清潔に管理できるという大きなメリットがあります。
しかし、メリットの裏返しとして、赤玉土自体には植物の成長に必要な栄養分(肥料成分)がほとんど含まれていません。植物が成長するためには、水と光合成だけでなく、チッソ・リンサン・カリなどの栄養素が不可欠です。
したがって、赤玉土だけで育てる場合は、外部からの定期的な施肥が生命線となります。
赤玉土のみで育てる場合の注意点
1.肥料による栄養補給が必須:ポトスの生育期である春から秋にかけては、栄養不足にならないよう計画的な施肥が必要です。即効性のある液体肥料を1〜2週間に1回程度、水やりの代わりに与えるか、効果が長く続く緩効性の固形肥料を土の上に置いて栄養を補う必要があります。
2.粒の崩れによる土壌環境の悪化:赤玉土は使用しているうちに徐々に粒が崩れ、本来の多孔質な構造が失われていきます。粒が崩れて微塵(みじん)になると、土の隙間が埋まり、通気性や排水性が極端に悪化します。
これは根が呼吸できなくなる「根詰まり」や「根腐れ」の直接的な原因になるため、1〜2年に1回は新しい土に植え替える作業が推奨されます。
赤玉土は基本用土として非常に優秀ですが、単体で使う場合は「徹底した肥料管理」と「定期的な植え替えによる土のリフレッシュ」が、ポトスを元気に育てるカギとなります。
鹿沼土のみで育てる場合
鹿沼土も赤玉土と同様に、無機質の基本用土であり、単体でポトスを育てる用土として使用できます。鹿沼土は栃木県の鹿沼地方で産出される火山灰が風化したもので、非常に水はけが良く、通気性に優れているのが特徴です。
赤玉土との大きな違いは、土壌がpH3.0〜5.0程度の強い酸性であることです。多くの観葉植物はpH5.5〜6.5程度の弱酸性を好みますが、ポトスは適応範囲が広く、鹿沼土の酸性環境でも問題なく育つことができます。
ただし、赤玉土と同じく、鹿沼土自体にも栄養分は一切含まれていません。そのため、肥料による栄養補給は必須です。また、鹿沼土は赤玉土よりも粒が柔らかく崩れやすい性質があるため、使用状況によっては植え替えの頻度が少し高くなる可能性があります。
もう一つの特徴は、非常に乾燥しやすいことです。赤玉土と比較しても保水性が低いため、水やりの頻度は少し多めになるかもしれません。一方で、この「乾きやすさ」は、水のやりすぎによる根腐れを防ぐというメリットにもなります。
土の表面が乾いているのを確認してから水を与えるという基本を守りやすい用土と言えます。
赤玉土と鹿沼土の使い分け
どちらも無機質で清潔な用土ですが、特性が異なります。
- 赤玉土:保水性と排水性のバランスが良い。迷ったらこちらが基本。
- 鹿沼土:排水性と通気性をより重視したい場合。酸性を好む植物にも。
実際には、ポトスの土を配合する際、これらを単体で使うよりも「赤玉土6:鹿沼土2:腐葉土2」のように、他の用土と混ぜてそれぞれの良い特性(排水性、保水性、通気性、保肥性)を引き出す使い方が一般的です。
100均で揃う土の材料
最近では、100円ショップ(ダイソー、セリアなど)の園芸コーナーが充実しており、観葉植物用の培養土や、配合に使う基本用土が手軽に入手できるようになりました。
例えば、以下のような材料が少量パッケージで販売されていることがあります。
- 観葉植物の土(あらかじめ配合済みの培養土)
- 赤玉土(小粒)
- 鹿沼土(小粒)
- 腐葉土
- パーライト(排水性を高めるための改良用土)
- 鉢底石(軽石)
これらの最大のメリットは、「少量から手軽に試せる」ことです。「自分で初めて土を配合してみたいけれど、ホームセンターで大きな袋(10L以上)を買うのは不安」「小さな鉢を一つだけ植え替えたい」という初心者の方にとって、100均の材料は非常に便利です。
ただし、利用する際にはいくつか注意点もあります。園芸専門店で扱われている高品質な用土と比較すると、品質にばらつきがある可能性も否定できません。
特に、微塵(みじん)と呼ばれる細かすぎる土の粉が多く含まれている場合があり、そのまま使うと土が詰まって排水性を悪化させる原因になることもあります。
また、大きな鉢植えの植え替えなど、たくさんの土が必要な場合には、結果的にコストパフォーマンスが悪くなるため、用途や量に応じてホームセンターの製品と使い分けるのが賢明です。
初めての土の配合チャレンジや、小さな鉢(3〜4号鉢程度)の植え替えであれば、100均の材料を活用してみるのは非常に良い選択肢ですね。まずは手軽に試してみましょう。
土を使わない栽培方法とは?

観葉スタイル・イメージ
ポトスは非常に順応性が高いため、土を一切使わずに育てることも可能です。この方法を一般的に「ハイドロカルチャー(水耕栽培)」と呼びます。
ハイドロカルチャーは、土の代わりに「ハイドロボール(粘土を高温で焼いた発泡煉石)」や「セラミス」「ゼオライト」といった無機質の専用培地を使用して植物の根を固定し、水と液体肥料で育てる方法です。土の栽培とは異なるメリットと注意点があります。
ハイドロカルチャーのメリット
1.清潔で虫が湧きにくい:最大のメリットです。土(特に有機質)を使わないため、コバエなどの害虫が発生するリスクを大幅に減らせます。キッチンカウンターや食卓、寝室など、清潔さを保ちたい場所に置くのに最適です。
2.水やり管理が視覚的に容易:透明なガラス容器などを使えば、容器内の水の残量が一目でわかります。これにより、水やりのタイミングを逃したり、逆に与えすぎたりする失敗を減らせます。水位計がセットになった専用鉢も市販されています。
3.見た目がおしゃれで省スペース:ガラス容器や好みのカップなど、鉢底に穴がない容器でも育てられるため、インテリアとしての自由度が高いです。
ハイドロカルチャーの注意点
1.根腐れしやすい:土栽培と異なり、根が常に水に接している時間が長くなるため、根が酸素不足になりやすく、土栽培よりも根腐れのリスクが高くなります。容器の底に溜める水は、容器全体の1/5程度までとし、水が完全になくなってから数日待って与える、といった管理が重要です。
2.根腐れ防止剤が必須:このリスクを軽減するため、容器の底には必ず「根腐れ防止剤(ゼオライトやミリオンAなど)」を敷き詰めることが重要です。これらは水質を浄化し、水が腐るのを防ぐ働きがあります。
3.専用肥料が必須:水道水だけでは植物の成長に必要な栄養がないため、ハイドロカルチャー専用の液体肥料を定期的に与える必要があります。
土栽培からハイドロカルチャーへの植え替えは慎重に
すでに土で育っているポトスをハイドロカルチャーへ移行する場合、根についた土を完全に洗い流す必要があります。この作業は根に大きなダメージを与えるため、非常に慎重に行わなければなりません。少しでも土の有機物が残っていると、水の中で腐敗し、根腐れの原因になるため、初心者の方は挿し木(水挿し)で発根させた株をハイドKカルチャーで育てる方が失敗が少ないです。
肥料の成分と土の関係
前述の通り、赤玉土や鹿沼土などの基本用土(無機質用土)には、植物の成長に必要な栄養分がほとんど含まれていません。
市販の「観葉植物の土」には、あらかじめ元肥(もとごえ)として肥料成分が配合されていることが多いですが、自分で配合した無機質用土で育てる場合や、長期間植え替えていない土では、外部からの施肥(せひ)が不可欠です。
植物の成長には様々な成分が必要ですが、特に重要なのは「肥料の三要素(三大栄養素)」と呼ばれる以下の3つです。
| 成分 | 記号 | 主な役割と通称 | 不足するとどうなるか |
|---|---|---|---|
| チッソ(窒素) | N | 「葉肥(はごえ)」 葉や茎の成長を促し、葉色を濃くします。ポトスのような葉を観賞する植物には特に重要です。 | 葉が小さくなり、葉色も薄黄色っぽくなる。下の葉から枯れ始める。 |
| リンサン(リン酸) | P | 「実肥(みごえ)」「花肥(はなごえ)」 花や実のつきを良くします。 | (ポトスでは目立ちにくいが)花が咲きにくく、葉の色が濃い緑や赤紫色になることがある。 |
| カリ(カリウム) | K | 「根肥(ねごえ)」 根の成長を促し、植物全体を丈夫にします。寒さや暑さ、病気への抵抗力を高めます。 | 根の張りが悪くなる。葉の縁から枯れこむことがある。 |
市販されているポトス(観葉植物)用の肥料として市販されているものは、一般的にこのチッソ(N)の比率が多めに配合されています。「N-P-K = 10-8-8」のように、パッケージにこの比率が記載されています。
肥料の種類と使い分け
肥料には大きく分けて「固形肥料」と「液体肥料」があります。
1.緩効性固形肥料(置肥):土の上に置くだけで、水やりのたびにゆっくりと成分が溶け出します。効果が長く続く(約1〜2ヶ月)のが特徴で、管理が簡単です。「プロミック観葉植物用」などが有名です。植え替え時に土に混ぜ込む「元肥(もとごえ)」として使われる「マグァンプK」もこの仲間です。
2.液体肥料(液肥):水で規定の倍率(500倍〜1000倍など)に薄めて使用します。即効性があるのが特徴ですが、効果は持続しません。生育期に1〜2週間に1回程度、水やりの代わりに与えます。「ハイポネックス原液」などが知られています。必ず規定の倍率を守り、濃すぎないように注意が必要です。
土の配合を自分で管理するということは、植物に必要な栄養(食事)である肥料の管理も自分で行うということだと理解しておきましょう。
ポトスの土を配合する植え替え
参考
- ポトスの植え替えサインと時期
- 植え替えの具体的な手順
- 植え替え後のポトスの育て方
- 植え替え後の施肥タイミング
- ポトスの寿命と管理方法
ポトスの植え替えサインと時期
ポトスは非常に成長が早く、丈夫な植物です。しかし、その成長の早さゆえに、同じ鉢で長く育てていると、鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」を起こしてしまいます。
根詰まりが起こると、根が新しい水を吸収するスペースや、呼吸するための酸素を取り込む隙間がなくなり、植物は窒息状態に陥ります。その結果、水や養分をうまく吸収できなくなり、成長が止まったり、葉が枯れたり、最悪の場合は根腐れを起こして枯れてしまいます。
そのため、ポトスを健康に長く育てるには、1〜2年に1回は、古い土を落として新しい土を補充し、一回り大きな鉢に植え替える作業が不可欠です。
植え替えが必要なサイン
- 鉢の底穴から根が飛び出している:これが最もわかりやすいサインです。根が新しいスペースを求めて外に出てきています。
- 水やりをしても、水が土に染み込みにくい:鉢の中が根でパンパンになり、土のスペースがなくなっている証拠です。
- 葉が黄色くなったり、元気なく垂れたりする:根詰まりや根腐れにより、うまく水分や養分を吸い上げられていない可能性があります。
- 鉢に対して株が大きくなりすぎ、バランスが悪い:見た目の問題だけでなく、頭が重くなり倒れやすくなるため危険です。
これらのサインが一つでも見られたら、植え替えのタイミングです。
植え替えに最適な時期は、ポトスの生育期である5月〜7月頃です。
この時期は気温が安定して暖かく、ポトスが最も活発に成長する時期にあたります。植え替え作業で根が多少傷ついたとしても、回復が早いため、植物本体への負担が最小限で済みます。遅くとも9月中旬までには終えるのが理想です。
冬場の植え替えは絶対に避けてください。
気温が10度を下回る冬は、ポトスの成長が緩慢になる「休眠期」にあたります。この時期に植え替えを行うと、根が受けたダメージを回復する力がなく、そのまま株全体が弱って枯れてしまうリスクが非常に高くなります。
植え替えの具体的な手順

観葉スタイル・イメージ
ポトスの植え替えは、ポイントさえ押さえれば決して難しくありません。ここでは、自分で土を配合する場合の基本的な手順を、ステップバイステップで詳しく解説します。
1.準備するもの
必要なモノ
- 現在よりも一回り大きい鉢(直径で3cm程度大きいサイズ)
- 鉢底ネット(鉢底穴をふさぐネット)
- 鉢底石(軽石や黒曜石パーライトなど)
- 自分で配合した土(例:赤玉土小粒6:腐葉土3:パーライト1)
- 元肥となる緩効性肥料(マグァンプKなど※土に混ぜ込む場合)
- 清潔なハサミ(根を切るため)
- 割り箸(土を隙間に入れるため)
- 新聞紙やレジャーシート(作業場所を汚さないため)
2.植え替えの数日前から水やりを控える
作業の数日前から水やりを止め、鉢の土を乾燥させておきます。これにより、鉢から株が抜きやすくなり、根についた古い土も落としやすくなります。
3.新しい鉢の準備
新しい鉢の底穴に鉢底ネットを敷きます。その上に、鉢底石を鉢の底が見えなくなる程度(鉢の高さの1/5程度)敷き詰めます。これは鉢内の排水性と通気性を格段に良くし、根腐れを防ぐための非常に重要な層です。
4.ポトスを鉢から取り出す
ポトスの株元を持ち、鉢の側面を軽く叩きながら慎重に引き抜きます。なかなか抜けない場合は、無理に引っ張らず、鉢の側面を優しく押して土と鉢の間に隙間を作ったり、鉢の縁に沿って細い棒を差し込んだりすると抜けやすくなります。
5.古い土と根の整理
鉢から抜いた株を「根鉢(ねばち)」と呼びます。この根鉢を優しく手で揉みほぐし、古い土を1/3程度落とします。すべて落とす必要はありません。このとき、根の状態をよく観察してください。
- 健康な根:白く、ハリがある。
- 古い根・腐った根:黒ずんでいる、ブヨブヨしている、スカスカしている。
黒ずんで腐った根や、鉢底でぐるぐる巻きになっている長すぎる根は、清潔なハサミで切り落として整理します。
6.新しい鉢への植え付け
準備した新しい鉢に、配合した土を鉢底石が隠れる程度入れます。(もし元肥を混ぜる場合は、このタイミングで土と混ぜておきます)。
ポトスを鉢の中央に置き、高さを調整します。ポトスの株元が鉢の縁よりも数センチ低くなる位置がベストです。この空間を「ウォータースペース」と呼び、水やりの際に水や土が溢れるのを防ぐ役割があります。
高さを決めたら、鉢と根鉢の隙間に新しい土を流し込みます。このとき、割り箸などで軽く土をつつきながら入れると、根の隙間まで土がしっかりと充填されます。
7.水やり
植え付けが完了したら、作業の総仕上げです。鉢底から透明な水が勢いよく流れ出るまで、これ以上ないというほどたっぷりと水を与えます。これは、土の中の微塵(細かいチリ)を洗い流し、根と新しい土を密着させるための重要な「水極め(みずぎめ)」という作業です。
植え替え後のポトスの育て方

観葉スタイル・イメージ
植え替え直後のポトスは、人間でいえば「大きな手術を終えた直後」のような、非常にデリケートな状態です。根が切られたり、環境が変わったりしたことで、大きなストレスを受けています。そのため、通常通りの管理をすると弱ってしまう可能性があります。
植え替え後、約1〜2週間は「養生期間」として、以下の点に注意して特別に管理してください。
植え替え直後の管理ポイント(養生)
1.置き場所:明るい日陰で休ませる:直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は絶対に避けてください。体力が落ちている状態での直射日光は、葉焼けや水分の蒸散過多を引き起こします。
室内でも窓から少し離れた、レースのカーテン越しの明るい日陰など、風通しの良い穏やかな場所で静かに休ませましょう。
2.水やり:メリハリをつけ、やや乾燥気味に:植え替え直後にたっぷりと水を与えた後は、土の表面が白っぽく、しっかりと乾くまで水やりを控えます。
根がまだ新しい土に張っておらず、水を吸う力が弱っているため、この時期に土が常に湿っていると、あっという間に根腐れを起こします。土が乾いたら、再び鉢底から流れるまでたっぷりと与える。「メリハリ」を通常時以上に意識することが重要です。
3.葉水(はみず):根の代わりに葉から水分補給:根からの水分吸収がうまくできていないため、霧吹きなどで葉に直接水分を与える「葉水」が非常に効果的です。空気中の湿度を保ち、葉の乾燥を防ぐとともに、ハダニなどの害虫予防にもなります。
植え替え後の施肥タイミング
植え替え後のポトスの管理において、水のやり方と並んで最も注意したい点が、施肥(肥料やり)のタイミングです。適切なタイミングを誤ると、回復を早めるどころか、かえって深刻なダメージを与えてしまう可能性があります。
植え替え直後のポトスの根は、古い土をほぐしたり、腐った根を切ったりしたことで、目に見えない無数の細かな傷がついています。根は本来、土中の水分を「浸透圧」の原理で吸収していますが、傷ついた根はこの機能が著しく低下しています。
この非常にデリケートな状態の根に、濃度の高い肥料(化学肥料=塩類)が触れると、どうなるでしょうか。根の細胞内の水分濃度よりも、土中の肥料濃度の方が高くなり、浸透圧のバランスが逆転します。その結果、根は水分を吸収するどころか、逆に内部の水分を奪われてしまうのです。
これが「肥料焼け」と呼ばれる現象の正体です。これはまさに、傷口に塩を塗り込むような行為であり、根は脱水症状を起こしてさらに傷み、株全体を急激に弱らせる最大の原因となります。
植え替え直後の「追肥」は厳禁
植え替え後、最低でも2週間から1ヶ月は、即効性のある液体肥料(液肥)や固形の置肥(おきごえ)といった「追肥(ついひ)」を一切与えないでください。
「元肥」と「追肥」で対応を分ける
ここで重要になるのが、「元肥(もとごえ)」と「追肥(ついひ)」の違いです。
- 元肥(もとごえ):植え付け時にあらかじめ土に混ぜ込んでおく、ゆっくり長く効くタイプの肥料(緩効性肥料)。例:「マグァンプK」など。
- 追肥(ついひ):植物の生育期に、後から追加で与える肥料。即効性のある液体肥料や、土の上に置く固形肥料(置肥)を指します。例:「ハイポネックス原液」「プロミック」など。
植え替え直後に厳禁なのは、根に直接的なダメージを与えやすい、即効性のある「追肥」です。では、元肥はどうなのでしょうか。植え替え時の状況別に、正しい対応方法を解説します。
ケース1:元肥入りの土(市販の培養土など)に植え替えた場合
市販の「観葉植物の土」の多くには、あらかじめ「マグァンプK」などの緩効性肥料が元肥として配合されています。
このタイプの肥料は、水にゆっくりと溶け出し、1〜2ヶ月かけて穏やかに効き始めます。これは、ポトスが植え替えのダメージから回復し、再び栄養を必要とし始めるタイミングと一致します。
したがって、元肥入りの土を使った場合は、養生期間(2週間〜1ヶ月)が過ぎた後も、さらに1〜2ヶ月は追加の追肥(液体肥料など)は一切不要です。
肥料のパッケージに記載されている持続期間(例:「約2ヶ月間効果が持続」)を目安に、追肥の開始を検討してください。
ケース2:元肥なしの土(赤玉土のみなど)に植え替えた場合
赤玉土や鹿沼土のみなど、栄養分を含まない無機質用土で植え替えた場合は、土の中に一切の栄養がありません。そのため、株が回復した後は、外部から栄養を補給してあげる必要があります。
肥料を再開する目安は、ポトスから「回復して成長を再開したサイン」が明確に見えてからです。
- 新しい芽が動き出し、小さな葉が開き始めた
- 新しいツルが伸びてきた
- 葉の色つやが良くなってきた
これらのサインが見えたら、肥料再開の合図です。ただし、いきなり通常の濃度の肥料を与えるのはまだ危険です。まずは、規定の倍率よりもさらに薄めた液体肥料からスタートしてください。
例えば、規定が「水で1000倍に薄める」ものであれば、最初は「2000倍」程度に薄めます。それを1〜2回与えてみて問題がなければ、次に「1500倍」、そして「1000倍」と、段階的に通常の濃度に戻していくと非常に安全です。
焦って肥料を与えたくなる気持ちを抑え、まずはポトス自身の回復力を信じて見守ることが、植え替えを成功させる最大の秘訣です。
ポトスの寿命と管理方法
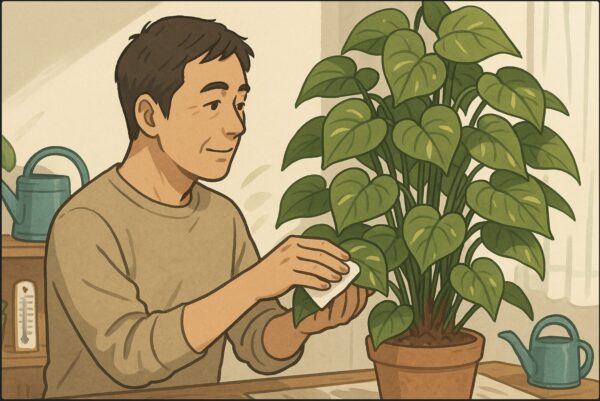
観葉スタイル・イメージ
ポトスはサトイモ科の多年草であり、生物学的に明確な「寿命」はありません。
原産地の熱帯雨林では、他の樹木などに根を張って(着生して)絡みつきながら、何十年も成長を続けます。家庭での栽培においても、環境と管理方法が適切であれば、10年、20年と非常に長く楽しむことができます。「寿命で枯れた」と思われるケースのほとんどは、実際には管理方法が原因で枯れてしまっています。
ポトスの「寿命」を縮める主な原因
- 根腐れ:最大の原因です。水のやりすぎ、または土の排水性が悪く常に湿っている状態が続くことで根が窒息して腐敗します。
- 根詰まり:前述の通り、長期間植え替えをせず、鉢の中で根が飽和状態になっている状態です。
- 寒さ(低温障害):ポトスは熱帯の植物で耐寒性が弱く、一般的に室温が5度以下になると成長が止まり、枯れてしまうリスクが高まります。冬場は必ず暖かい室内に取り込む必要があります。
- 水切れ:長期間の水切れは、当然ながら枯れる原因となります。
- 葉焼け:夏の強い直射日光に当てると、葉が焼けて白っぽく変色し、光合成ができなくなります。
つまり、「ポトスの土の配合」を排水性良く見直し、定期的に「植え替え」を行って根の環境をリフレッシュし、季節に合わせた「水やり」や「施肥」、「置き場所」を管理すること。これらの基本的な管理こそが、ポトスの寿命を延ばす唯一の方法と言えます。
ペットや小さなお子様への注意点
ポトスの管理において、もう一つ知っておくべき重要な点があります。それは「毒性」です。 厚生労働省の「自然毒のリスクプロファイル」によると、ポトスを含むサトイモ科の植物には、「シュウ酸カルシウム」の針状の結晶が含まれているとされています。
この樹液が皮膚に付着するとかぶれ(皮膚炎)を、ペットや幼児が誤って口にすると、口腔内の灼熱感や激しい痛み、嘔吐などを引き起こす可能性があります。
植え替えや剪定の作業をする際は手袋を着用し、ペットや小さなお子様の手の届かない場所に置くなど、管理には十分注意してください。
ポトスの土の配合で元気に育てる
ポトスの土の配合や、それに関わる植え替え、管理方法について詳しく解説してきました。最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。
チェックリスト
- ポトスの土で最も重要なのは「排水性」と「通気性」
- 根腐れを防ぐことがポトスを長く育てる最大のコツ
- 自分で配合するなら赤玉土や鹿沼土などの無機質用土が基本となる
- 市販の「観葉植物の土」はバランスが良く初心者には最も簡単
- 赤玉土のみや鹿沼土のみでも栽培は可能だが上級者向け
- 無機質用土だけの場合は肥料(施肥)による栄養補給が必須
- 肥料にはチッソ(葉)・リンサン(花)・カリ(根)の三要素がある
- ポトスには葉の成長を促すチッソ成分が重要
- 100均の材料は土の配合を少量から試すのに便利
- 土を使わないハイドロカルチャーという清潔な育て方もある
- ハイドロカルチャーは根腐れ防止剤が必須となる
- ポトスは1〜2年に1回、5月〜7月頃の植え替えが必要
- 植え替えのサインは鉢底からの根の飛び出しや水の浸透不良
- 植え替え後は直射日光を避けた明るい日陰で1〜2週間「養生」させる
- 植え替え後2週間〜1ヶ月は「肥料焼け」を防ぐため施肥をしない
- ポトスに明確な寿命はなく、適切な管理で10年以上育てられる
- 冬の寒さ(5度以下)と夏の直射日光は避ける
- ポトスには毒性(シュウ酸カルシウム)があり、ペットや幼児に注意
