
観葉スタイル・イメージ
人気の観葉植物パキラを、種から育ててみたいと考えたことはありませんか。「パキラの種子」と検索したあなたは、種はどこで売ってるのか、もし自宅で実がなったら種の採取や種取りはどうするのか、といった疑問をお持ちかもしれません。
種から育てる「実生(みしょう)」のパキラは、一般的な挿し木苗とは異なる魅力があります。
この記事では、パキラの種を入手する方法から、最適な種まきの時期、水苔を使った発芽のコツ、植え付けに適した土の種類、そして失敗しやすいカビの対策まで、詳しく解説します。風水の意味も含め、パキラを種から育てる楽しみをご紹介します。
ポイント
- パキラの種の具体的な入手先と最適な時期
- 種から育てる「実生」と挿し木の違い
- 水苔を使った発芽の手順と成功のコツ
- 発芽後の植え付けやカビ対策
コンテンツ
パキラの種子の入手方法と基礎知識

観葉スタイル・イメージ
パキラを種から育てる旅は、まずその「種」を手に入れることから始まります。しかし、パキラの種は一般的な花の種のように簡単には手に入りません。流通量が限られているのには明確な理由があります。
ここでは、種の入手方法や、種から育てることの根本的な意味、そして一般的な「挿し木」のパキラとの違いについて詳しく解説します。
参考
- パキラの種はどこで売ってる?
- 自宅での種の採取は可能か
- 収穫した実からの種取り方法
- 実生株と挿し木の違いとは
パキラの種はどこで売ってる?

観葉スタイル・イメージ
パキラの種を探して、近所のホームセンターや大規模な園芸店を巡っても、見つかることはほとんどありません。棚に並んでいる野菜や花の種とは異なり、パキラの種は一般流通には乗りにくい特別な事情を持っています。
その最大の理由は、パキラの種が「短命種子(たんめいしゅし)」であり、極端に寿命が短いという特性を持っているからです。
一般的な植物の種は乾燥させて長期保存が可能ですが、パキラの種は乾燥に非常に弱く、採取してから適切な湿度を保った状態でも、早ければ約半月~1ヶ月で発芽する力を失ってしまうとされています。
このため、主な入手先は、インターネット通販やネットオークション、フリマサイト(メルカリなど)が中心となります。
特に、パキラの種が収穫される時期(国内や近隣の産地によりますが、主に2月頃や8月頃)になると、専門の園芸店や、趣味でパキラを大きく育てて種を収穫した個人の栽培家から出品されることが増えます。
ネット購入のリスクと注意点
ネットで種を購入する際は、その鮮度が命です。フリマサイトなどでは、収穫時期が不明確なものや、古い種が出品されているリスクもゼロではありません。購入する際は、以下の点を確認しましょう。
- 収穫日の明記:いつ収穫した種かが明確か。
- 出品者の評価:過去の取引で種に関するトラブルがないか。
- 保存状態:乾燥させずに適切に保湿管理されていたか。
価格の安さだけでなく、鮮度と出品者の信頼性を最優先に考えることが、発芽成功への第一歩となります。
自宅での種の採取は可能か
結論から言うと、自宅でパキラの種を採取することは「理論上は可能ですが、非常に難易度が高い」のが実情です。
この最大の理由は、日本で一般的に流通しているパキラのほとんどが、枝を切って土に挿し、根を出させて増やす「挿し木(さしき)」という方法で生産された苗である点にあります。
植物には、人間でいう「子供」の時期(幼若相)と「大人」の時期(成熟相)という区分があります。種から育った植物は「子供」からスタートしますが、挿し木で増やされた株は、遺伝的には親株と同じ「大人」の状態です。
しかし、開花・結実には原産地(熱帯アメリカ)のような高温多湿な環境や、十分な大きさ(樹高)が求められます。日本の一般的な室内環境で挿し木株が開花することはほぼありません。
種を採取するためには、種から育てられた「実生(みしょう)」の株を手に入れなければなりません。
この実生株を、適切な環境(十分な光、温度、湿度)で最低でも5年から10年かけて大株に育てることで、初めて開花の可能性が生まれます。室内でパキラの花を咲かせること自体、園芸愛好家にとって一つの大きな目標となるほど稀なケースと言えるでしょう。
実生株の見分け方
もし将来的な開花と種の採取を目指して苗から育てる場合、「実生株」を選ぶ必要があります。実生株は、挿し木株と比べて根元がぷっくりと膨らみやすい傾向が見られます(個体差はあります)。
一方、挿し木株は幹がまっすぐで、上部を剪定(カット)した跡があることも少なくありません。購入時に「実生苗」と明記されたものを選ぶのが最も確実でしょう。
収穫した実からの種取り方法
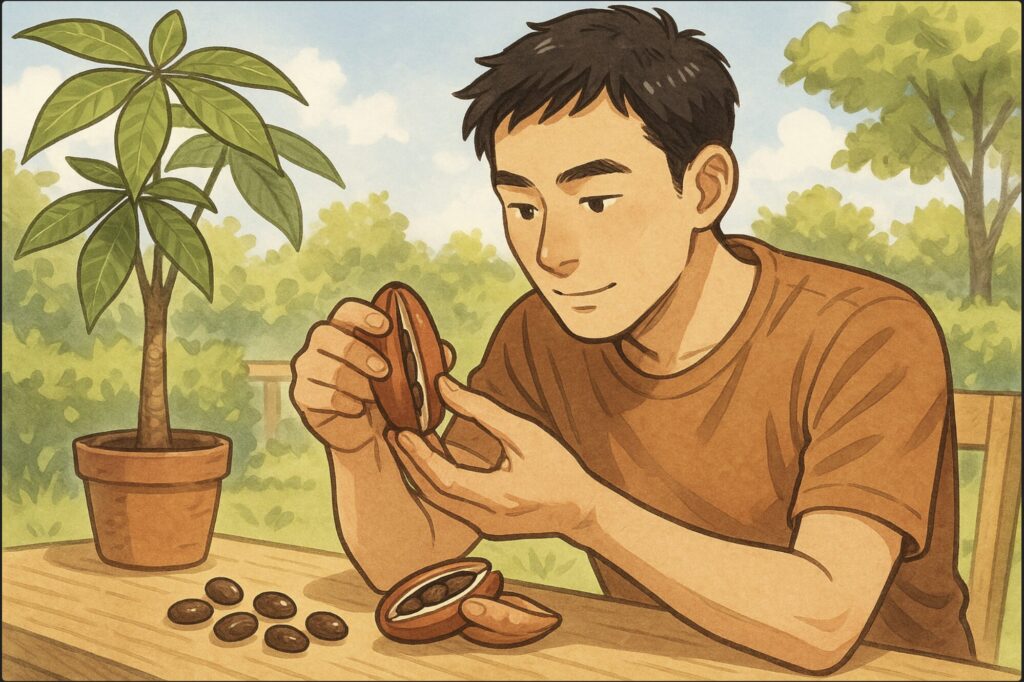
観葉スタイル・イメージ
もし幸運にも、丹精込めて育てた実生パキラに花が咲き、無事に受粉して実(果実)がついた場合、それは非常に貴重な体験です。次なるステップは、その実から健康な種を正しく取り出すことです。
パキラの実は、受粉後から徐々に大きくなり、最終的にはゴツゴツとした大きく硬い殻に覆われます。その見た目はカカオやアボカド、あるいは小さなラグビーボールのようにも例えられるユニークな姿をしています。
1.収穫のタイミングの見極め
種取りの成否は、収穫のタイミングで決まると言っても過言ではありません。
- NGな状態:実がまだ緑色(未熟)の状態。この時期の実は非常に硬く、中の種もまだ成熟していません。この段階で無理やり収穫しても、発芽は期待できません。
- OKな状態:実が成長を終え、緑色から黄褐色、そして全体が茶色く変色し、表面が乾燥して硬くなります。最終的に、熟した果実は自然に縦の割れ目(裂け目)が入り始めます。
収穫は、この「自然に割れ目が入る」か、あるいは木の上で実が弾けて種がこぼれ落ちるのを待つのがベストです。
収穫を失敗しないための工夫
パキラの実は成熟すると木の上で弾け飛び、種が広範囲に飛散することがあります。また、実自体が大きくて重いため、そのまま落下すると種が傷つく可能性もあります。
これを防ぐため、実が茶色く熟し始めたら、玉ねぎネットや園芸用の不織布などで実全体を袋状に優しく包んでおくことを強くおすすめします。これにより、実が弾けても種が飛散せず、安全に全て回収することができます。
2.種取りの具体的な作業
自然に裂け目が入った果実や、落下・弾けた果実は、硬い殻も手で比較的簡単に割ることができます。道具が必要なほど硬い場合は、まだ未熟な可能性があります。
殻を開くと、中から栗やトチの実に似た、茶色く大きな種が複数個(10~20個程度)ぎっしりと詰まって出てきます。
種の周りには、果肉のようなものはほとんど付着していません。薄い皮(渋皮のようなもの)に包まれている場合がありますが、無理に剥がす必要はありません。表面の汚れを軽く水で洗い流す程度で十分です。
3.収穫直後の最重要ルール:乾燥厳禁
取り出した種を見て、「少し乾燥させよう」と天日干しや室内干しをすることは絶対に避けてください。
パキラの種は「短命種子」です
パキラの種は、収穫した瞬間から猛烈なスピードで発芽能力(生命力)が低下し始めます。乾燥に極端に弱く、数日間乾燥しただけで発芽率がゼロになることも珍しくありません。鮮度が命であり、理想は「収穫後24時間以内に次のステップ(水没検査・種まき)に進む」ことです。
もしどうしてもすぐに作業できない場合は、湿らせたキッチンペーパーや水苔で種を包み、それをビニール袋に入れて口を軽く縛り、冷蔵庫の野菜室で保管してください。ただし、これも数日間の応急処置であり、1日でも早く作業を始めることが成功の鍵です。
4.食用に関する注意喚起
パキラは原産地で「カイエンナッツ」と呼ばれ、種が食用にされる(炒って食べるなど)という情報もあります。しかし、それは特定の品種(食用にされてきたPachira aquaticaなど)の話である可能性が高いです。
日本で観賞用として流通しているパキラの多くは、品種が異なる(Pachira glabraなど)とも言われており、その安全性は全く確認されていません。観賞用の品種には、微量のアルカロイドなど、人体に有害な成分が含まれている可能性も否定できません。
見た目はナッツに似ていても、食用の確証がない限り、絶対に食べないようにしてください。
実生株と挿し木の違いとは
「実生(みしょう)」と「挿し木(さしき)」では、見た目や性質に明確な違いがあります。どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれの特性を理解し、ご自身の好みに合わせて選ぶと良いでしょう。もちろん、これから種から育てる場合は、自動的に「実生株」になります。
主な違いを以下の表にまとめました。観葉植物を選ぶ際の参考にしてください。
| 比較項目 | 実生株(種から育てた株) | 挿し木株(枝から増やした株) |
|---|---|---|
| 根元の形 | 個体差があるが、ぷっくりと太りやすい傾向がある。貯水タンクの役割も持つ。 | 親木の一部なので、まっすぐな幹が多く、根元が顕著に太ることは少ない。 |
| 成長 | 地中深くに伸びる「主根(しゅこん)」があり、体を支え、効率よく水を吸う。成長が早い傾向。 | 主根がなく、細い根(不定根)が横に広がる。成長は実生より穏やか。 |
| 開花・結実 | 5~10年後、咲く可能性がある。 | 日本ではほぼ咲かない(開花例は極めて稀)。 |
| 入手方法 | 幼苗として販売(「実生苗」と表記)、または種を入手。 | 最も一般的に流通。「三つ編みパキラ」などもこれにあたる。 |
特に大きな違いは「主根」の有無です。種から発芽した実生株は、まず太い主根をまっすぐ下に伸ばし、体を支える土台を作ります。このため、将来的に大きく育ちやすく、環境適応力(乾燥や寒さへの耐性)も高い傾向にあると言われています。
一方、挿し木株は加工がしやすいため、複数の苗を編み込んで「三つ編みパキラ」としてデザイン性を高めた商品に多く利用されています。
インテリアとしておなじみの、幹が編み込まれた「三つ編みパキラ」は、100%挿し木株です。種から育てると、あのような姿にはならず、根元がどっしりとした自然な樹形に育ちますよ。どちらも違った魅力がありますね。
パキラの種子から育てる方法
貴重なパキラの種を手に入れたら、いよいよ種まきの工程に入ります。鮮度が命であるため、入手後は迅速に作業を始めることが成功率を上げる最大のポイントです。ここでは、発芽から植え付け、その後の管理まで、失敗しやすいポイントを含めて具体的なステップを解説します。
参考
- 最適な種まきの時期はいつ?
- 水苔を使った発芽の準備
- 発芽させるための管理方法
- 発芽後に適した土の種類
- 種や苗のカビを防ぐ対策
- 種から育てるパキラと風水
- パキラ育成を楽しむコツ
最適な種まきの時期はいつ?
パキラの種まきにおいて、カレンダー上の「時期」よりも圧倒的に優先すべきは「鮮度」です。
結論としては、「種を入手したら季節を問わず、すぐにまく」が正解です。前述の通り、パキラの種は採取から約1ヶ月で発芽率が著しく低下すると言われています。
手元に届いた時点で、すでにある程度の時間が経過している可能性を考慮し、新鮮なうちに作業を始める必要があります。「春まで待とう」と保存している間に、発芽能力を失ってしまう可能性が非常に高いのです。
とはいえ、パキラは熱帯アメリカ原産の植物であり、発芽には20℃以上の安定した気温が不可欠です。有名企業のアイリスオーヤマの通販サイトでもパキラの生育適温は20℃〜30℃と紹介されており、発芽には特に安定した暖かさが求められます。
このため、気温が自然に20℃を超える春から夏(5月~9月頃)は、特別な加温設備がなくても管理しやすく、最も適した時期と言えます。
もし冬場(2月頃の収穫期)に種を入手した場合は、暖房の効いた室内や、園芸用の育苗ヒーター(パネルヒーター)、あるいは発泡スチロールの箱に入れるなどの工夫をして、常に20℃以上をキープできるように環境を整えてから種まきを行いましょう。
水苔を使った発芽の準備

観葉スタイル・イメージ
パキラの種は、清潔で保湿性に優れた水苔(みずごけ)を使って発芽させる方法が一般的で、土に直接まくよりも成功率が高いとされています。これは、水苔が①清潔で雑菌が少ない、②適度な湿度を保ちやすい、③発根の様子を観察しやすい、というメリットがあるためです。
ステップ1:水没検査
まず、入手した種が発芽可能かどうかを選別する「水没検査」を行います。バケツやボウルに常温の水を張り、種を静かに入れます。
- 沈む種:中身が詰まっており、発芽する可能性が高い健康な種です。こちらを使います。
- 浮く種:中身が未熟、乾燥、あるいは虫害などで空洞になっている種(シイナと呼ばれます)です。これらは発芽しにくく、水苔の中で腐敗してカビの原因にもなるため、取り除きます。
水没検査は1日以内に
水没検査のために長時間(丸1日以上)水に浸けっぱなしにすると、種が呼吸できずに窒息し、健康な種まで腐ってしまう原因になります。検査は数時間から半日程度で切り上げ、すぐに次の作業に移してください。
ステップ2:水苔で包む
乾燥水苔を使用する場合は、まず水で十分に戻し、両手で挟んで固く絞り、余分な水分を取り除きます。「触ると湿っている」状態がベストで、「握ると水が滴る(ビショビショ)」状態ではいけません。
この湿らせた水苔で、水没検査で選別した種を優しく包み込みます。種が隠れる程度にふんわりと包むのがコツです。
発芽させるための管理方法
種を包んだ水苔は、「高温(20~25℃)」と「高湿度」を安定して維持することが発芽成功の鍵です。
水苔が乾燥しないよう、プラスチック製の食品トレイやタッパー、チャック付きのビニール袋などに入れます。フタや袋は完全に密閉せず、少し空気の通り道を作っておくか、1日に1回程度開けて換気することで、カビの発生を抑えることができます(これを「蒸れ」の防止と呼びます)。
これを、室温20℃~25℃程度を保てる暖かい場所に置きます。発芽に光は必要ないため、直射日光の当たらない半日陰(例:リビングの棚の上や、ルーター機器の近くなど、ほんのり暖かい場所)で管理します。
早ければ数日、通常は1~2週間ほどで、種の殻が割れて白く太い根(これは「胚軸(はいじく)」や「幼根(ようこん)」と呼ばれる部分です)が伸びてきます。
植え付けのタイミング
根が伸び、芽になる部分(子葉)が見え始め、根の長さが2~3cm程度に育ってきたら、デリケートな根が傷つく前に、土へ植え付ける最適なタイミングです。根が長くなりすぎると、水苔に絡まって植え付け時に傷つけてしまうリスクが高まります。
発芽後に適した土の種類

観葉スタイル・イメージ
発芽したばかりのパキラの幼苗は、人間でいえば新生児と同じで非常にデリケートです。植え付ける土は、肥料分が含まれていない、清潔で水はけの良い土を選びましょう。
理由は、この段階で肥料の成分(特に化学肥料)が繊細な根に触れると「肥料焼け」を起こし、枯れてしまうことがあるためです。また、使い古しの土など雑菌が多い土では、植え付けたばかりの幼苗が病気にかかりやすくなります。
おすすめの用土
- 赤玉土(小粒)の単用:最も一般的で清潔。水はけと保水性のバランスが良いです。
- 種まき、挿し芽専用の培養土:市販されているもので、最初から清潔に処理されています。
- バーミキュライトやパーライト:赤玉土に混ぜて、さらに通気性や保水性を調整するのに使えます。
3号程度(直径9cm)の小さなポリポットや鉢に、鉢底ネットと鉢底石(軽石など)を薄く敷き、上記の清潔な土を入れます。土はあらかじめ湿らせておきます。中央に指で軽く穴を開け、胚(根)を傷つけないように優しく差し込みます。
このとき、種の殻(子葉)が半分地上に出るくらいの「浅植え」にし、乾燥防止のために土の表面を発芽に使った水苔で軽く覆っておく(マルチング)のも非常に効果的です。
水やりは、植え付け直後に優しく行い、その後は土の表面が乾いたら与える程度にします。肥料は、本葉が数枚展開して成長が安定してから、ごく薄めた液体肥料(通常の観葉植物用の1000倍希釈よりさらに薄い2000倍希釈程度から)を与えることから始めます。
種や苗のカビを防ぐ対策
パキラの種まきで最も多く報告される失敗例が「カビ」です。高温多湿を好むのはパキラだけでなくカビも同じです。カビ(糸状菌)は、「①過剰な水分(多湿)」「②腐敗しやすい有機物(栄養源)」「③空気の停滞(蒸れ)」の3つの条件が揃うと爆発的に発生しやすくなります。
対策1:浮いた種(シイナ)は必ず除く
前述の通り、水没検査で浮いた種は、発芽しないだけでなく、水苔の中で腐敗してカビの温床(栄養源)となります。「もしかしたら」と残しておくと、他の健康な種までカビに侵される原因になるため、必ず取り除きましょう。
対策2:水分の管理と「換気」
水苔も土も、ビショビショの「多湿」状態にし続けるのは最も危険です。水苔は固く絞ってから使い、植え付け後も土が常に湿っている状態ではなく、適度な風通しを意識してください。
タッパーなどで管理する場合も、1日に1~2回はフタを開けて新鮮な空気に入れ替えることが非常に重要です。これが「換気」であり、「蒸れ」を防ぐ最も有効な手段です。
対策3:種殻の除去
発芽して双葉(子葉)が開いた後、栄養を使い果たした種の殻が残ることがあります。この殻や、双葉の間に残ったゼリー状の物質(胚乳の一部など)が腐敗してカビの原因になることがあります。見た目が悪くなってきたら、ピンセットなどで優しく取り除くと清潔に保てます。
一般的なカビ対策
植物栽培におけるカビ(糸状菌)は、風通しを良くすることが最大の予防策です。梅雨時期などは、サーキュレーターで室内の空気を軽く循環させるのも効果的です。
カビの発生予防や初期症状については、大手園芸薬品メーカーの病害虫情報ページ(KINCHO園芸など)で、一般的な病気の種類(うどんこ病、灰色かび病など)と対策を確認しておくと参考になります。これらの病気も、原因の多くは「風通しの悪さ」とされています。
種から育てるパキラと風水
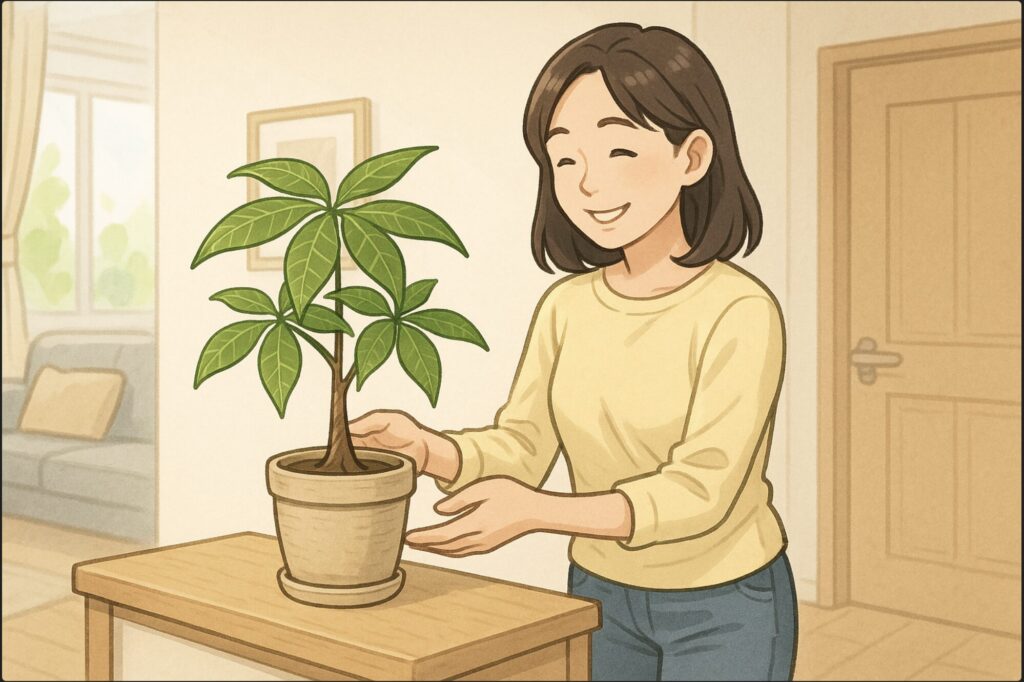
観葉スタイル・イメージ
パキラは、その育てやすさと美しい姿から観葉植物として絶大な人気を誇りますが、それと同時に風水アイテムとしても非常に有名です。
園芸店やインテリアショップで「マネーツリー(Money Tree)」や、そのまま「発財樹(はつざいじゅ)」という名前で販売されているのを見たことがある人も多いでしょう。
このように呼ばれる由来は、「昔、貧しい人がパキラの苗を売って財を成した」という伝説から来ており、風水において強力な「金運」や「仕事運」を引き寄せる力があるとされています。
しかし、パキラの風水効果はそれだけではありません。具体的にどのような力があり、どこに置くのが良いのか、そして「種から育てる」ことにどのような特別な意味があるのかを詳しく解説します。
パキラが持つ風水パワーの源
パキラが風水で重宝される理由は、その姿形にあります。
- 上向きに伸びる強い生命力:パキラは非常に成長が早く、幹も太く、上へ上へと力強く伸びていきます。この姿が「陽の気」を象徴し、運気の「成長」「発展」を促すとされています。
- 手のひらのような葉:5枚(時に6枚や7枚)の葉が放射状に広がる姿は、「手を広げて金運を掴む」様子に例えられます。また、人や良い気を集める力があるとされています。
- 丸みを帯びた葉:風水では、尖った葉は「邪気」を払う力が強い反面、気を緊張させるとも言われます。パキラのような丸みを帯びた葉は、周囲の「気」を穏やかにし、リラックス効果をもたらすため、人間関係の円満にもつながります。
運気別・おすすめの置き場所
パキラの持つパワーを最大限に活かすため、目的に合わせた置き場所をご紹介します。
金運・仕事運アップを狙うなら
「玄関」や「リビングの東南」がおすすめです。
玄関は全ての運気が入ってくる入り口であり、そこに「発財樹」を置くことで、外から良い金運を呼び込むとされています。また、風水で「東南」は財産や人間関係(縁)を司る方角とされるため、リビングの東南に置くことで金運と良縁を引き寄せます。
勉強運・集中力アップなら
「書斎」や「子供部屋」、「オフィスのデスク」が最適です。
パキラの丸い葉がもたらすリラックス効果と、上へ伸びる「陽の気」が、集中力を高め、発展・成長(学業成就や昇進)をサポートすると言われています。特に「東」の方角は仕事や勉強の発展を促すため、部屋の東側に置くとより効果的です。
風水で植物を置く際の注意点
風水で植物を使う際、最も重要なのは「植物が健康であること」です。埃をかぶっていたり、枯れ葉がついていたり、元気がなかったりすると、逆に「陰の気」や「停滞した気」を生み出し、運気を下げてしまう原因になりかねません。
- 葉水(霧吹き)などで葉を常に清潔に保ちましょう。
- 枯れた葉はこまめに取り除いてください。
- 日当たりや風通しが悪い場所に置きっぱなしにせず、植物が元気に育つ環境を整えることが、結果として良い運気を呼び込みます。
- 特に寝室に置く場合は、植物が夜間に二酸化炭素を出すことや、気が停滞しやすいとされるため、大きすぎるものは避けるか、清潔さを徹底するなどの配慮が必要です。
「実生パキラ」が持つ特別な風水パワー
一般的な挿し木苗のパキラでも、もちろん風水効果は期待できます。しかし、この記事のテーマである「種から育てる実生パキラ」には、それを上回る特別な風水的な意味が込められています。
それは、「ゼロから富を築く力」と「運気を育てるプロセス」そのものです。
挿し木は、すでにある親木の一部(枝)を利用し、他者の力(生産者)によって増やされたものです。これは「既にある運」や「他力による運」を象徴するとも言えます。
対して「実生」は、たった一粒の種という「ゼロ」の状態から、発芽させ、根を張らせ、芽を出し、幹を太らせていきます。このプロセスは、まさに「発財樹」の由来となった伝説のように、自らの手で「無」から「有」を生み出し、富と繁栄を着実に築き上げていく姿そのものです。
「運気を育てる」という感覚ですね。毎日水を与え、成長を見守るという行為そのものが、あなたの「金運」や「仕事運」を育てる儀式のようになります。だからこそ、実生パキラは世界に一つだけの、あなたにとって最も強力なパーソナルなお守り(風水アイテム)となるのです!
パキラ育成を楽しむコツ
挿し木苗を購入するのに比べ、パキラを種子から育てるのは時間も手間もかかり、カビなどのリスクも伴います。発芽に成功しても、お店で売っているような立派な姿になるには数年かかります。しかし、それ以上に代えがたい大きな魅力とロマンがあります。
1.成長のプロセスを楽しむ喜び
固い種が数日でその殻を破り、太い根を伸ばし、やがて双葉が開き、パキラらしい5枚葉が展開していく…。生命の誕生と成長のプロセスを日々、目の当たりにできるのは、種から育てる醍醐味です。
「今日は昨日より根が伸びた」「双葉が完全に開いた」「本葉の赤ちゃんが見えてきた」という小さな発見が、大きな喜びと達成感を与えてくれます。この過程は、完成品の苗を購入するだけでは決して味わえません。
2.実生株ならではの個性と樹形
挿し木株がどれも似た姿(親木のクローン)になるのに対し、種から育った実生株は一つひとつに個性が出ます。人間と同じで、兄弟でも顔つきや性格が違うように、同じ時にまいた種でも成長の速さや葉の形、枝分かれの仕方が異なります。
特に、パキラの魅力の一つである根元がぷっくりと膨らんでいく独特の樹形は、実生株ならではの楽しみです。「自分だけのパキラ」を育てている実感が、愛着をさらに深めてくれます。
3.最大のロマン「開花」の可能性
そして、なんといっても最大の魅力は、「花が咲く可能性」を秘めている点です!
パキラの花は、夕方から夜にかけて咲き始め、無数の白いおしべ(時に赤みがかることも)が線香花火のように一斉に広がる、非常に繊細で幻想的な姿をしています。残念ながらその命は短く、翌朝にはしぼんでしまうことが多い「一日花」です。
詳しくは、NHK趣味の園芸「パキラの基本情報」などの専門サイトでも紹介されていますが、挿し木株では絶対に見ることができないこの幻想的な花を、5年後、10年後に咲かせられるかもしれないというロマン。
この感動は、種から育てた人にしか味わえない、特別なご褒美と言えるでしょう。貴重な種を無事に発芽させ、あなただけのパキラを育てる旅は、きっと素晴らしい体験になりますよ。ぜひこの記事を参考に、挑戦してみてください。
パキラを種子から育てる魅力
チェックリスト
- パキラの種は「短命種子」であり鮮度が命である
- 種の寿命は採取から約半月〜1ヶ月と非常に短い
- 主な入手先は収穫時期(2月・8月頃)のネット通販やオークション
- 一般的なホームセンターでの入手は困難
- 自宅で種を採取するには「実生株」を5〜10年育て開花させる必要がある
- 日本で流通する多くは「挿し木株」で花は咲かない
- 実生株は根元が太りやすく主根があり成長が早い
- 挿し木株は根元がまっすぐで三つ編みなどに利用される
- 種を入手したらすぐに「水没検査」を行う
- 水に沈む種だけを選び浮く種はカビの原因になるため除く
- 水没検査は1日以上行わず短時間で終える
- 種まきの適期は気温20℃以上(春〜夏)が理想
- 冬でも20℃以上を保てるならすぐにまく
- 清潔で湿らせた「水苔」で種を包み発芽を待つ
- 発芽までは高温多湿を保ちつつ適度な換気を行う
- 発芽後の土は肥料分のない清潔な土(赤玉土など)を選ぶ
- カビ対策には「浮いた種」の除去と「換気」が最も重要
- 種から育てるパキラは風水的に「ゼロから富を生む」象徴となる
- 最大の魅力は挿し木株では見られない「開花」の可能性があること
