
観葉スタイル・イメージ
育てているパキラが、気づけばひょろひょろに。パキラがひょろひょろになるのはなぜ?と疑問に思いつつ、思い切って剪定したら、今度はパキラが丸坊主の状態になってしまった…。
葉が一枚もない幹だけの姿を前に、このまま芽が出ないのではないか、枯れてしまったのではないかと、毎日不安な気持ちで幹を眺めてしまいますよね。
もちろん、パキラを丸坊主にするにはどうしたらいいですか?と、樹形をリセットするために積極的な剪定を調べる方もいますが、多くは意図せず丸坊主になってしまい、失敗したと感じているはずです。
剪定の時期や成長点を意識していましたか?どこを切るかで、その後の成長は大きく変わります。また、パキラは1年でどれくらい成長しますか?という疑問の通り、本来は非常に生育旺盛な植物です。適切な置き場所や風通しを管理すれば、きっと復活します。
この記事では、なぜパキラが丸坊主状態になってしまったのかという原因の解明から、失敗しないための正しい剪定手順、そして最も重要な剪定後の管理方法まで、パキラを確実に復活させるための知識を網羅的に解説します。
ポイント
- パキラが丸坊主になる主な原因
- 失敗しない剪定の時期と正しい位置
- 剪定後に新芽が出ないときの対処法
- 丸坊主から復活させるための管理方法
コンテンツ
パキラを丸坊主にする原因と基本知識
参考
- パキラがひょろひょろになるのはなぜ?
- 剪定で失敗しないためのポイント
- 丸坊主に適した時期はいつ?
- 成長点を意識した剪定のコツ
- 剪定で失敗しない「切る位置」の実践テクニック
- パキラは1年でどれくらい成長しますか?
パキラがひょろひょろになるのはなぜ?

観葉スタイル・イメージ
パキラがひょろひょろと力なく伸びてしまう現象、その主な原因は「徒長(とちょう)」と呼ばれる植物の異常な成長状態です。そして、この徒長を引き起こす最大の引き金は、圧倒的な「日照不足」です。
パキラは「耐陰性(日陰に耐える力)がある」観葉植物として有名ですが、この言葉は誤解されがちです。耐陰性とは、あくまで「暗い場所でもすぐに枯れはしない」という耐久力を示すものであり、「暗い場所で元気に育つ」という意味では決してありません。
パキラも他の植物と同様、本来は太陽の光を浴びて光合成を行い、成長するためのエネルギー(糖)を作り出しています。光が足りないと、このエネルギーが慢性的に不足します。
「もやし」と同じ原理で伸びる
エネルギー不足に陥ったパキラは、生き残るために「緊急避難」的な成長を始めます。それが徒長です。
植物には、光のある方向へ枝を伸ばす性質(光屈性)があります。暗い場所に置かれたパキラは、「このままではエネルギーが作れず死んでしまう」と判断し、今あるエネルギーのすべてを「光のある場所へ到達すること」だけに集中させます。
スーパーで売られている「もやし」が、暗闇の中で光を求めて細長く伸びるのと同じ原理です。
その結果、以下のようなエネルギー配分の偏りが起こります。
- 幹や枝を太く、丈夫にするためのエネルギーを節約する。
- 葉を大きく、厚くするためのエネルギーを節約する。
- 代わりに、節と節の間(節間)を長く伸ばし、とにかく「高さ」を稼ごうとする。
このため、細胞壁は薄く、葉は小さく色も薄い、茎だけが間延びした「ひょろひょろ」で「軟弱」な姿になってしまうのです。
あなたのパキラは大丈夫?徒長の見分け方
以下の項目に当てはまる場合、徒長している可能性が高いです。
- 節と節の間隔が、購入時と比べて不自然に長くなっている。
- 葉の色が健康的な濃い緑ではなく、薄い黄緑色をしている。
- 新しく展開する葉が、以前より明らかに小さい。
- 枝や幹が細く、自分の葉の重みを支えきれずに垂れ下がっている。
- 窓のある一方向に向かって、不自然に傾いて伸びている。
日照不足以外の徒長要因
日照不足が最大の原因ですが、他の要因が組み合わさることで徒長をさらに悪化させることがあります。
| 要因 | 解説 |
|---|---|
| 水のやりすぎ | 土が常に湿っていると根が酸素不足になり、根腐れを起こします。根が傷むと、光合成に必要な水分や養分をうまく吸い上げられず、結果としてエネルギー不足を助長し、徒長につながります。 |
| 風通しの悪さ | 植物は適度な風に揺られることで、自身を支えるために幹や枝を太く丈夫にしようとします。風通しが悪いと物理的な刺激がなく、より軟弱に育ちやすくなります。 |
| 肥料(窒素)過多 | 肥料の三要素のうち、「窒素(N)」は「葉肥え」とも呼ばれ、葉や茎を成長させる働きがあります。日照不足の状態で窒素ばかりを与えすぎると、成長のバランスが崩れ、軟弱な徒長をさらに促進させてしまいます。 |
徒長を放置してはいけない理由
ひょろひょろな姿は、単に「見た目が悪い」だけではありません。細胞壁が薄く軟弱な状態は、人間で言えば免疫力が低下しているのと同じです。カビなどの病気にかかりやすくなったり、ハダニやカイガラムシといった害虫の格好のターゲットになったりします。
残念ながら、一度徒長してひょろひょろに伸びてしまった枝は、その後どれだけ明るい場所に移動させても、太く丈夫な姿に戻ることはありません。
この乱れた樹形と健康状態をリセットする唯一の方法が、次に解説する「剪定」なのです。
剪定で失敗しないためのポイント

観葉スタイル・イメージ
パキラの剪定で失敗しないための最大のポイントは、「適切な時期を守る」ことと「清潔な道具を使う」ことです。この2点を守るだけで、成功率は格段に上がります。
パキラは非常に生命力が強い植物ですが、基本を無視して適当に切ってしまうと、切り口から雑菌が入ったり、回復が遅れたりする原因になります。
清潔なハサミを使う
剪定に使用するハサミは、必ず消毒したものを使いましょう。植物の切り口は、人間の手術痕や傷口と同じです。土の中や空気中には無数の雑菌(カビの胞子やバクテリア)が存在しており、汚れたハサミを使うと、それらの菌を植物の体内に直接植え付けてしまうことになります。
菌が道管(水の通り道)で繁殖すると、水の流れが詰まり、切り口から先が黒く変色しながら枯れ込んでしまうことがあります。
簡単な消毒方法
- 市販の消毒用エタノールやキッチン用アルコールスプレーを刃先に吹きかけ、清潔な布やティッシュで拭き取る。
- ライターの火で刃先を数秒間軽く炙る(火炎消毒)。※火傷に注意してください。
- 園芸用の刃物クリーナーを使用する。
切れ味の良いハサミで一気に切る
切れ味の悪いハサミで何度も枝を挟んだり、潰すように切ったりすると、植物の細胞(道管や師管)が潰れてしまいます。これにより、切り口の乾燥が遅れ、雑菌の侵入を許す時間が長くなります。また、回復のために余計なエネルギーを使うことにもなります。
できるだけ切れ味の良い園芸用の剪定バサミを用意し、スパッと一回で切り落とすことを心がけてください。これにより、切り口がきれいに保たれ、回復が早まります。
丸坊主に適した時期はいつ?

観葉スタイル・イメージ
パキラの剪定、特に幹や太い枝を切り落とす「丸坊主」のような強い剪定は、生育期である5月〜7月が最適です。
気温が安定して15℃以上、できれば20℃〜30℃の範囲になるこの時期は、パキラの細胞分裂が最も活発です。剪定という大きなストレスを受けても、すぐに新しい芽を形成し、成長を再開する力を持っています。
多くの園芸専門情報サイトや書籍でも、観葉植物の強剪定は、生育期の前半(5月〜7月)に行うことが推奨されています。(例:APEGOオンライン)逆に、絶対に避けるべき時期もあります。
真夏(8月)は避ける:気温が35℃を超えるような猛暑日が続く時期は、パキラも人間と同じく「夏バテ」状態になり、成長が一時的に鈍ることがあります。この時期の強剪定は、回復を遅らせる可能性があるため、できれば避けた方が無難です。
秋・冬の剪定は絶対にNG:気温が15℃を下回り始める秋以降(目安として9月下旬〜10月以降)、パキラは水の吸い上げを極端に減らし、成長を止める「休眠期」に入ります。
この「寝ている」状態で大きな手術(剪定)を行うと、新芽を出す体力が残っておらず、剪定のダメージから回復できずにそのまま枯れてしまうリスクが非常に高くなります。
成長点を意識した剪定のコツ

観葉スタイル・イメージ
パキラの枝や幹には「成長点」と呼ばれる、新芽が出るポイントが存在します。この成長点を残すように意識して剪定することが、早い復活につながるコツです。
成長点とは、パキラの幹や枝の表面にある、少し膨らんだ節や、葉っぱが落ちた跡の小さな突起のような部分です。
幹の表面で樹皮の色が少し違ったり、小さな円形や楕円形の模様に見えたりする場所で、元々葉がついていた付け根の跡であることが多いです。ここが、植物が次に成長するための「芽の元」だと考えてください。
剪定する際は、この新芽を吹かせたい成長点を探し、その少し上(5mm〜1cm程度)で枝を切り落とします。
成長点の真上ギリギリで切ってしまうと、切り口と一緒に成長点が乾燥して機能しなくなることがあるため、必ず少し余裕を持たせて切るのがポイントです。
もし成長点がはっきりと見つからなくても、パキラは生命力が非常に強いため、幹の途中から新しい成長点を作り出して芽吹くことも多いです。
ただし、木質化(茶色く硬くなった)した古い幹の途中からは、新芽が出にくい場合があります。できるだけ、緑色が残っている若い枝や、比較的新しい幹の部分で成長点を探す方が確実です。成長点を残して剪定した方が、より早く、そして確実に新芽の展開が期待できます。
剪定で失敗しない「切る位置」の実践テクニック
剪定で「どこを切るか」は、「将来、どの位置から新しい枝を分岐させたいか」をイメージして決めるのが最も重要です。剪定は「切って終わり」ではなく、「新しい芽をどこから出させるか」をデザインする作業だと考えてください。
前述の通り、パキラの新芽は切った場所のすぐ下にある「成長点」から分岐して生えてくるという、はっきりとしたルールがあります。このルールを踏まえ、目的別にどこを切るべきかを見ていきましょう。
1.徒長リセット(丸坊主)の場合:低い位置で高低差をつける
ひょろひょろに伸びた樹形を根本からリセットしたい場合、切るべきは「幹」そのものです。
切る位置:将来的に葉が茂ってほしい高さよりも、5cm〜10cm低い位置で切ります。
例えば、床から50cmの位置から葉をこんもりとさせたい場合、床から40cm〜45cmの位置にある成長点を探し、その上でカットします。なぜなら、新芽はそこから上に向かって伸びていくため、あらかじめ成長する「伸びしろ」を確保しておく必要があるからです。
編み込みパキラの場合の重要テクニック
複数の幹が編み込まれているパキラを丸坊主にする場合、「すべての幹を同じ高さで切らない」ことが、自然な樹形に仕上げる最大のコツです。
すべての幹を同じ高さで切り揃えてしまうと、新芽が一斉に同じ高さから生え、まるで「散髪に失敗した頭」や「人工的な生垣」のようになりがちです。
あえて、40cm、43cm、47cmのように、各幹の切る高さを3〜5cmずつズラしてみてください。これにより、新芽が出たときに高低差が生まれ、ボリューム感のある自然なシルエットに仕上がります。
2.部分的な修正(軽い剪定)の場合:枝の分岐点までたどる
「丸坊主にはしたくないが、一本だけ飛び出た枝が邪魔」という場合もあります。
切る位置:その飛び出た枝を、葉の密集している部分までたどり、枝分かれしている付け根(分岐点)や、幹から出ているすぐの場所で切ります。
枝の途中で中途半端に切ると、そこからまた不自然な形で新芽が伸びてしまいます。切るなら、その枝の「根元」から切り落とし、他の健康な枝にエネルギーを集中させるのが正解です。
丸坊主剪定は、まさしく「理想の樹形の骨格」を作る作業です。「この位置から芽が出て、こう伸びて…」と、半年後の姿を想像しながら、不格好になることを恐れずに思い切って切ることが成功の秘訣です。
パキラは1年でどれくらい成長しますか?
パキラの成長速度は、育成環境、特に日照量と鉢の大きさによって大きく左右されます。
適切な環境(レースカーテン越しの明るい室内、適切な水やりと肥料)であれば、生育旺盛な株は1年で15cm〜30cmほど伸びることも珍しくありません。特に5月〜7月の生育期は、観察していると分かるほど、新しい葉を次々と展開します。
原産地の中南米では、パキラは20メートルを超える高木になる植物です(出典:山科植物資料館など)。鉢植えで育てる場合は、根が伸びるスペースが限られるため、成長が抑制されます。
鉢が小さいと根が伸びるスペースがなくなり(根詰まり)、成長が抑制されます。逆に言えば、あまり大きくしたくない場合は、あえて植え替えの間隔を空け、小さな鉢で管理する「根域制限」というテクニックもあります。
逆に言えば、定期的な剪定で大きさをコントロールすることは、室内でパキラを楽しむために不可欠な作業なのです。
パキラを丸坊主にする手順と剪定後の育て方
参考
- パキラを丸坊主にするにはどうしたらいいですか?
- 剪定後に芽が出ないときの原因
- 新芽を育てるための最適な置き場所
- 風通しの良い環境で管理しよう
- もうパキラを丸坊主にしないための育て方
パキラを丸坊主にするにはどうしたらいいですか?
パキラを意図的に丸坊主(強剪定)にする場合は、正しい手順を踏むことで失敗のリスクを最小限に抑えられます。これは、ひょろひょろになった樹形を根本からリセットするための「外科手術」です。
手順1:準備(時期、道具、心構え)
前述の通り、剪定時期が5月〜7月であることを確認します。そして、アルコールなどで消毒した、切れ味の良い清潔な剪定バサミを用意してください。幹が太い場合は、園芸用のノコギリや、癒合剤(切り口保護剤)も準備しておくと万全です。
手順2:水やりを控え、土を乾かす
剪定の数日前から水やりを控え、土を少し乾かし気味にしておきます。これは、剪定後に水の吸い上げが激減するため、鉢内が過湿になるのを防ぎ、根腐れを予防する目的があります。
手順3:切る位置を決める
幹や枝にある「成長点」を確認します。どの高さから新芽を芽吹かせたいかを明確にイメージし、切る位置(成長点の5mm〜1cm上)を決めます。複数の幹がある場合は、全体のバランスを見て高低差をつけると、新芽が出たときに自然な樹形になります。
手順4:剪定の実行
決めた位置を、思い切ってハサミやノコギリで一気に切り落とします。ためらって何度も切りつけると、切り口がギザギザになり、表面積が増えて乾燥しやすくなるほか、雑菌の温床にもなります。
手順5:切り口のケア(推奨)
特に直径1cmを超えるような太い幹や枝を切った場合、切り口から雑菌が入ったり、水分が蒸発しすぎたりするのを防ぐため、「癒合剤(ゆごうざい)」という保護剤を塗っておくと安心です。
切り口にフタをするイメージで、チューブから出して塗布します。園芸店やホームセンターで「カルスメイト」などの商品名で入手できます。
剪定後に芽が出ないときの原因
剪定から2〜3週間経っても新芽が出てこない場合、多くの人が「失敗した」と諦めかけますが、まだ望みはあります。いくつかの原因が考えられるため、以下の点を確認してみてください。
| 主な原因 | 解説と対策 |
|---|---|
| 1.水のやりすぎ(根腐れ) | これが最も多い致命的な原因です。葉がないと吸水量が激減します。それなのに剪定前と同じペースで水やりを続けると、土が常に湿った状態になり、根が呼吸できずに腐ってしまいます。根が死ねば、新芽は絶対に出ません。対策:今すぐ水やりを止め、徹底的に土を乾かしてください。幹を軽く触ってみてブヨブヨしていないか確認します。もし柔らかい部分があれば、その部分は残念ながら腐っています。 |
| 2.剪定時期の間違い | 秋や冬の休眠期に剪定した場合、新芽を出す体力がありません。残念ながら、暖かくなる春まで待つしかありませんが、剪定のダメージから回復できず、そのまま枯れてしまうリスクも高いです。 |
| 3.日照不足 | 新芽を出すためには多くのエネルギーが必要です。暗すぎる場所に置いていると、植物が「今は成長する時期ではない」と判断し、新芽を出すのをためらってしまいます。対策:レースカーテン越しの明るい場所へ移動させましょう。 |
| 4.株の体力不足 | もともと弱っていた株(例:購入直後、長期間の栄養不足、根詰まり)の場合、剪定のダメージに耐えられず、新芽を出す体力がないことがあります。対策:活力剤(肥料ではありません)を与えるのも一つの手ですが、基本は下記の置き場所と風通しを守って見守ることです。 |
| 5.単なる時間経過 | 環境や個体差によっては、新芽が出るまで3週間〜1ヶ月以上かかることもあります。特に、幹の古い部分から芽を出す場合は、新しい成長点を形成する必要があるため、時間がかかる傾向にあります。対策:幹が固い限り、諦めずに気長に待ちましょう。 |
新芽を育てるための最適な置き場所
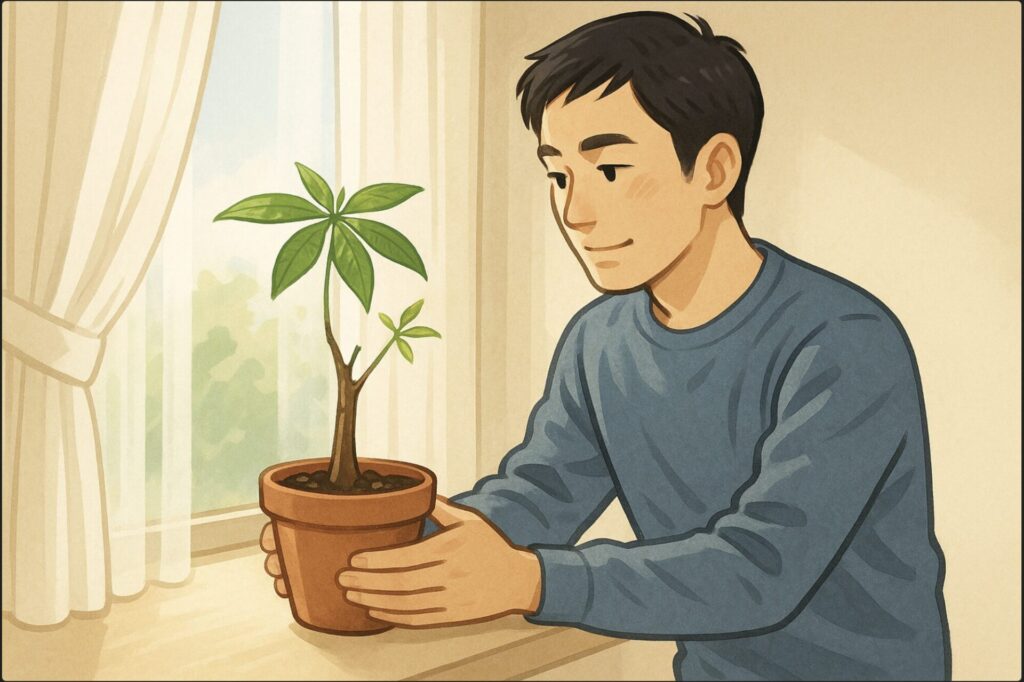
観葉スタイル・イメージ
剪定で丸坊主になったパキラは、人間で言えば「大手術を終えた直後」であり、いわば集中治療室(ICU)にいる状態です。光合成を行う「葉(=エネルギー生産工場)」をすべて失い、幹に蓄えられた体力だけで生き延びている、非常にデリケートな状況だと理解してください。
この状態のパキラに最も必要なのは、強い刺激ではなく、「安定した、負担のない環境」です。この時期の置き場所の選択が、復活できるかどうかを左右する最大のポイントとなります。
結論から言えば、最適な置き場所は「レースカーテン越しの、風通しの良い明るい日陰」です。
絶対に避けるべき「直射日光」のワナ
ここで最も多くの人が犯してしまう間違いが、「新芽を出すためにもっと光を!」と焦り、ベランダや窓辺の直射日光に当てることです。これは回復どころか、致命的なダメージを与える「最悪の選択」です。
これには2つの明確な理由があります。
- 幹焼け(みきやけ)の発生:植物の幹は、通常はたくさんの葉によって直射日光から守られています。葉を失った丸裸の幹に夏の強い直射日光が当たると、幹の表面温度が急激に上昇します。これにより、樹皮のすぐ下にある細胞組織(形成層など、植物が成長するために重要な部分)が文字通り火傷を起こし、壊死してしまう「幹焼け」を引き起こします。幹焼けを起こした部分は黒く変色し、その部分からは二度と新芽が出なくなります。広範囲に及ぶと、株全体が枯死してしまいます。
- 新芽の葉焼け:さらに、仮に幹焼けを免れても、次に出てくる新芽は非常にデリケートです。生まれたての葉は、まだ表面を保護するクチクラ層(ワックス層)が未発達な「赤ちゃんの肌」と同じです。そこに強すぎる光(特に紫外線)が当たると、葉緑素が破壊されてしまい、すぐに「葉焼け」を起こして茶色くチリチリになってしまいます。
光以外の「置き場所」の注意点:温度と風
ICU(集中治療室)に必要なのは、光の管理だけではありません。「安定した温度」と「風の管理」も同様に重要です。
- 温度管理:パキラが活発に新芽を出すには、20℃〜30℃程度の安定した温度が理想です。剪定後の株を、夜間に冷え込む窓際や、エアコンの冷風が直撃する場所に置くのは絶対に避けてください。寒暖差は大きなストレスになります。
- 風の管理:エアコンや扇風機の風が直接当たる場所もNGです。せっかく出ようとしている小さな新芽は、乾燥した風にさらされると、開く前に干からびて黒くなってしまいます。
ただし、空気がよどんだ場所は鉢内が蒸れるため、「優しい空気の流れ(風通し)」があるリビングの中央などが理想的です。
回復のプロセスと「社会復帰」
「明るい日陰」で体力を回復させ、徐々に慣らす:新芽を出すためには、強すぎる直射日光ではなく、柔らかい「間接光(散光)」が必要です。
レースカーテン越しに差し込む光は、まさにこの間接光であり、幹焼けや葉焼けのリスクを最小限に抑えつつ、新芽の形成に必要なエネルギー(光合成)を幹や新芽自身に促すことができます。
まずはこの「明るい日陰」で新芽が出るのを待ち、新芽がしっかりと展開して葉が固く(色が濃く)なってきたら、それは「ICUからの退院」のサインです。
退院後もすぐに直射日光に当てるのではなく、まず1〜2週間かけて、少しずつ窓辺に近い場所に移動させるなど、徐々に光の量に慣らしていく(順化させる)ことで、健康な株に育て直すことができます。
風通しの良い環境で管理しよう
剪定後は、特に風通しを良くすることが、置き場所と同じくらい重要です。
葉がない状態では、植物からの蒸散(葉から水分を放出すること)が行われません。このため、鉢の中の水分が非常に蒸発しにくい状態になっています。この状態で空気がよどんだ場所に置くと、鉢の中が常にジメジメした状態になり、カビや根腐れの原因菌が繁殖しやすくなります。
風通しを良くすることは、以下の2つの重要な効果をもたらします。
- 根腐れの防止:土の表面から水分を適度に蒸発させ、鉢内部に新しい空気を送り込む手助けをします。これにより、根が呼吸できる環境を保ちます。
- 病害虫の予防:ジメジメして空気がよどんだ場所は、カビや、ハダニ・カイガラムシといった害虫が好む環境です。風通しを良くすることで、これらの発生を物理的に抑制できます。
窓を開けて空気を循環させるか、サーキュレーターなどで鉢周りの空気を優しく動かしてあげる(直接風を当てない)と、土の乾燥が促され、根腐れ防止に非常に効果的ですよ。
【最重要】剪定後の水やりについて
前述の通り、剪定後は水やりを「徹底的に控える」ことが最も重要です。
葉がないパキラは、ほとんど水を必要としません。「新芽が出ないのは水が足りないからかも…」と水を与えてしまうのが、最もよくある失敗パターンです。
新芽が確認できるまでは、『水やりはしない』くらいの気持ちでいてください。
土の表面が乾いてから、さらに1〜2週間待つくらいの感覚でも遅くありません。幹が少しシワシワになってきても、まだ我慢です。水を与えたくなる気持ちを抑えることが、丸坊主からの復活を成功させる最大の鍵です。
もうパキラを丸坊主にしないための育て方

観葉スタイル・イメージ
「丸坊主」という強剪定は、植物にとって大きな負担となります。これを避けるためには、日頃のこまめなメンテナンスが有効です。樹形が大きく乱れる前に、こまめに手を加えていきましょう。
摘心(てきしん)
これは、新しく伸びてきた枝の先端にある「芽」を摘み取る簡単な作業です。上への成長を止めることで、エネルギーが脇に回り、脇から新しい芽を出させる(=枝数を増やす)効果があります。
やり方は、新しく伸びてきた枝の先端、まだ柔らかい緑色の部分を、指先で摘み取るだけです。すると、摘み取ったすぐ下の葉の付け根から、2〜3本の新しい脇芽が伸びてきます。これにより、葉の密度が高く、こんもりとした樹形を維持しやすくなります。
軽い切り戻し
丸坊主にするまで放置せず、「ちょっとこの枝が伸びすぎたな」「ここから枝が出ると不格好だな」と感じたタイミングで、その枝だけを剪定(切り戻し)します。
この方法なら、他の多くの葉が光合成を続けてくれるため、株への負担は最小限で済みます。これを「生育期(5月〜7月)」の間に数回に分けて行うことで、株への負担を分散させつつ、常に理想の樹形をキープできます。
結局のところ、ひょろひょろにさせないこと、つまり「日当たりと風通しの良い置き場所を確保する」ことが、結果的に丸坊主剪定を避けるための一番の近道と言えます。
十分な光があれば、パキラは無理に背を伸ばす必要がなくなり、節間が詰まった丈夫な枝葉を展開します。これが健康的な樹形の基本です。
パキラを丸坊主から復活させる育て方まとめ
チェックリスト
- パキラがひょろひょろになる原因は主に日照不足
- ひょろひょろ(徒長)を治すには剪定が必要
- 丸坊主剪定の最適な時期は生育期の5月~7月
- 秋や冬の休眠期に丸坊主にするのは非常に危険
- 剪定道具は必ず火やアルコールで消毒する
- 切れ味の良いハサミで一気に切ることが大切
- 新芽が出る「成長点」の少し上で切ると回復が早い
- 剪定後は「レースカーテン越しの明るい日陰」に置く
- 直射日光は「幹焼け」の原因になるため絶対に避ける
- 剪定後は葉がないため水の吸い上げが激減する
- 剪定後に芽が出ない最大の原因は「水のやりすぎ(根腐れ)」
- 新芽が出るまで水やりは徹底的に控える
- 土の表面が乾いてから1週間以上待つくらいで良い
- 風通しを良くして鉢の蒸れを防ぐ
- 新芽が出るまで3週間~1ヶ月以上かかる場合もある
- 丸坊主を避けるには日頃の「摘心」や「軽い切り戻し」が有効
