
観葉スタイル・イメージ
大切に育てているパキラの幹が、根本から茶色く硬くなる「パキラの木質化」という現象に、不安を感じていませんか。これが順調な成長の証なのか、それとも枯れる前兆や根腐れのサインなのか、見分け方が知りたいですよね。
また、下の葉が次々と落ちたり、幹がひょろひょろと頼りなく伸びてしまい、パキラの木がスカスカするのはなぜですか?と悩んでいる方もいるでしょう。この状態は、見た目が寂しいだけでなく、パキラが「助けて」とサインを出しているのかもしれません。
理想の樹形を保つためには剪定や切り戻しが欠かせません。しかし、どこを切れば良いのか、新芽を出すための成長点の見極め方や、剪定後の管理方法が分からないと不安です。
この記事では、パキラの木質化の正しい診断方法から、乱れた樹形を整える適切な剪定、さらには剪定で切り取った枝を活用した挿し木での増やし方まで、あなたのパキラを元気に再生させる秘訣を、順を追って詳しく解説します。
ポイント
- 木質化が健康か病気か見分ける方法
- パキラがひょろひょろになる原因
- 正しい剪定と切り戻しのテクニック
- 剪定した枝で挿し木を成功させるコツ
コンテンツ
パキラの木質化は病気のサイン?

観葉スタイル・イメージ
パキラの幹が変色してくると、多くの人が「病気かもしれない」と心配します。しかし、それが必ずしも悪い兆候とは限りません。ここでは、パキラが示す様々なサインを正しく読み解き、それが健康な成長の証なのか、それとも根腐れなどの危険なトラブルなのかを詳しく解説します。
参考
- 根腐れとの見分け方を解説
- 下の葉が落ちる原因
- ひょろひょろな姿になる理由
- パキラの木がスカスカするのはなぜですか?
- 理想の樹形を保つコツ
根腐れとの見分け方を解説

観葉スタイル・イメージ
パキラの幹が茶色く硬くなる「木質化」は、多くの場合、病気ではなく正常な成長過程です。人間で言えば「大人になる」のと同じで、植物が成熟し、自重を支えたり、より多くの水分や養分を運んだりするために幹が太く丈夫になる現象です。
これは細胞壁に「リグニン」という物質が沈着することで起こり、特に根元に近い部分から徐々に進行します。
ただし、最も警戒すべきは「根腐れ」による幹の変色です。根腐れは、水のやりすぎや土の排水不良によって土壌が常に湿った状態になり、根が呼吸できず(酸素不足)、腐敗してしまう深刻なトラブルです。
農林水産省も土づくりの基本として、土壌の通気性や排水性の重要性を指摘しています。これら二つの現象は、見た目が似ているようで、パキラの生死を分ける全く異なる状態です。見分け方が非常に重要になります。
正常な木質化と根腐れの見分け方:パキラの幹を「触って」「嗅いで」チェックすることが、最も確実な診断方法です。以下の表で、ご自身のパキラの状態を慎重に確認してみてください。
| チェック項目 | ①正常な木質化(健康) | ②根腐れ(危険な状態) |
|---|---|---|
| 幹の感触 | 表面は硬く、木材のようにしっかりしている | 柔らかい、ブヨブヨ・フカフカしている、押すとへこむ |
| 幹の色 | 薄茶色からこげ茶色。根元から徐々に均一に広がる | 黒ずんでいる、灰色っぽい、水っぽく変色している |
| 匂い | 特になし(土や木の匂い) | ドブのような酸っぱい匂い、明らかな腐敗臭がする |
| 他の症状 | 葉は元気で新芽も出る。下の葉が落ちることはある | 葉が急に黄色くなる、葉がしおれる、新芽の成長が止まる |
幹がブヨブヨしたら緊急事態です!
もし幹を触ってみて少しでも柔らかい感触(ブヨブヨ・スカスカ)がしたり、異臭がしたりする場合は、根腐れがかなり進行している可能性が非常に高いです。根腐れは放置すると、腐敗が幹を伝って上部へと広がり、株全体が枯れてしまいます。
このサインを見つけたら、ためらわずに緊急手術(植え替え)が必要です。すぐに鉢から抜き、腐った黒い根や幹の柔らかい部分を、清潔なハサミで健康な部分が露出するまですべて切り落とします。
その後、新しい清潔な観葉植物用の土に植え替え、水やりは非常に控えめに管理して回復を待ちます。
下の葉が落ちる原因
木質化と同時に下の葉がパラパラと落ちてくると、「やはり調子が悪いのでは?」と心配になりますよね。もちろん、根腐れのサインである場合もありますが、それ以外にもいくつかの理由が考えられます。
①新陳代謝(生理現象)
パキラは成長する際、上へ上へと新芽を展開させます。これは「頂芽優勢」という植物の性質で、一番てっぺんの芽に優先的に栄養が送られます。このとき、株は限られたエネルギーを効率よく使うため、光合成の効率が落ちた古い葉である「下の葉」への栄養供給を止めることがあります。
栄養が来なくなった葉は自然と黄色くなり、やがて落葉します。これは健康な株でも起こる自然な新陳代謝(世代交代)なので、新芽が元気に育っているなら心配しすぎる必要はありません。
②日照不足
室内で育てている場合、特に棚の下段や部屋の奥まった場所では、下の葉まで十分に光が届かないことがあります。植物にとって葉は光合成を行う「工場」です。
光が当たらず、光合成ができない(=エネルギーを作れない)葉は、植物全体から見ると維持コストだけがかかるお荷物となります。そのため、自ら切り離してエネルギーを節約しようとするのです。これが下の葉が落ちる原因として非常に多いパターンです。
③水やりの問題(根腐れ・水切れ)
前述の通り、根腐れを起こしていると、根が機能不全に陥り、水分や養分を正常に吸い上げられなくなります。その結果、葉が枯れ落ちます。
逆に、長期間の水切れ(極度の乾燥)でも、植物は体内の水分を保持するために、水分の蒸発口である葉を自ら落として「休眠状態」に入ろうとします。水のやりすぎ・やらなさすぎ、両極端が同じ「落葉」という症状を引き起こすのです。
新陳代謝かトラブルかの見極め方
下の葉が落ちるのが「新陳代謝」なのか「トラブル」なのかは、新芽の状態と葉の落ち方で見極めましょう。
- 健全な新陳代謝:新芽が元気に次々と出ており、下の葉が「1~2枚ずつ、ゆっくりと」黄色くなって落ちる。
- 危険なトラブル:新芽の成長が止まったり、新芽自体が黒ずんだりしている。下の葉だけでなく、中間の葉や新しい葉まで含めて「一度にたくさんの葉」が黄色くなったり、しおれたりして落ちる。
後者の場合は、日照不足や根のトラブルを強く疑い、置き場所の変更や植え替えを検討してください。
ひょろひょろな姿になる理由

観葉スタイル・イメージ
パキラの幹や枝が、本来の力強さを失い、太くならずに細く間延びしたように伸びる「ひょろひょろ」な状態。これは「徒長(とちょう)」と呼ばれる、植物が発する明確なSOSサインです。
徒長の最大の原因は、圧倒的な日照不足です。
植物は、生きていくためのエネルギーを「光合成」によって作ります。JST(科学技術振興機構)の解説にもあるように、光合成には十分な光が不可欠です。暗い場所に置かれたパキラは、そのわずかな光を少しでも多く浴びようとして、光のある窓の方向へ必死に体を伸ばそうとします。
このとき、幹を太くしたり、葉を密に茂らせたりするエネルギーをすべて「上へ伸びる」ことだけに使ってしまうため、節と節の間が異常に長く、弱々しい姿になってしまうのです。
徒長を防ぎ、幹を太く丈夫にする環境づくり
パキラをひょろひょろにさせず、幹をがっしりと太く木質化させるには「日光」と「風」が不可欠です。
- 日光:室内でも必ずレースカーテン越しの日光が当たる窓際など、最も明るい場所に置きます。ただし、真夏の強い直射日光は葉焼けの原因になるため避けてください。
- 風通し:空気が循環する場所に置きます。植物は適度な風(揺れ)を感じると、倒れないように自らを強くしようと、幹を太く丈夫に育てる性質があります。窓を閉め切る場合は、サーキュレーターなどで空気を優しく動かすのも非常に効果的です。
もし環境が許すなら、最も良いのは春から秋(最低気温が15度以上を安定して超える時期)に屋外の半日陰で管理することです。直射日光は葉焼けの原因になるため厳禁ですが、屋外の明るい光と自然の風に当てることで、室内管理とは比較にならないほど幹は太く丈夫に育ちます。
パキラの木がスカスカするのはなぜですか?
「日当たりに気をつけているつもりなのに、気づいたら幹の途中が寂しくなってしまった…」
「パキラの木がスカスカするのはなぜですか?」
これは、パキラを室内で数年育てている多くの方が直面する、非常によくある悩みです。
この「スカスカ」な状態は、ある日突然起こるのではなく、室内栽培特有の環境要因によって、数ヶ月から数年かけてゆっくりと進行する現象です。
主な原因は、これまで解説した「徒長(ひょろひょろ)」と「下の葉が落ちる」という2つの現象が、止められない悪循環として組み合わさって発生することにあります。
スカスカな樹形が完成するまでの悪循環
この現象は、特に室内での栽培環境が引き金となります。
簡単な流れ
- 一方向からの光による「徒長」:屋外の太陽は真上から降り注ぎますが、室内の場合、光は主に横にある窓から一方向でしか当たりません。パキラは光合成をするために、そのわずかな光を求めて、窓のある方向へ、そして光の強い上へ上へと必死に枝を伸ばします。これが幹や枝をひょろひょろにさせる「徒長」の始まりです。
- 上部の葉による「自己遮蔽」:徒長して上部に新しく展開した葉が、まるで傘のように幹の中間部分や株元に影を落とします。この現象を「自己遮蔽(じこしゃへい)」と呼びます。室内の一方向からの弱い光では、この影を解消することができません。
- 日照不足による「下葉の脱落」:影になり、慢性的な日照不足に陥った中間部分や下部の古い葉は、光合成でエネルギーを作ることができなくなります。植物にとって、エネルギーを作れない葉は維持コストだけがかかる「お荷物」です。そのため、株はエネルギーを節約するため、それらの葉への栄養供給を止め、自ら切り離してしまいます(落葉)。
- 「頂芽優勢」によるエネルギーの偏り:同時に、植物の「頂芽優勢」という性質により、成長エネルギーは常に先端の芽(頂芽)に集中し続けます。これにより、影になって日照不足の下の節にある「休眠芽」は、光もエネルギーも足りないため、目覚めるきっかけを完全に失ってしまいます。
- 「ほうき樹形」の完成:この1~4のサイクルが繰り返された結果、上へ上へと伸びた枝の先端にだけ葉が残り、光が当たらず葉が落ちた幹の中間部分は、枝も葉もない「スカスカ」な状態になってしまうのです。これが、まるで「ほうき」を逆さにしたような樹形の正体です。
これは単なる見た目の問題ではありません。上部にしか葉がないため、株全体で光合成できる総量が減り、徐々に株の体力(幹や根に蓄えられたエネルギー)が失われていきます。
また、頭でっかちのバランスの悪い樹形は、植物自体の重さや、何かが少しぶつかった衝撃で幹が折れてしまうリスクも高まります。
この悪循環に陥ってしまった状態をリセットし、再び低い位置からも葉を茂らせるためには、次の章で解説する「剪定(せんてい)」という外科的な処置が、唯一にして最も効果的な方法となります。
理想の樹形を保つコツ
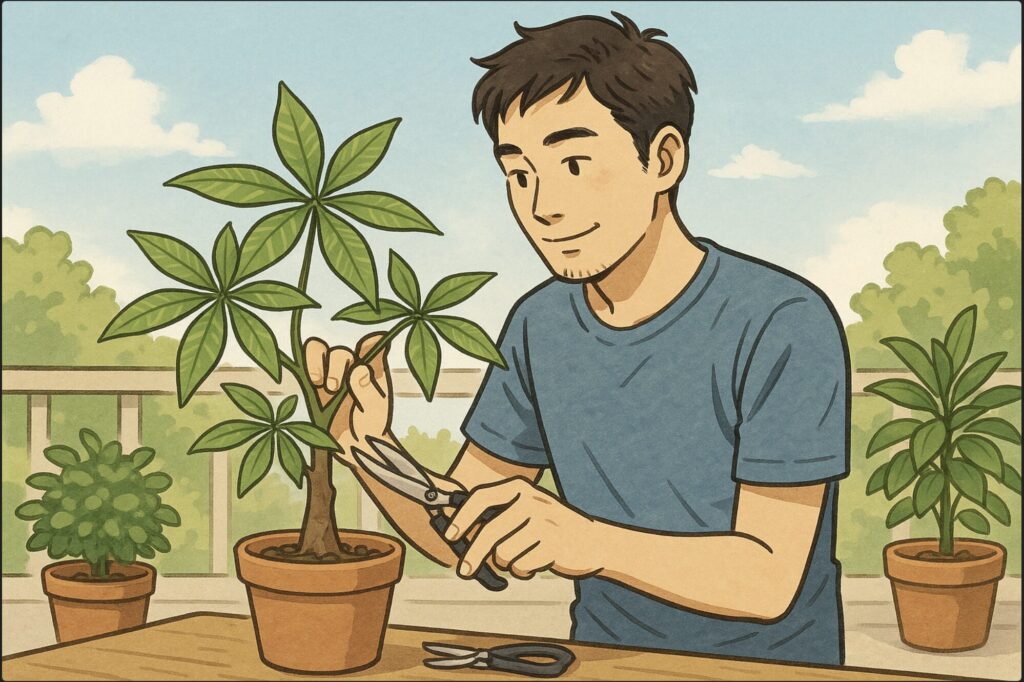
観葉スタイル・イメージ
スカスカやひょろひょろの状態を防ぎ、カフェや雑誌で見るような「こんもりと葉が茂った」理想の樹形を保つには、「環境改善(予防)」と「剪定(治療)」、この2つのアプローチが必要です。
1.環境の抜本的な改善(予防)
前述の通り、まずは徒長させないことが第一です。パキラが元気に育つ「明るい場所」と「風通し」を確保することが大前提となります。
特に室内では、季節によって太陽の光が入る角度が変わるため、定期的に置き場所を見直すことも重要です。環境が悪いままでは、いくら剪定しても再び同じように徒長してしまいます。
2.定期的な剪定(治療と維持)
パキラは非常に成長が早い植物です。原産地では10mを超える高木になるほど生命力が旺盛です。放置すれば、日本の室内環境でも天井につくほど上に伸びてしまい、バランスが悪くなります。
定期的に剪定(切り戻し)を行うことで、高さを抑えることができます。
それだけでなく、植物の「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質を打破し、それまで眠っていた脇から新しい芽(脇芽)が出るのを促す効果があります。これにより、葉の密度を高め、こんもりとした樹形を作ることができるのです。
すでにスカスカになってしまった株も、勇気を出して剪定することで、低い位置から新芽を出させ、樹形を根本から作り直すことが可能です。
パキラの木質化と剪定での再生
パキラの樹形が乱れてしまった場合、最も効果的で確実な再生方法が「剪定」です。木質化した幹であっても、適切な時期と方法で行えば、驚くほど元気に新芽を吹かせることができます。ここでは、剪定の具体的なテクニックと、その後の管理方法について詳しく解説します。
参考
- 剪定の適切な時期と手順
- 成長点を残すのが重要
- 思い切った切り戻しの方法
- 剪定後に新芽を吹かせる管理
- 挿し木でパキラを増やす手順
剪定の適切な時期と手順
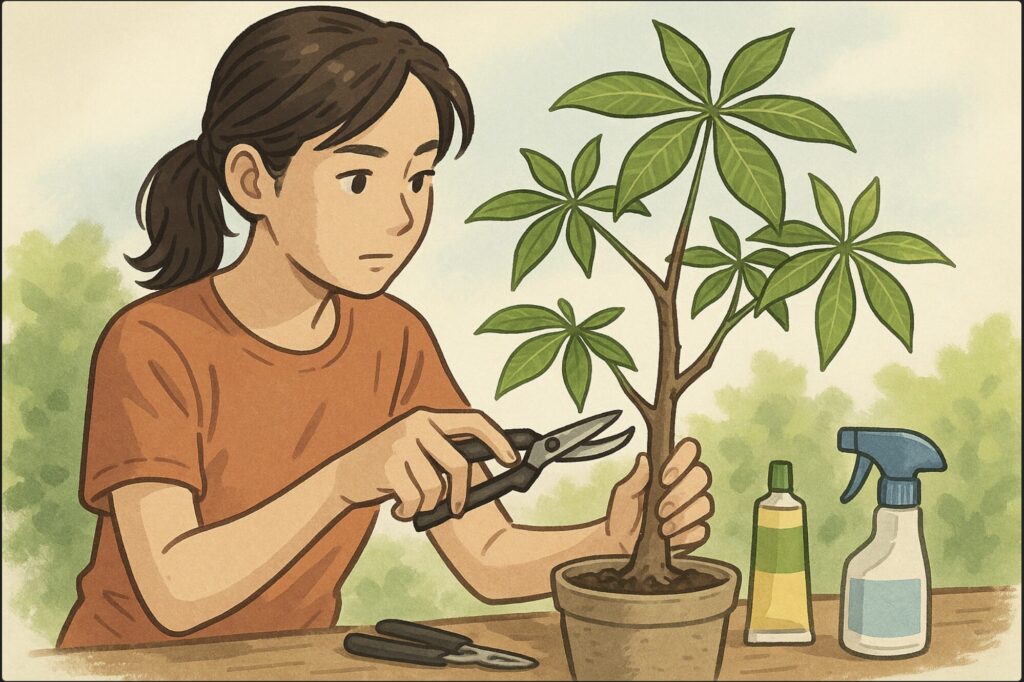
観葉スタイル・イメージ
ひょろひょろに伸びたり、スカスカになったりしたパキラの樹形を整えるには、剪定が最も効果的な方法です。パキラは非常に強健な植物なので、適切な時期に行えば、初心者の方でも失敗のリスクはほとんどありません。
剪定のベストシーズン
剪定の適期は、パキラの成長期である5月~7月です。この時期は、植物の成長に最も適した安定した気温(多くの地域で最低気温15℃~20℃以上)が続き、株の生命力が最も旺盛になります。
そのため、剪定によるダメージからの回復が非常に早く、カットしてから数週間で力強い新芽が出てきます。
この時期の剪定は避けてください!
- 真夏(35度を超える猛暑日):人間が夏バテするように、植物も高温すぎると成長が一時的に鈍化します。この時期の強剪定は株に大きな負担をかけます。
- 秋~冬(9月下旬以降):気温が下がり始めるとパキラは成長を止め、休眠期に入ります。この時期に切ると、新芽が出る力が残っておらず、切り口が塞がらないまま雑菌が入ったり、そこから枯れ込んだりするリスクが非常に高くなります。
剪定の基本手順
- 道具の準備:切れ味の良い清潔な剪定バサミを用意します。切り口が潰れると雑菌が入りやすくなるため、よく切れることが重要です。使用前にアルコールスプレーや熱湯で刃先を消毒しておくと、病気の感染を防げて万全です。
- 完成形をイメージする:いきなり切るのではなく、少し離れてパキラ全体を眺め、「どのくらいの高さにしたいか」「どのあたりから葉を茂らせたいか」を具体的にイメージします。
- カットする:後述する「成長点」の少し上を狙って、思い切ってカットします。中途半端に枝先だけを切ると、かえって不格好になることもあるため、勇気を持つことが大切です。
- 切り口のケア(推奨):特に直径1cmを超えるような太い幹や枝を切った場合は、切り口から雑菌が入ったり、水分が蒸発しすぎたりするのを防ぐため、園芸用の「癒合剤(ゆごうざい)」を塗っておくと安心です。
成長点を残すのが重要
パキラの剪定を成功させるか失敗させるかを分ける、最も重要な知識が「成長点」を意識することです。なぜなら、新しい枝や葉は、必ずこの成長点からしか出てこないからです。この場所を無視して剪定しても、期待した場所から新芽が出ることは決してありません。
成長点(節)とは何か?
成長点とは、植物学でいう「節(ふし)」のことです。幹や枝をよく観察してみてください。竹の「節」のように、幹のところどころにわずかな膨らみや、横に筋が入っている部分があるのが分かります。
具体的には、葉や枝が(または、かつて葉が)生えていた付け根の部分を指します。葉が落ちた跡が、半月状の「スマイルマーク」のようになっている場合もあります。これが「節」です。
この節には、「休眠芽(きゅうみんが)」と呼ばれる、次の出番を待っている新芽のタネが隠されています。逆に、節と節の間のツルツルした部分は「節間(せっかん)」と呼ばれ、ここには芽を作る組織がありません。そのため、節間をいくら眺めていても新芽は出ません。
どこで切るのが正解か
剪定する際は、この成長点(節)の「すぐ上」、具体的には5mm~1cm程度上でカットするのが鉄則です。この位置で切ることで、切り口のすぐ下にある休眠芽が「自分が新しいリーダーだ」と認識し、成長を始めるための刺激を受けます。
注意:節間(ツルツルした部分)で切ってはいけません
もし成長点を無視して節と節の真ん中(節間)で切ってしまうと、どうなるでしょうか?
- 切った場所(節間)からは芽が出ません。
- 植物は、仕方なく「切られた場所よりも下にある、一番近い節」から新芽を出そうとします。
- 結果として、新しく出た芽から、あなたが剪定した切り口までの間(数cmの節間)が、意味のない「枯れ枝」として残ってしまいます。
この残った部分は見栄えが悪いだけでなく、そこから水分が蒸発して幹全体が弱ったり、雑菌が入って枯れ込んだりする原因にもなります。必ず節のすぐ上で切ることを徹底してください。
Q.木質化した硬い幹からも新芽は出ますか?
A.はい、出る可能性は非常に高いです。これはパキラの強さの証です。
幹が茶色く木質化していても、それは表面の樹皮が硬くなっただけです。その樹皮の下の「節」には、緑色の若い枝と同じように、休眠芽がしっかり生きて眠っています。
もちろん、緑色で成長が活発な若い枝に比べると、硬い樹皮を破って新芽が出るまでに少し時間がかかることもあります(数週間余計にかかることも)。しかし、適切な時期(5月~7月)に、節の上で剪定すれば、木質化した幹からでも元気に発芽します。
ひょろひょろに伸びたパキラを低い位置で仕立て直す際は、木質化した部分で切ることを恐れず、自信を持って剪定してください。
思い切った切り戻しの方法
樹形がひどく乱れてしまった場合(例:下葉がすべて落ちて上部だけに葉が茂る「ほうき状」になった、徒長してひょろひょろになり自立できない、天井に届くほど高くなりすぎた)や、株全体が弱っているわけではないものの、低い位置から根本的に仕立て直したい場合には、葉がまったくない状態にする「丸坊主」のような、思い切った切り戻しも非常に有効な手段です。
「葉が全部なくなったら、光合成ができなくて枯れてしまうのでは?」 このように、すべての葉を切り落とすことに強い不安を感じるかもしれません。
しかし、適切な時期(成長期の5月~7月)であり、根腐れなどを起こしていない健康な株であれば、まず問題ありません。パキラは幹や根に十分なエネルギーを蓄えているため、その貯金を使って新しい芽を吹かせる力を持っています。
切り戻しの最大の目的:頂芽優勢の打破
植物には一般的に「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。これは、一番てっぺんにある芽(頂芽)に優先的に成長ホルモンが送られ、そこが最も強く伸びていく仕組みのことです。
この性質がある限り、下のほうにある芽(成長点)は「今は自分の出番ではない」と判断し、眠ったまま(休眠芽)になります。
思い切った切り戻しによってこの頂芽を物理的に取り除くことで、頂芽優勢のバランスが崩れます。これにより、頂芽に抑えつけられていた下部の休眠芽が一斉に目覚め、「自分が次のトップになろう」と成長を始めるのです。
これが、切り戻しによって脇からたくさんの新芽が吹き出しやすくなるメカニズムです。
切り戻しのメリット
- 樹高を劇的に低くリセットできる。
- 複数の成長点が同時に動き出すため、枝数が増え、こんもりとした樹形を作りやすい。
- 株のエネルギーが新芽の展開に集中する。
どこで切るべきか?
ひょろひょろに伸びた幹を、思い切って好みの高さでカットします。例えば、「床から30cmの高さで仕立て直したい」と決めたら、その位置でカットします。
ただし、絶対に守るべきルールは、必ず「成長点(節)」のすぐ上(5mm~1cm程度)で切ることです。節と節のツルツルした中間部分で切ると、そこから芽が出ずに切り口から枯れ込むリスクがあります。
木質化した茶色い幹の部分でも、よく見れば必ず節(葉が落ちた跡)がありますので、その位置を確認してからハサミを入れてください。
切り戻しのリスクと注意点
非常に有効な方法ですが、株にとっては大きな手術です。以下のリスクを理解した上で実行してください。
- 時期の厳守:成長期(5~7月)を逃すと、新芽が出る体力が残っておらず、そのまま枯れてしまうリスクが非常に高いです。
- 健康な株限定:すでに根腐れで弱っている株に丸坊主を行うと、回復できずに枯れる可能性が高まります。根腐れの場合は、まず植え替えと根の整理が最優先です。
- 回復までの時間:新芽が出るまでには数週間~1ヶ月以上かかる場合もあります。その間は後述する「剪定後の管理(特に水やりを極端に控える)」を徹底する必要があります。
剪定後に新芽を吹かせる管理
剪定した後の管理方法は、通常時と大きく異なります。ここで管理を間違えると、新芽が出なかったり、最悪の場合枯れてしまったりするため、細心の注意が必要です。特に注意すべきは「水やり」です。
最重要:剪定後の水やりは「超」乾燥気味に!
剪定によって葉がほとんどなくなったパキラは、植物が水分を蒸発させる「蒸散(じょうさん)」の量が激減します。この状態で剪定前と同じように水を与え続けると、土がまったく乾かず、ほぼ100%根腐れを起こして枯れてしまいます。
新芽がしっかりと展開し始めるまでは、水やりは厳しく控えてください。土の表面が乾いてから、さらに数日待つくらい、常に乾燥気味を意識します。
水やりの代わりに、霧吹きで幹や枝を湿らせる「葉水(幹水)」を毎日1~2回与えて、幹の乾燥防止と湿度を保つのが非常に効果的です。
剪定後の管理ポイント
- 置き場所:新芽が出るまでは、直射日光を避けた、明るい日陰や半日陰に置きます。葉がない状態で幹に直射日光が当たると「幹焼け」を起こして傷むことがあるためです。新芽が展開し始めたら、徐々に明るい場所へ移動させます。風通しは常に良く保ちましょう。
- 肥料:新芽が元気に伸び始め、葉が数枚開くまでは肥料は一切与えないでください。根が弱っている状態で肥料を与えると「肥料焼け」を起こし、逆効果になります。
挿し木でパキラを増やす手順

観葉スタイル・イメージ
剪定で切り落とした枝は、捨てずに「挿し木(さしき)」に使うことで、新しいパキラの株として増やすことができます。パキラは非常に成功率が高く、園芸の楽しみを広げてくれる作業です。
挿し木の手順
簡単な流れ
- 時期:剪定と同じく、成長期の5月~7月が最適です。気温が高く、発根(根が出ること)のスピードが早いです。
- 挿し穂(さしほ)の準備:切り落とした枝を10~15cmほどの長さにカットします。このとき、枝に「成長点」が最低1つ、できれば2つ以上含まれるようにしてください。枝の先端(天挿し)も、中間の部分(管挿し)も使えます。
- 葉の調整:葉が多すぎると水分が蒸発しすぎるため、葉を1~2枚だけ残します。残した葉も、大きすぎる場合は半分ほどの大きさにハサミでカットして蒸散量を抑えます。
- 水揚げ:挿し穂の切り口(土に挿す側)をカッターナイフなどで斜めに鋭くカットし直し(吸水面積を広げるため)、コップなどに入れた水に1~2時間ほど浸けて吸水させます。
- 土に挿す:挿し木・種まき用の清潔な土(赤玉土小粒やバーミキュライト、挿し木専用土など)をポットに入れます。植物の切り口は雑菌に弱いため、必ず新しい土を使いましょう。(参考:農林水産省 植物防疫所「挿し木等による増殖時の注意点」)土を湿らせた後、割り箸などで穴を開け、挿し穂の切り口を傷めないように挿します。
- 管理:土が乾かないように注意しながら、剪定後の親株と同じく明るい日陰で管理します。1ヶ月ほどで発根し、成長点から新芽が動き始めます。
手軽な「水挿し」も可能
土に挿すのが面倒な場合は、水を入れたコップや瓶に挿しておくだけの「水挿し」でも簡単に発根します。根が出る様子が目に見えるので楽しい方法です。毎日水を替えて清潔に保ちましょう。
根が十分(5~10cmほど)伸びたら、土に植え替えます。ただし、水で出た根(水根)は土用の根と性質が異なるため、土に植え替えた直後は一時的に成長が止まることがあります。
なお、挿し木で育てたパキラは、種から育てた「実生(みしょう)」のパキラとは異なり、根元がぷっくりと太くならないことが多いです。これは、実生株が肥大する「主根」を持つのに対し、挿し木株は「不定根」から成長するためです。
パキラの木質化を理解して育てよう
パキラの木質化や、それに伴う様々な変化、そして再生方法について解説しました。最後に、この記事の要点をリストでまとめます。
チェックリスト
- パキラの木質化は多くの場合、病気ではなく正常な成長
- 幹が茶色く硬くなるのは成熟の証
- 根腐れは幹がブヨブヨし異臭がする
- 下の葉が落ちるのは新陳代謝や日照不足が原因
- ひょろひょろになるのは「徒長」と呼ばれる日照不足
- スカスカな樹形は徒長と葉落ちが同時に起きた状態
- 理想の樹形には日光と風通しが不可欠
- 成長期に屋外の半日陰で管理すると幹が太くなる
- 剪定の適期は成長期の5月から7月
- 剪定時は新芽が出る「成長点」の少し上で切る
- 木質化した硬い幹からでも新芽は出る可能性がある
- 樹形リセットには思い切った「切り戻し」が有効
- 剪定後は葉がないため水やりを厳しく控え乾燥気味に
- 剪定で切った枝は挿し木で増やせる
- 挿し木も5月から7月が成功しやすい
