
観葉スタイル・イメージ
大切に育てている観葉植物のパキラに元気がないと、「もしかしてパキラの寿命が来たのかな?」と心配になりますよね。パキラが枯れる原因は何ですか?という疑問や、平均寿命はどのくらいなのか、葉っぱの異変がサインなのかと、不安は尽きないものです。
また、ハイドロカルチャーやおしゃれな編み込みのパキラの育て方、挿し木での増やし方についても知りたい方が多いのではないでしょうか。実は、パキラは枯れても復活しますか?という問いへの答えは「はい」です。
この記事では、寿命を縮めるNG行動を避け、剪定や植え替えによる延命のコツを、植物のメカニズムにも触れながら詳しく解説します。正しい知識で、あなたのパキラをより長く元気に育てましょう。
ポイント
- パキラの平均寿命と枯れてしまう主な原因
- パキラの寿命を縮めてしまうNGな育て方
- 枯れかけたパキラを復活させる具体的な方法
- 植え替えや剪定などパキラを長く楽しむための延命のコツ
コンテンツ
気になるパキラの寿命と枯れる原因
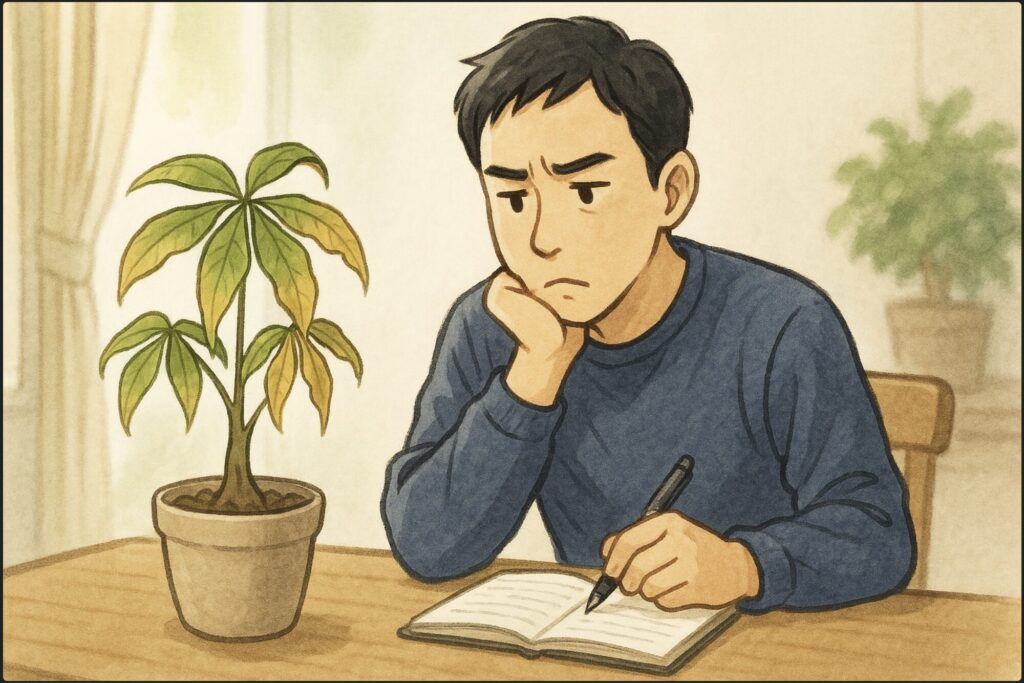
観葉スタイル・イメージ
参考
- パキラの平均寿命はどのくらい?
- パキラが枯れる原因は何ですか?
- 葉っぱの異変は寿命のサイン?
- 編み込みパキラは寿命が短い?
- ハイドロカルチャーでの育て方
パキラの平均寿命はどのくらい?

観葉スタイル・イメージ
大切に育ててきたパキラが10年、15年と時を経て、最近少し元気がなくなってきたように感じると、「とうとう寿命が来たのかもしれない…」と寂しい気持ちになりますよね。
しかし、結論から申し上げると、その心配はほとんどの場合不要です。パキラの寿命は、私たちが想像するよりも遥かに長く、本来は人間の一生を超えるほどのポテンシャルを秘めています。
原産地である中南米の熱帯地域に自生するパキラは、樹高が20メートルにも達する大木に成長し、樹齢100年を超える個体も珍しくありません。この事実からも、パキラがいかに強靭な生命力を持つ植物であるかがわかります。
もちろん、限られた鉢の中で育つ日本の室内環境と、無限の大地が広がる原産地とでは条件が大きく異なります。それでも、その驚異的な生命力は健在で、適切な環境と手入れを施せば数十年単位で成長を続けることが十分に可能です。
園芸愛好家の間では、親子二代にわたって20年、30年と育て続けているという話もよく聞かれます。そのため、育て始めて10年程度で元気がなくなったとしても、それが生物学的な寿命である可能性は極めて低いと言えるでしょう。
「最大寿命」と「生態的寿命」の違い
植物の寿命を考えるとき、この二つの言葉がヒントになります。
- 最大寿命:その生物が、病気や外的ストレスのない理想的な環境で生きられる、遺伝的にプログラムされた最長の寿命。パキラの場合は100年を超えるポテンシャルを指します。
- 生態的寿命:実際に生息する特定の環境下での寿命。栄養不足や根詰まりといった環境ストレスによって、最大寿命よりも短くなります。
私たちが鉢植えで育てるパキラの寿命は、この「生態的寿命」をいかに延ばしてあげられるかにかかっています。
ではなぜ、10年ほど経つと元気がなくなるケースが多いのでしょうか。それは「寿命」ではなく、むしろ鉢という限られた飼育環境が限界を迎えているサインなのです。
10年という歳月は、土の栄養分が枯渇し、根が鉢の中でパンパンになり、水はけが悪くなるのに十分な時間です。人間で例えるなら、長年住んだ家のインフラが古くなり、リフォームや引っ越しが必要な時期に来ているのと同じ状態と言えます。
つまり、元気がなくなったのは「老化」が直接の原因ではなく、「住環境の悪化」が引き起こしている不調なのです。この問題を解決してあげることで、パキラは再び力強く成長を始めます。
寿命を心配するよりも、まずはパキラが置かれている環境を見直すこと。それが、元気を取り戻すための最も確実な第一歩となります。
パキラは本来、驚くほど長寿な植物です
- ポテンシャルとして100年以上の「最大寿命」を持っています。
- 室内での寿命は「生態的寿命」と呼ばれ、育て方次第で大きく変わります。
- 10年程度で元気がなくなるのは寿命ではなく、植え替えなど環境のリセットが必要なサインです。
- 適切なメンテナンスを続ければ、50年近く共に暮らすパートナーになり得ます。
その生命力を信じて、丁寧にお世話をしてあげましょう。
パキラが枯れる原因は何ですか?

観葉スタイル・イメージ
パキラが枯れてしまう原因のほとんどは、寿命ではなく日々の管理方法にあります。特に注意すべき三大原因が、「水のやりすぎ」「日照不足」「根詰まり」です。これらの原因が複合的に絡み合っているケースも少なくありません。
水のやりすぎ(根腐れ)
植物を枯らす原因として最も多いのが、水の与えすぎによる「根腐れ」です。可愛がるあまり、土がまだ湿っているのに水やりを繰り返してしまうと、土の中の水分が過剰になり、根が深刻な酸欠状態に陥ります。
根も人間と同じように呼吸をしており、酸素がなければ正常に機能できません。
酸欠状態が続くと根の細胞が壊死し、やがて腐敗してしまいます。腐った根は水分や養分を吸収する能力を失うため、結果として植物全体が枯れてしまうのです。(参照:NHK みんなの趣味の園芸)
見逃さないで!根腐れの危険なサイン
- 幹の根元がブヨブヨする:健康な幹は硬いですが、根腐れが進行すると幹の下部から腐敗が始まり、柔らかくなります。
- 土から異臭がする:腐敗菌が繁殖し、ドブのような嫌な臭いが発生します。
- 水をあげても葉が元気にならない:根が水を吸えないため、水やりをしても葉がしおれたままになります。
- 土の表面にカビが生える:鉢内が常に過湿状態である証拠です。
これらの症状が見られたら、すぐに対処が必要です。
日照不足
パキラは比較的日陰に強い「耐陰性」を持つ植物ですが、それは「日陰でもなんとか耐えられる」という意味であり、「光がなくても育つ」わけではありません。
植物は光合成によって生きるためのエネルギーを作り出しているため、長期間光が不足するとエネルギー不足に陥り、徐々に弱ってしまいます。葉の色が薄くなったり、日光を求めて枝が細く間延びした「徒長(とちょう)」という状態になったりするのは、典型的な日照不足のサインです。
根詰まり
パキラは成長スピードが速い植物です。購入してから1〜2年以上同じ鉢で育てていると、鉢の中が根でパンパンになる「根詰まり」という状態を引き起こします。根詰まりすると、新しい根を伸ばす物理的なスペースがなくなり、水や肥料を効率的に吸収できなくなります。
また、土の中の根の割合が多くなりすぎることで、土が本来持つべき保水性や通気性も失われ、水やりをしてもすぐに土が乾く「水切れ」を起こしやすくなるという悪循環に陥ります。
これらの三大原因の他にも、エアコンの風が直接当たることによる極端な乾燥や、冬場の低温(5℃以下)に晒されることも、パキラの健康を損なう大きな原因となります。
葉っぱの異変は寿命のサイン?

観葉スタイル・イメージ
パキラの葉に現れる様々な変化は、多くの飼い主を不安にさせますが、これらは寿命の訪れを告げるものではありません。むしろ、パキラが「今の環境はちょっとつらいよ」と発している貴重なSOSサインです。
そのサインを正しく読み解き、原因に応じた対処をすることで、パキラは再び生き生きとした姿を取り戻します。
ここでは、代表的な葉の症状と、その背景にある原因を詳しく解説します。
| 葉の症状 | 考えられる主な原因とメカニズム |
|---|---|
| 葉が黄色くなる | 日照不足:光合成に必要な葉緑素が十分に作れず、緑色が薄くなります。 根詰まり・栄養不足:根から十分な栄養(特に窒素)を吸収できず、古い葉から黄色く変色します。 根腐れ:根が傷み、水分や栄養を葉に送れなくなります。 |
| 葉が茶色くパリパリになる | 葉焼け:強い直射日光が葉の組織を破壊し、枯れた状態になります。 水切れ:水分が不足し、葉先から乾燥が進みます。 寒さ:低温によって葉の細胞が凍結・破壊されてしまいます。 |
| 葉がぐったりと下を向く | 水不足(水切れ):植物は葉からの水分蒸散を防ぐために、自ら葉を閉じてぐったりさせます。水やりをすれば回復することが多いです。 |
| 新しい葉が小さい | 栄養不足・根詰まり:株全体に十分なエネルギーや栄養がないため、大きな葉を展開する余力がありません。長年育てている場合に特に見られます。 |
| 葉に白い斑点やクモの巣 | ハダニなどの病害虫:ハダニは葉の裏に寄生し、養分を吸います。その跡が白い斑点として残り、大量発生するとクモの巣のような糸を張ります。(参考:あいち病害虫情報) |
このように、一つの症状に対しても複数の原因が考えられます。例えば「葉が黄色い」場合、置き場所や水やり、最後の植え替えがいつだったかを総合的に振り返ることが、的確な原因究明に繋がります。
編み込みパキラは寿命が短い?
複数の若いパキラの幹を人工的に編み込んで仕立てた「編み込みパキラ」は、そのユニークでおしゃれな姿からインテリアグリーンとして絶大な人気を誇ります。しかし、その美しさの裏で、自然な一本立ちのパキラに比べて寿命が短くなりやすいという側面も持っています。
その最大の理由は、成長に伴う幹の物理的な締め付けです。購入時は細く柔らかい幹も、年月と共に太く硬く成長します。すると、編み込まれた部分がお互いを強く圧迫し合い、水分や栄養素が通る維管束を傷つけたり、塞いでしまったりするのです。
これにより、締め付けが特に強い株や弱い株が栄養不足に陥り、最終的に枯れてしまうことがあります。
さらに、複数の株が密集しているため、どうしても風通しが悪くなりがちです。湿気がこもりやすい環境は、カビや病気の原因となるほか、カイガラムシなどの害虫の温床にもなりやすいというデメリットがあります。
編み込みパキラを長く楽しむための注意点
編み込みパキラの特性を理解した上で、できるだけ長く楽しむためには、購入時の株選びと日々の管理が重要です。編み込みが緩やかで、各々の幹に十分なスペースがあるものを選びましょう。
また、定期的に葉を間引いて風通しを確保し、病害虫がいないかこまめにチェックすることが大切です。もし一本の幹が枯れてしまった場合は、無理に引き抜こうとせず、腐敗が進まないようにハサミで根元から切り取るのが賢明です。
デザイン性を取るか、植物本来の健康と長寿を取るか、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選ぶことが推奨されます。
ハイドロカルチャーでの育て方
ハイドロカルチャーは、土を使わずにハイドロボールやゼオライトといった無機質の人工培地で植物を育てる水耕栽培の一種です。
土を使わないため、清潔でコバエなどの虫が発生しにくい、匂いがない、容器の底に溜まった水の量で水やりのタイミングが分かりやすいといった多くのメリットがあり、特に室内での園芸初心者から人気を集めています。
パキラもこのハイドロカルチャーで育てることが可能ですが、この方法が土栽培に比べて寿命を延ばすわけではない点は理解しておく必要があります。むしろ、成長スピードは土栽培よりも緩やかになり、管理には特有のコツが求められます。
ハイドロカルチャーはメリットが多い一方で、土栽培とは違う注意点があります。一番の違いは「根の環境」ですね。
最大のデメリットは、根が常に水に触れやすい環境にあるため、根腐れのリスクが土栽培よりも高いことです。また、土とは異なり培地自体には栄養分がほとんど含まれていないため、生育期には定期的に専用の液体肥料を与えて栄養を補給し続けなければなりません。
ハイドロカルチャー管理を成功させるコツ
- 根腐れ防止剤を使う:容器の底にミリオンAなどの根腐れ防止剤を敷くことで、水を浄化し、根腐れのリスクを大幅に軽減できます。
- 水やりはメリハリをつけて:容器に溜めた水が完全になくなってから、2~3日ほど根を乾かす期間を設けるのが重要です。これにより、根が呼吸する時間を確保できます。水は容器の高さの1/5程度までが目安です。
- 定期的な容器の洗浄:長期間同じ容器で育てていると、藻が発生したり水が澱んだりすることがあります。数ヶ月に一度は植物を取り出し、容器をきれいに洗浄すると良いでしょう。
これらのポイントを押さえれば、ハイドロカルチャーでもパキラを健康に育てることは十分に可能です。
パキラの寿命を延ばす育て方のコツ
参考
- パキラは枯れても復活しますか?
- 植え替えで延命は可能?
- 元気を取り戻す剪定のコツ
- 挿し木で新しい命を育てる
- 寿命を縮めるNG行動とは?
- 正しい手入れでパキラの寿命を延ばそう
パキラは枯れても復活しますか?

観葉スタイル・イメージ
葉がすべて落ちてしまい、枝も枯れて、まるで生命の灯が消えたかのような痛々しい姿に、「もうダメかもしれない…」と肩を落としてしまうのは無理もありません。
しかし、ここで諦めてしまうのは非常にもったいないことです。結論から力強くお伝えします。パキラはその驚異的な生命力により、瀕死の状態からでも復活する可能性が非常に高い植物です。
なぜなら、パキラの幹や枝の節目には「休眠芽(きゅうみんが)」と呼ばれる、いわば“生命のバックアップシステム”が備わっているからです。
これは、普段は眠っている予備の芽で、病気や乾燥、剪定などで上部の枝葉が失われるという非常事態に陥ると、植物が生き延びるために目を覚まし、新たな芽吹きを始めます。パキラはこの力が特に強く、幹や根の一部でも生きていさえすれば、そこから力強く再生することができるのです。
まるでトカゲの尻尾みたいですよね。パキラは自ら枯れた部分を切り捨て、生きている部分から再生する力を持っているんです!
ただし、復活させるためには、まずそのパキラにまだ生命が残っているかを正確に見極める必要があります。以下の「3つのチェックポイント」で、あなたのパキラの状態を確認してみましょう。
生と死を見極める!復活の3大チェックポイント
- 【触診】幹を触って硬さを確認する:
最も簡単で重要な確認方法です。幹、特に土に近い根元の部分を指で優しく、しかし少し力を込めて押してみてください。ブヨブヨと柔らかく、指が沈むような感触であれば、残念ながらその部分は内部まで腐敗が進んでいます。しかし、一部分でもしっかりと硬さが残っていれば、その組織はまだ生きており、復活の望みは十分にあります。 - 【視診】幹の表皮を少し削って断面の色を見る:
より確実に生死を判断する方法です。清潔なカッターナイフやハサミの刃先で、幹の茶色い表皮をミリ単位でごく浅く削ってみてください。削った下の層が鮮やかな緑色やクリーム色であれば、その部分は生きています。もし、茶色や黒色でカスカスに乾いている場合は、その部分は完全に枯死しています。複数の箇所で試してみて、緑色の部分を探しましょう。 - 【根の確認】鉢から抜いて根の状態を見る:
これは最終確認です。思い切って株を鉢からそっと引き抜き、根の状態を直接確認します。土を優しくほぐしたとき、白くてハリのある健康な根が一本でも残っていれば、復活の可能性は非常に高いです。逆に、すべての根が黒ずんでドロドロに溶けていたり、スカスカになっていたりする場合は、残念ながら復活は困難です。
これらのチェックで一つでも「生」のサインが見つかったなら、あなたのパキラはまだ生きています。ここから適切な手当てを施すことで、再び緑の葉を茂らせる姿を取り戻すことができます。
具体的な復活へのステップは、次の「植え替え」や「剪定」のセクションで詳しく解説していきます。パキラの持つ底力を信じて、再生への一歩を踏み出しましょう。
植え替えで延命は可能?

観葉スタイル・イメージ
はい、間違いなく定期的な植え替えは、パキラの健康を維持し、寿命を最大限に延ばすための最も重要で効果的な作業の一つです。
成長が早いパキラは、購入時の鉢のまま1〜2年も育てると、鉢の中が根でぎゅうぎゅう詰めの「根詰まり」状態になってしまいます。この状態をリセットし、新たな成長を促すのが植え替えの目的です。
植え替えを行うことで、パキラにとって数多くのメリットがもたらされます。
植え替えがもたらす4つの重要なメリット
- 成長スペースの確保:一回り大きな鉢に植え替えることで、根が自由に伸びるための物理的な空間を確保し、株全体のさらなる成長を促します。
- 土壌環境のリフレッシュ:長期間使われた土は栄養分が枯渇し、水はけも悪くなっています。新しい観葉植物用の土に入れ替えることで、必要な栄養を補給し、通気性と排水性を改善します。
- 根の健康診断とメンテナンス:植え替えの際に株を鉢から抜くことで、普段は見えない根の状態を確認できます。黒ずんで腐った根や、古く硬くなった根を整理することで、新しい健康な根の発生を促します。
- 根腐れの予防と治療:もし根腐れが始まっていた場合、腐った部分を完全に取り除き、新しい清潔な土に植えることで、被害の拡大を防ぎ、株の再生を図ることができます。
植え替えに最適な時期は、パキラの生命活動が最も活発になる成長期の5月〜9月頃です。この時期であれば、植え替え時に多少根を傷つけてしまっても回復が早く、株への負担を最小限に抑えられます。
逆に、気温が低く成長が停滞する冬場の植え替えは、回復に時間がかかり、最悪の場合そのまま枯れてしまうリスクがあるため、緊急時以外は避けましょう。
鉢の底穴から根がはみ出している、土の表面が固くなっている、水やりをしても水がなかなか染み込んでいかない、といった症状は、植え替えが必要な明確なサインです。
元気を取り戻す剪定のコツ
植え替えが土の中の環境を整える「内科的治療」だとすれば、「剪定」は植物の地上部を整える「外科的治療」と言えます。
枝が伸びすぎて樹形が乱れたり、葉が密集して内部の風通しが悪くなったりした時に行う剪定は、見た目を美しくするだけでなく、パキラの健康を維持し、寿命を延ばすために不可欠な作業です。
剪定の主な目的と効果は以下の通りです。
- 栄養の効率的な分配:不要な枝葉を取り除くことで、植物が作るエネルギーを、成長させたい主要な枝や新しい芽に集中させることができます。
- 病害虫の予防:込み合った枝葉を間引くことで、株内部の風通しと日当たりが劇的に改善されます。これにより、湿気を好む病原菌やカイガラムシなどの害虫が発生しにくい環境を作ります。
- 新陳代謝の促進:枝を切ることで、その切り口付近の休眠していた芽が刺激され、新しい枝葉の成長が活発になります。
剪定の時期も、植え替えと同様に成長期である5月〜8月が最適です。パキラは非常に萌芽力(ほうがりょく:新しい芽を出す力)が強いため、多少切りすぎても失敗することはほとんどありません。
伸びすぎた枝や、他の枝と交差している枝、枯れた枝などを、切れ味の良い清潔なハサミで付け根から切り取りましょう。
特に株が弱っている場合は、思い切って枝葉の量を減らす「強剪定」を行うことで、根の負担を軽減し、株全体のエネルギー消費を抑えることができます。これにより、残されたエネルギーが株の回復に集中され、復活を早める効果が期待できます。
剪定した元気な枝は宝物!
剪定で切り落とした枝の中でも、緑色でハリのある元気な枝は、次の項目で紹介する「挿し木」に最適な材料です。捨ててしまう前に、ぜひ新しい株を育てることに挑戦してみてください。
挿し木で新しい命を育てる
「挿し木」は、剪定で出た枝の一部を利用して、親株と全く同じ遺伝子を持つ新しい株(クローン)を育てる方法です。
この方法を使えば、万が一親株が寿命を迎えたり、病気で枯れてしまったりした場合でも、その命を次の世代へと繋いでいくことができます。パキラは非常に簡単に挿し木で増やすことができる植物の一つです。
基本的な挿し木の手順は以下の通りです。
- 挿し穂の準備:剪定した枝の中から、葉がついていて元気な部分を10〜15cm程度の長さに切り出します。これを「挿し穂(さしほ)」と呼びます。根の発生にエネルギーを集中させるため、先端の葉を2〜3枚だけ残し、他の葉は付け根から切り取ります。
- 水揚げ:挿し穂の切り口をカッターなどで斜めに鋭くカットし直します。その後、コップなどに入れた水に切り口を1〜2時間ほど浸け、十分に水を吸わせます(水揚げ)。
- 土に挿す:肥料分のない清潔な挿し木用の土や、赤玉土(小粒)を湿らせてポットに入れます。指や棒で穴を開け、そこに挿し穂の切り口を傷めないように優しく挿します。
- 発根までの管理:土が乾かないように注意しながら、直射日光の当たらない明るい日陰で管理します。ビニール袋をかぶせて湿度を保つのも効果的です。約1ヶ月ほどで根が出て、新しい芽が動き始めます。
土に挿す代わりに、そのまま水を入れた容器に挿しておく「水挿し」でも発根させることが可能です。生命力旺盛なパキラならではの手軽さと言えるでしょう。親株の保険として、また園芸の楽しみを広げるためにも、ぜひ挑戦してみてください。
寿命を縮めるNG行動とは?
愛情を持って育てているつもりでも、知らず知らずのうちにパキラの寿命を縮める行動をとっていることがあります。ここでは、特に初心者が陥りがちな、避けるべきNG行動とその理由を詳しく解説します。ご自身の普段のお手入れ方法を一度見直してみましょう。
| NG行動 | なぜダメなのか?(理由と正しい対処法) |
|---|---|
| ① 毎日水やりをする | これは根腐れに直結する最も危険な行為です。土の中が常に湿っていると根が呼吸できなくなり腐敗します。【正しい対処法】水やりは必ず土の表面が完全に乾いてから。指を土に少し入れてみて、中の湿り気を感じなくなったら、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与えます。「乾いたら、たっぷり」が鉄則です。 |
| ② 冬にも肥料を与える | パキラは冬になると成長をほぼ停止する休眠期に入ります。この時期に肥料を与えても、根はそれを吸収できません。吸収されない肥料分は土の中に溜まり、塩類濃度を高めてしまいます。これにより、浸透圧の関係で逆に根から水分が奪われる「肥料焼け」を起こし、根を傷める原因となります。【正しい対処法】肥料は成長期である春(5月頃)から秋(9月頃)までにとどめましょう。 |
| ③ エアコンの風が直接当たる場所に置く | エアコンの風は極度に乾燥しており、植物の葉から急激に水分を奪います。これにより、葉がチリチリになったり、落葉したりする原因となります。【正しい対処法】エアコンの風が直接当たらない、空気の流れが穏やかな場所に置いてください。 |
| ④ 寒い場所に置きっぱなしにする | 熱帯生まれのパキラは寒さが大の苦手です。一般的に、耐えられる最低温度は5℃とされています。これ以下の環境が続くと、葉が黒ずんで落ちたり、最悪の場合、株全体が凍結して枯死してしまいます。【正しい対処法】冬は必ず室内の暖かい場所で管理します。特に冷え込む夜間は、窓際は外気と同じくらい温度が下がるため、部屋の中央に移動させるなどの対策が必要です。 |
これらのNG行動を避けるだけで、パキラが直面するストレスの大部分を取り除くことができ、健康で長生きするための土台ができます。
正しい手入れでパキラの寿命を延ばそう
この記事では、パキラの本来の寿命と、その寿命を全うさせるための正しい育て方やトラブルの対処法について詳しく解説してきました。大切なのは、日々の観察を通してパキラが出す小さなサインに気づき、早めに対処してあげることです。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
パキラは非常に生命力が強く、愛情を持って正しい手入れをすれば、きっとあなたのそばで長く元気に育ち、日々の暮らしに彩りを与えてくれるはずです。この記事が、あなたと大切なパキラとの豊かなグリーンライフの一助となれば心から幸いです。
チェックリスト
- パキラの本来の寿命は非常に長く数十年以上生きる
- 枯れる主な原因は「水のやりすぎ」「日照不足」「根詰まり」の三つ
- 葉に現れる異変は寿命のサインではなく植物からのSOS
- 編み込みパキラは成長すると幹を締め付け合い枯れるリスクがある
- ハイドロカルチャーは清潔だが根腐れしやすく栄養管理が必要
- 幹に硬い部分が残っていれば枯れかけても復活できる可能性が高い
- 1〜2年に一度の植え替えは健康と長寿のために必須の作業
- 根詰まりは栄養吸収を阻害しパキラを弱らせる
- 剪定は風通しを良くして病害虫を防ぎ新陳代謝を促す
- 剪定で切った元気な枝は挿し木で新しい株に再生できる
- 土が乾く前の水やりは根腐れに直結する最大のNG行動
- 水やりは「乾いたら、たっぷり」のメリハリが重要
- 成長が止まる冬に肥料を与えると根を傷める原因になる
- エアコンの風や強い直射日光は葉を傷めるので避けるべき
- 寒さに弱いため冬は5℃以上の暖かい室内で管理する
