
観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの寄せ植えは、そのユニークな樹形と生命力の強さから、室内でも楽しめるグリーンインテリアとして非常に高い人気を誇ります。しかし、購入した後の管理方法や、植え替えに適した時期がいつなのか、迷うことも多いのではないでしょうか。
観葉植物に適した培養土の選び方から、元気に育てるための肥料の与え方、夏の強い直射日光を避ける置き場所まで、育てる上での基本は非常に重要です。
また、育てているうちに幹がスカスカになってしまった時の具体的な対処法や、室内管理で特に注意が必要な厄介な害虫の予防と対策も知っておきたいポイントです。
この記事では、ガジュマルの寄せ植えを長く、そしておしゃれに楽しむための剪定のコツ、さらには剪定した枝を活用した挿し木や、清潔に管理できる水耕栽培での増やし方も含めて、総合的に詳しく解説します。
ポイント
- 寄せ植えに適した時期と土の選び方
- 室内での置き場所や光の当て方のコツ
- 肥料や剪定など日々のお手入れ方法
- 幹がスカスカになった時の対処法や害虫対策
コンテンツ
ガジュマルの寄せ植えをおしゃれに作る基本
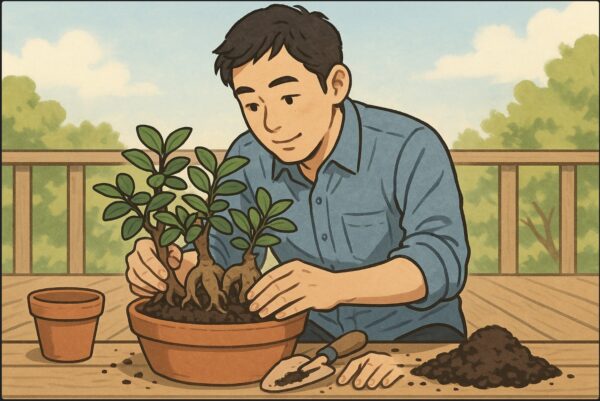
観葉スタイル・イメージ
参考
- 寄せ植えに適した時期はいつ?
- 観葉植物用の培養土を選ぶコツ
- 室内での管理と置き場所
- 直射日光を避けた光の当て方
寄せ植えに適した時期はいつ?

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの寄せ植えを成功させるためには、作業を行う「時期」が最も重要なポイントとなります。植物にとって植え替えは、人間で言えば手術を伴う引っ越しのようなもので、非常に大きなストレスがかかります。そのため、ガジュマルが最も元気で、回復力が高い時期を選ぶ必要があります。
結論から言うと、寄せ植えに最も適した時期は、成長期の前半にあたる5月後半から7月頃です。この期間は、気温が安定して20℃以上を保つ日が多くなり、ガジュマルの新陳代謝が最も活発になるタイミングです。
特に、日本の梅雨時期にあたる6月頃は、空気中の湿度が高く、ガジュマルが好む高温多湿の環境と一致します。この湿度が、根の乾燥を防ぎ、発根を促すため、作業後の回復を強力に後押ししてくれます。
寄せ植えは、単体の植え替えと異なり、複数の苗を鉢から取り出し、それぞれの根鉢(根と土が固まった部分)を丁寧にほぐし、バランスを見ながら配置するという複雑な作業が伴います。
この過程で、どうしても根が傷ついたり、空気にさらされたりする時間が長くなりますが、成長期であれば、万が一ダメージを受けても新しい根を迅速に展開させ、新しい土にもすぐに順応してくれます。
寄せ植えのベストシーズン
- 最適期:5月後半〜7月(成長期・高温多湿)
- 理由:新陳代謝が活発で、ダメージからの回復が圧倒的に早い。梅雨の湿度が発根を助ける。
- 次善期:9月初旬(成長期)
- 注意:9月後半になると気温が下がり始め、冬までに回復する期間が短くなるため、避けた方が無難です。
作業を絶対に避けるべき時期
一方で、ガジュマルの体力が落ちている、または活動を停止している時期の作業は、枯らしてしまうリスクが非常に高いため絶対に避けてください。
注意:これらの時期の作業は厳禁です
1.休眠期(10月〜3月頃)
ガジュマルは寒さに弱く、気温が下がると成長を止め「休眠期」に入ります。この時期は、新陳代謝がほぼ停止しており、ダメージを回復する力がありません。休眠期に根を傷つけると、傷口がふさがらず、そこから腐敗菌が侵入したり、水分を吸えなくなったりして、春を待たずに枯れてしまう直接的な原因となります。
2.真夏の猛暑日(35℃を超える日)
気温が高すぎる真夏も避けるべきです。人間が夏バテするように、植物も高温下では体力を消耗しています。葉からの水分の蒸散が激しく、根からの水分吸収が追いつかない状態です。このタイミングで根を傷つけると、深刻な水分不足(水切れ)を起こし、一気にしおれて枯れてしまうリスクがあります。
寄せ植えは、複数の植物の根を扱う繊細な作業です。必ず、植物の体力(回復力)が万全な5月後半から7月の間に行うようにしましょう。
観葉植物用の培養土を選ぶコツ

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの寄せ植えを成功させるためには、土選びが非常に重要です。
ガジュマルは原産地では高温多湿の環境に自生していますが、鉢植えで育てる場合、根が常に湿った状態にあると「根腐れ」を起こしやすくなります。根腐れは、根が呼吸できなくなり腐敗する状態で、観葉植物を枯らす最大の原因の一つです。
そのため、鉢植えの土には「水はけの良さ」と「適度な保水力」という、相反する二つの性質を兼ね備えた土を選ぶ必要があります。
観葉植物の栽培が初めての方や、手軽に済ませたい場合は、市販されている「観葉植物用の培養土」を使用するのが最も簡単で失敗が少ない方法です。
これらは、赤玉土や鹿沼土、ピートモスなどが最適なバランスで配合されており、元肥(もとごえ)として初期育成に必要な肥料が含まれている製品も多くあります。
自分で土を配合する場合
もし土の配合にこだわりたい場合は、「赤玉土(小粒)6:腐葉土3:パーライト1」といった割合で混ぜ合わせることで、ガジュマルに適した水はけの良い土を作ることもできます。それぞれの用土の役割は以下の通りです。
| 用土 | 主な役割 |
|---|---|
| 赤玉土 | 水はけ、保水性、保肥性の基本となる土。 |
| 腐葉土 | 通気性を高め、土に栄養分(有機物)を供給する。 |
| パーライト | 黒曜石を高温処理したもので、土を軽くし、水はけを格段に良くする。 |
安価すぎる培養土の中には、水はけが悪く、水やりの後に土が固く締まってしまうものもあります。根腐れを防ぎ、健康に育てるためにも、園芸用品メーカーが観葉植物専用に配合した土を選ぶことをおすすめします。(参考:株式会社ハイポネックスジャパン「観葉植物の土」)
室内での管理と置き場所

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルを室内で健康に育てるためには、「どこに置くか」という環境設定が非常に重要です。その後の健康状態を左右する「光」「温度」「風」の3つの側面から、室内管理のポイントを詳しく解説します。
①光:耐陰性の誤解と「光不足」のリスク
ガジュマルの管理において、光は非常に重要です。多くの人が「ガジュマルは耐陰性がある」と聞きますが、この言葉の意味を正しく理解することがスタートラインです。
耐陰性があるとは、「暗い場所でもすぐに枯れはしない」という耐久力があるという意味であり、「暗い場所を好む」わけでは決してありません。
ガジュマルは本来、日光を好む植物です。光が不足した環境に長期間置かれると、植物は生き延びるために体力を消耗し、様々な不調を引き起こします。
- 徒長(とちょう):植物が光を求めて、枝や茎が間延びしてひょろひょろと弱々しく育つ現象です。幹は太らず、樹形が大きく崩れる原因となります。
- 葉が落ちる(落葉):光合成ができないと、植物はエネルギーを節約するために自ら葉を落とし始めます。これは体力が弱っている明確なサインです。
もしインテリアの都合上、どうしても暗い場所に置きたい場合は、「ローテーション」を導入してください。
1週間のうち数日は明るい場所で光合成をさせ、残りの数日を暗い場所に置く、というサイクルを繰り返すことで、健康状態を維持しやすくなります。または、植物育成ライトを補助的に使用するのも有効な手段です。
②温度:熱帯生まれの植物であることを意識する
ガジュマルは熱帯・亜熱帯原産の植物であり、暖かい気候を好みます。生育に適した温度は20℃〜30℃程度とされています。
その反面、寒さには非常に弱いです。元気に冬越しさせるためには、最低でも5℃以上の室温を保つことが推奨されています。(できれば8℃〜10℃以上あると植物にとってストレスがなく安心です)
冬の夜間は「窓際」から「部屋の中央」へ
特に冬の管理で注意が必要なのが、「夜間の窓際」です。日中は暖かくても、夜になると外の冷気が窓ガラスを通して伝わり、窓際は室内でも5℃近くまで急激に温度が下がることがあります。
この寒暖差と冷気が株に大きなストレスを与えるため、夜間は窓から少し離れた、部屋の中央など暖かい場所へ鉢を移動させてあげると、冬越しの失敗を格段に減らすことができます。
③風:エアコンの風と空気の循環
室内管理では「空気の流れ」も重要です。ガジュマルにとって良くない風と、良い風があります。
【厳禁】エアコンの風
室内の管理で絶対に避けたいのが、エアコンの風です。暖房や冷房の風が直接ガジュマルに当たると、葉が極端に乾燥してしまい、水分を急激に奪われます。これは植物にとって非常に大きなストレスであり、葉を落とす最大の原因となります。必ずエアコンの風が当たらない場所に置いてください。
【推奨】穏やかな空気の循環(風通し)
一方で、空気がまったく動かない「よどんだ場所」も良くありません。風通しが悪いと、鉢土の湿気が乾かず根腐れを助長したり、カイガラムシやハダニなどの害虫が発生しやすくなったりします。
サーキュレーターなどで部屋の空気を穏やかに循環させたり、時々窓を開けて換気したりすることは、ガジュマルの健康維持(病害虫予防)に非常に効果的です。
直射日光を避けた光の当て方
前述の通り、ガジュマルは光を好む植物ですが、ただ当てれば良いというわけではありません。特に室内管理では、光の「質」と「強さ」に注意が必要で、「強い直射日光」は厳禁です。
特に、5月から8月にかけての夏場の強い日差しに当ててしまうと、人間の肌が日焼けするのと同様に、葉が焼けて黄色や茶色に変色してしまう「葉焼け」を起こすことがあります。一度葉焼けしてしまった葉は、残念ながら元のきれいな緑色には戻りません。
室内で管理する場合は、レースカーテンを一枚挟むことで、強い日差しを柔らかい光に変えてあげるのが最も簡単な対策です。これが、ガジュマルにとっての「適切な明るさ」を確保する最適な方法となります。
「適切な明るさ」の目安として、日中に電気をつけなくても新聞や読書が快適にできる程度の「明るい日陰」と覚えておくと分かりやすいです。暗すぎる場所ももちろん良くありません。
もし春から秋にかけて屋外で管理する場合も、直射日光が当たる場所は避け、軒下や木陰、または園芸用の遮光ネットやすだれを使って、必ず強い日差しを和らげる工夫をしてください。
また、植物は光が差す方向に向かって成長する性質があります。同じ向きに置き続けると、光の当たる方ばかり枝葉が茂り、反対側は寂しい状態になるなど、樹形が偏ってしまいます。
時々で良いので鉢を回転させて、全体に均一に光が当たるようにしてあげると、バランスの取れた美しい形に育ちます。
ガジュマルの寄せ植えの管理と育て方
参考
- 元気に育てる肥料の与え方
- 剪定で樹形を整える方法
- 幹がスカスカになった時の対処法
- 発生しやすい害虫の種類と予防
- 挿し木でガジュマルを増やす
- 水耕栽培での育て方とは
元気に育てる肥料の与え方
ガジュマルの寄せ植えを元気に育てるためには、適切な時期に肥料を与えることが大切です。植物にとって肥料は「ごはん」と同じです。成長期には多くの栄養を必要としますが、休んでいる時には必要ありません。
肥料は、ガジュマルの成長期である春から秋(具体的には4月〜9月頃)に与えます。この時期は新芽を次々と出し、活発に成長するため、栄養を補給してあげることで、葉の色が濃くなり、丈夫な株に育ちます。
逆に、成長が止まる冬(12月〜3月頃)は、肥料を必要としません。この時期に肥料を与えると、根が養分を吸収しきれずに土の中の肥料濃度が高くなり、「肥料焼け」という根が傷む現象を起こします。これはかえって株を弱らせる原因になるため、冬場の施肥は絶対に避けましょう。
肥料の種類には、主に以下の2タイプがあり、ライフスタイルに合わせて選ぶのがおすすめです。
液体肥料(速効性)
水で薄めて使用するタイプで、水やりの代わりに与えます。1〜2週間に1回程度が目安です。すぐに効果が現れますが、その分、効果は長続きしません。植物の様子を見ながらこまめに管理したい方に向いています。
固形肥料(緩効性)
土の上に置くタイプの肥料です。「緩効性(かんこうせい)肥料」とも呼ばれ、水やりのたびに少しずつ栄養が溶け出し、1〜2ヶ月程度効果が持続します。手軽で管理が簡単なため、忙しい方や初心者の方にもおすすめです。
植え替え直後は肥料NG
寄せ植えを作った直後や、植え替えた直後は、根がダメージを受けています。その状態で肥料を与えると、弱った胃に無理やり食事をさせるようなもので、大きな負担となります。作業後2週間〜1ヶ月程度は肥料を控え、株が新しい環境に慣れ、回復するのを待ちましょう。
剪定で樹形を整える方法
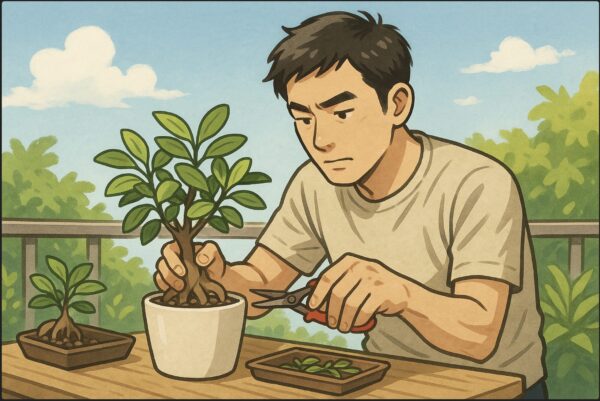
観葉スタイル・イメージ
ガジュマルは生命力が非常に強く、環境が合えば枝葉をよく茂らせます。
そのままにしておくと形が崩れるだけでなく、内側の葉に光が当たらなくなったり、風通しが悪くなったりします。この「風通しの悪さ」が、後述する病害虫の発生原因になるため、剪定は見た目だけでなく健康維持のためにも重要です。
剪定に最適な時期は、寄せ植えの作成と同じく成長期の5月〜7月頃です。この時期であれば、少々大胆にカットしても、切り口のすぐ下からすぐに新しい芽が吹いてきます。
剪定の基本手順
手順
- 理想の樹形をイメージする:まず、どのような形(丸くこんもり、縦長など)に仕上げたいかを決めます。
- 不要な枝(忌み枝)を切る:密集している枝、内側に向かって伸びる枝(内向枝)、間延びした枝(徒長枝)、枯れた枝などを、清潔なハサミで付け根から切り落とします。
- 全体の形を整える:理想の樹形からはみ出している枝を、葉の付け根(節)の少し上でカットして、全体のバランスを整えます。
剪定を行う際は、必ず園芸用の手袋を着用してください。ガジュマルはクワ科フィカス属の植物で、切り口から「ラテックス」というゴムの成分を含む白い樹液を出します。
この樹液は、肌に触れるとかぶれやアレルギー反応を引き起こす可能性があります。特に肌が敏感な方は注意が必要です。もし触れてしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。
幹がスカスカになった時の対処法

観葉スタイル・イメージ
大切に育てていたガジュマルの幹が、ある日触ってみると柔らかくスカスカ(またはシワシワ)になっていることがあります。これは、ガジュマルが発している重大なSOSサインです。
ガジュマルの太い幹は、本来水分や養分を蓄える貯蔵タンクの役割を果たしています。そこが柔らかくなるというのは、その貯水タンクが機能不全に陥っている証拠です。
この主な原因は、「根腐れ(水のやりすぎ)」または「極端な水不足」という、正反対のどちらかである可能性が非常に高いです。まずは、どちらが原因かを見極めることが重要です。
スカスカ・シワシワの原因を見極める
- 根腐れのサイン:鉢土が常に湿っている、土からカビ臭い・腐敗臭がする、コバエ(キノコバエ)が飛んでいる、葉が黄色くなり(乾燥はせず)ポロポロ落ちる。
- 水不足のサイン:鉢土がカラカラに乾き、鉢と土の間に隙間ができている、鉢が非常に軽い、葉が乾燥してパリパリになり、枯れ落ちる。
寄せ植えの場合は、他の植物の陰になって水やりが届いていなかったり、逆に他の植物に合わせて水を与えすぎていたりと、一鉢の中で両方の原因が混在することもあり得るため、慎重な観察が必要です。
原因1:根腐れ(水のやりすぎ)
最も多く、そして最も危険な原因が根腐れです。寄せ植えは特に、鉢の中が過密になりやすく、土の量に対して植物の根が多いため、土が乾きにくい状態(過湿)になりがちです。
また、ガジュマルは比較的乾燥に強く、他の多湿を好む植物と寄せ植えにすると、水やりの頻度がガジュマルにとって多すぎることがあります。
土が常に湿っていると根が呼吸できずに窒息し、やがて腐敗し始めます。腐った根は水分や養分を幹に送れなくなるため、幹は蓄えを失い、最終的には幹自体も下から腐敗が進行してスカスカになります。
緊急対処法:根腐れは待ったなし!
根腐れを発見した場合、季節を問わず、発見次第すぐに緊急手術(植え替え)が必要です。放置すれば、腐敗は必ず株全体に広がり、手遅れになります。
簡単な流れ
- 鉢から取り出す:寄せ植えの他の植物も含め、株を傷つけないよう慎重に鉢から全て取り出します。
- 土を完全に落とす:根鉢を優しくほぐし、腐った古い土をすべて落とします。必要であれば、ぬるま湯で洗い流しても構いません。
- 腐った根の剪定:清潔なハサミ(アルコール消毒したもの)で、黒ずんだ根、ブヨブヨした根、簡単にちぎれる根を、健康な白い部分(または硬い部分)が見えるまで徹底的に切り落とします。
- 切り口の乾燥:(非常に重要)切り口を殺菌し、乾燥させるため、風通しの良い明るい日陰で数時間〜半日ほど株を乾かします。
- 新しい土で植え直す:必ず新しい、水はけの良い観葉植物用の培養土を使って植え直します。この時、根腐れ防止剤(ゼオライトなど)を土に混ぜ込むのも有効です。
- 地上部の剪定:(復活の鍵)根が大幅に減ったため、そのままでは葉からの水分の蒸散に根の給水が追いつきません。根の量に合わせて、枝や葉も2分の1〜3分の1程度まで剪定し、株全体の水分バランスを強制的に整えます。
植え替え直後の水やりについて
根腐れの処置をした直後は、すぐに水を与えないでください。切り口がまだ乾ききっていないため、すぐに水を与えると再びそこから腐る可能性があります。
植え替え後、2〜3日経過してから、初めての水やりを軽く行い、その後は土の様子を見ながら徐々に通常の水やりに戻していきます。それまでは明るい日陰で養生させましょう。
原因2:極端な水不足
長期間の水やり忘れや、土の保水力があまりにも無い場合(古い土がカチカチになっているなど)、根が水分を吸えずに枯れてしまいます。
この状態が続くと、根は「ミイラ化」し、もはや機能しなくなります。根から水分が来ないため、ガジュマルは生きるために幹に蓄えた水分を消費し始め、結果として幹がシワシワになります。
対処法:段階的な水分供給
- 土の状態を確認:まず、土がカラカラに乾いていることを確認します。
- 通常の水やり:鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。この時、土が水を弾いてしまい、鉢の縁を水が素通りしていないか確認します。
- 「腰水(こしみず)」の実施:もし土が水を弾く(保水力を失っている)場合、バケツや深めのトレーに水を張り、鉢ごと数時間つけて確実に吸水させます。これにより、乾ききった土の芯までゆっくりと水分が浸透します。
- 養生:吸水させた後は、すぐに直射日光に当てるのは避け、まずは明るい日陰で様子を見ます。急激な環境変化はさらなるストレスになります。
水不足で枯れた根は元に戻りませんが、まだ生きている根が水分を吸い上げ始めれば、幹のシワシワが多少回復し、新しい葉が展開してくる可能性があります。
どちらの場合も、一度スカスカになった幹の組織が、完全に元のパンと張った状態に戻るのは難しいことが多いです。しかし、原因を特定して早急に対処すれば、健康な部分(特に上部)から新しい芽を吹かせて復活させることが可能です。諦めずに丁寧に対処してあげましょう。
発生しやすい害虫の種類と予防
室内で管理しているガジュマルは、風通しが悪いと害虫が発生しやすくなります。寄せ植えにしていると、株元が込み合いやすく湿気がこもりやすいため、特に注意が必要です。
主に注意すべき害虫は以下の通りです。早期発見・早期駆除が鉄則です。
| 害虫の種類 | 特徴と被害 | 対策 |
|---|---|---|
| ハダニ | 高温・乾燥する時期(特に夏)に発生しやすい。非常に小さく、葉の裏に寄生する。養分を吸うため葉の色が白っぽくカスリ状になる。 | 水に弱いため、こまめに霧吹きで葉水(はみず)を行うことが最も効果的な予防・駆除になります。大量発生した場合は専用の薬剤を使います。 |
| カイガラムシ | 白い綿のようなものや、茶色い殻のようなものが枝葉に付着する。排泄物が原因で床や葉がベタベタする(すす病の原因にもなる)。成虫は殻で覆われ薬剤が効きにくい。 | 数が少ないうちに、歯ブラシやティッシュ、濡れた布などでこすり落とすのが確実です。幼虫の時期であれば薬剤も有効です。 |
| アブラムシ | 主に新芽や若い葉に群生し、養分を吸う。ウイルスを媒介することもある。 | 数が少なければテープで取り除きます。大量発生時は牛乳をスプレーして窒息させるか、専用の薬剤で駆除します。 |
(参考:アース製薬株式会社「害虫駆除の情報」)
害虫対策の基本は「予防」です!
毎日のお世話のついでに、定期的な葉水で葉の表裏の乾燥を防ぎ、剪定で株内部の風通しを良く保つこと。この2つを心がけるだけで、害虫の発生をかなり抑えることができますよ。
挿し木でガジュマルを増やす
ガジュマルは、剪定で切り落とした枝を利用して「挿し木」で簡単に増やすことができます。生命力が強いため成功率も高く、寄せ植えのボリュームアップや、別の鉢を作る際に挑戦してみましょう。
挿し木の適期も、剪定と同じく成長期の5月〜7月頃です。この時期は気温・湿度ともに発根(根が出ること)に適しています。
挿し木の手順(土挿し)
手順
- 剪定した枝の中から、新芽がついている元気の良い枝を10cmほどの長さにカットします。
- 切り口をカッターなどで斜めに切り直し、表面積を広げます。
- コップなどの水に数時間つけ、切り口から出る白い樹液をしっかりと洗い流します。(この樹液が残っていると発根しにくくなります)
- 水分の蒸散を防ぐため、先端の葉を2枚ほど残して、下の葉はすべて取り除きます。残す葉が大きい場合は、さらに半分の大きさにカットします。
- 清潔な挿し木用の土(赤玉土小粒やバーミキュライト、または市販の挿し木用土)に、枝の1/3ほどを挿します。
- 土が乾かないようにこまめに水やりをしながら、直射日光の当たらない明るい日陰に置いておくと、約2〜3週間ほどで発根し、新芽が動き出します。
水挿し(水挿し)でも発根します
土に挿す代わりに、手順3の樹液を洗い流した後、そのままコップの水に挿しておくだけでも発根します(これを「水挿し」と呼びます)。水は毎日交換して清潔に保ちましょう。根が数センチ伸びたのを確認してから、土に植え替えることも可能です。
水耕栽培での育て方とは
ガジュマルは、土を使わない「水耕栽培(ハイドロカルチャー)」でも育てることが可能です。ハイドロカルチャーとは、ハイドロボールやセラミスといった人工の資材を使って植物を育てる方法です。
土を使わないため、カビや害虫が発生しにくく清潔であること、また透明な容器を使えば水の残量が一目でわかるため、インテリア性が高いというメリットがあります。
挿し木(水挿し)で発根させた苗を、そのまま水耕栽培に移行するのが最も簡単な方法です。
もし土で育っている苗を水耕栽培に切り替える場合は、以下の手順で行います。
手順
- 寄せ植えからガジュマルを取り出し、根についている土を水で優しく、きれいに洗い流します。この時、根を傷つけないよう細心の注意を払います。
- 腐った根や細すぎる根があればカットします。
- 穴の開いていない容器に、根腐れ防止剤(ゼオライトなど)を底に必ず敷きます。
- ハイドロボール(人工の資材)で苗を安定させながら固定します。
- 容器の1/5から2/5程度の高さまで水を入れます。根が常に水に浸かりすぎると呼吸ができなくなるため、水の入れすぎに注意します。
水耕栽培では、土に含まれるような栄養分が水にはないため、週に1回程度、水耕栽培専用の液体肥料を水に混ぜて与える必要があります。
水耕栽培の管理は「水の清潔さ」が命
水耕栽培は、土の自浄作用がないため、水が腐りやすいというデメリットがあります。管理を怠ると雑菌が繁殖し、すぐに根腐れを起こします。夏場は毎日、冬場でも2〜3日に1回は水を全て交換し、容器内部も洗って常に清潔に保ってください。
失敗しないガジュマルの寄せ植えの総まとめ
この記事で解説した、ガジュマルの寄せ植えを元気に、そして美しく楽しむための重要なポイントを最後にまとめます。
チェックリスト
- 寄せ植えの作業は成長期の5月後半から7月に行う
- 冬や真夏の作業は株が弱るため避ける
- 土は市販の観葉植物用の培養土が手軽で確実
- 水はけの良い土を選ぶことが根腐れ防止の最大の鍵
- 室内ではレースカーテン越しの明るい場所に置く
- 夏の強い直射日光は葉焼けの原因になるため避ける
- 冬は寒さを避け、窓から離れた暖かい場所に移動させる
- エアコンの風が直接当たる場所は厳禁
- 肥料は成長期の春から秋(4月〜9月)に与える
- 冬は肥料を与えない(休眠期)
- 植え替え直後2週間から1ヶ月は肥料を控える
- 剪定も成長期の5月〜7月が最適
- 剪定時は白い樹液に触れないよう手袋を着用する
- 幹がスカスカになる原因は主に根腐れか極端な水不足
- 根腐れの場合は腐った根を取り除き新しい土で植え替える
- 害虫予防には毎日の葉水と剪定による風通しの確保が有効
- ハダニには葉水が効果的
- カイガラムシは歯ブラシなどでこすり落とす
- 剪定した枝は挿し木で増やすことができる
- 水耕栽培は清潔だが毎日の水換えと専用肥料が必要
