
観葉スタイル・イメージ
大切に育てているガジュマルが徒長(とちょう)して形が崩れてしまった時、思い切ったガジュマルの丸坊主を検討する方は少なくないでしょう。
しかし、剪定の時期やタイミングを安易に決めると、失敗して芽が出ないという最悪の事態や、致命的な根腐れを起こしてしまうリスクが潜んでいます。
特に室内で管理している場合、植え替えとの兼ね合いや、回復を願って与えた肥料が逆効果になることもあります。この記事では、ガジュマルの丸坊主で失敗しないための正しい知識と、剪定後に美しい樹形を取り戻すための具体的な管理方法を、手順を追って徹底的に解説します。
ポイント
- 丸坊主にする目的と最適な時期がわかる
- 失敗しない剪定の手順と管理方法を学べる
- 丸坊主後に芽が出ないときの原因と対処法がわかる
- 剪定後の水やりや肥料の正しいタイミングを理解できる
コンテンツ
ガジュマルを丸坊主にする目的と正しい剪定方法

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの丸坊主は、見た目のインパクトが強い剪定方法ですが、行う目的は非常に明確です。ここでは、その目的と、失敗しないための正しい手順、そして最も重要な「時期」について詳しく解説します。
参考
- 樹形をリセットする目的とは
- 丸坊主の実施に最適な時期
- 正しい剪定のやり方と手順
- 植え替えは同時に行うべきか
- 室内での作業と注意点
樹形をリセットする目的とは
ガジュマルを丸坊主にする一番の目的は、その名の通り「樹形のリセット」です。
ガジュマルは本来、非常に生命力が強い植物です。しかし、室内など特定の方向からしか光が当たらない環境が続くと、植物の本能として光を求めて枝が一方にだけ間延びして伸びる「徒長(とちょう)」という現象が起きます。これにより、全体のバランスが大きく崩れてしまうのです。
このように形が崩れてしまったガジュマルを、一度幹だけの状態に戻し、新しい芽を株全体から均等に吹かせて美しい樹形に仕立て直すこと。これが丸坊主の最大の目的であり、最大のメリットと言えます。
丸坊主の主な目的とメリット
- 樹形のリセット:徒長してバランスが悪くなった形を根本から整え直します。
- 健康状態の改善:枝葉が茂りすぎて風通しが悪くなると、湿気がこもり、ハダニやカイガラムシといった病害虫の温床になります。丸坊主で風通しを一気に改善し、病害虫のリスクを軽減します。
- 株の活性化:長年育てて元気がなくなってきた株や、成長が鈍化した株に対し、強い剪定という刺激を与えることで休眠している芽を目覚めさせ、新しい芽の成長を促す効果が期待できます。
もちろん、全ての葉を失うため、新芽が芽吹くまでは一時的に見た目が寂しくなってしまいます。しかし、ガジュマルの強い生命力を信じ、適切な時期と管理を行えば、以前よりも力強く、バランスの取れた姿で復活してくれる可能性を秘めています。
丸坊主の実施に最適な時期

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの丸坊主を成功させるために、他のどの要素よりも重要なのが「実施する時期」です。これを間違えると、どれだけ丁寧に作業しても失敗する可能性が高まります。
結論から言うと、最適な時期は「5月下旬から7月上旬」の成長期です。この時期は、ガジュマルの原産地である沖縄や東南アジアの気候に近付き、気温が安定して20℃以上を保つため、ガジュマルの生命力が一年で最も高まるタイミングとなります。
なぜなら、この成長期であれば、剪定という大きな手術によるダメージからの回復が非常に早く、新しい芽を吹く力が強いため、失敗のリスクが最小限になるからです。
ガジュマルは熱帯・亜熱帯地域が原産で、那覇市の気候(気象庁)のように年間を通して温暖な環境を好みます。このため、日本の気候では、最も暖かく成長が活発な初夏が最適なのです。
人間でいうところの「体力(免疫力)が万全な時に手術を受ける」のと同じですね。ガジュマルが最も元気で、「回復するぞ!」というエネルギーに満ち溢れている時期を選んであげることが、成功への一番の近道です。
| 時期 | 気温目安 | 状態 | リスク |
|---|---|---|---|
| 最適(5月〜7月) | 20℃〜30℃ | 成長期(活発) | 低い(回復が非常に早く、新芽が出やすい) |
| 注意(8月〜9月) | 25℃以上 | 成長期だが猛暑 | 中(猛暑すぎると株が夏バテし、回復が遅れる場合がある。台風シーズンでもあるため管理に注意) |
| 厳禁(10月〜4月) | 15℃以下 | 休眠期(または緩慢) | 非常に高い(成長が止まり、ダメージを回復できずにそのまま枯れる危険性が極めて高い) |
特に10月以降、気温が15℃を下回る時期の丸坊主は絶対に避けてください。ガジュマルが冬越しのための「休眠期」に入るため、成長が完全に止まります。この時期に大きなダメージを与えると、株が体力を回復できず、春を迎える前にそのまま枯れてしまう可能性が非常に高くなります。
正しい剪定のやり方と手順
最適な時期を選んだら、次は正しい手順で剪定作業を行います。作業自体は非常にシンプルですが、ガジュマルへの負担を最小限に抑え、感染症などを防ぐためにいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
1.必要な道具を準備する
まず、作業に必要な道具を揃えましょう。特に、ガジュマルの体に直接触れるハサミの清潔さは最重要項目です。
- 清潔な剪定バサミ:使用前に必ずアルコールスプレーで消毒するか、ライターの火で刃先を数秒炙るなどして殺菌してください。汚れたハサミを使うと、切り口から雑菌が侵入し、枯れる原因になります。
- 手袋(必須):後述しますが、ガジュマルの樹液から手を守るために必ず着用します。ゴム手袋が最適です。
- 新聞紙やシート:床が樹液や土で汚れるのを防ぐために、作業場所に広めに敷いておきます。
- 癒合剤(ゆごうざい):切り口を保護するための薬剤です。ホームセンターや園芸店で入手できます。特に太い枝を切る場合は、できるだけ用意しておくと安心です。
2.枝をカットする
準備ができたら、いよいよ枝をカットしていきます。丸坊主の場合は、残したい幹のイメージを決め、そこから伸びている枝を根元からすべて切り落とします。
中途半端に枝を残してしまうと、そこからアンバランスに新芽が出ることがあるため、思い切ってすべてカットする方が、幹全体から新しい芽がバランス良く出てきやすくなります。切る位置に迷う必要はあまりありませんが、幹自体を傷つけないよう注意しましょう。
3.樹液の処理
ガジュマルはゴムの木の仲間(フィカス属)であり、枝を切ると白い樹液がたくさん滲み出てきます。この樹液は、放置すると固まってしまうため、ティッシュや乾いた布で優しく拭き取ってください。
この白い樹液は、床やカーペットに付くとゴム質が固まり、非常に取れにくいシミになります。すぐに拭き取りましょう。また、体質によっては皮膚に触れるとかぶれの原因となるため、必ず手袋を着用して作業してください。
4.癒合剤を塗る
樹液の処理が終わり、切り口が少し乾いたら、癒合剤を塗ります。これは人間でいう「絆創膏」や「消毒薬」のようなもので、切り口を物理的に保護し、乾燥や雑菌の侵入を防ぐ役割があります。(参照:KINCHO園芸「園芸の基本」)
特に太い枝を切った場合、切り口の面積が大きくなるため、癒合剤を塗っておくことで失敗のリスク(枯れ込みや病気の発生)を大きく減らすことができます。
植え替えは同時に行うべきか

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの樹形も気になるし、鉢も小さくなってきたから根詰まりも解消したい。そう考えたとき、「どうせなら一度に全部やってしまおう」と、丸坊主(強剪定)と植え替えを同時に行うことは、絶対に避けるべきです。
これは、ガジュマルの生命力を過信した、最も危険な行為の一つです。なぜなら、剪定(地上部の手術)と植え替え(地下部の手術)は、それぞれが植物の体力を著しく消耗させる、全く別の種類の大きなストレスだからです。
なぜ同時作業は「致命的」なのか?
植物の生命活動を「会社」に例えてみましょう。
- 葉(地上部)は、光合成によってエネルギー(糖)を生み出す「生産工場」です。
- 根(地下部)は、活動に必要な水分や養分を吸収する「補給ライン」です。
「丸坊主」とは、この「生産工場(葉)」をすべて閉鎖し、エネルギー生産を完全にストップさせる行為です。植物は回復のために、幹や根に蓄えられた「貯金(養分)」を切り崩して新芽を出そうとします。
「植え替え」とは、その「補給ライン(根)」を古い土から引き剥がし、一部を切断・損傷させ、新しい環境に無理やり適応させる行為です。
これらを同時に行うことは、「収入源(工場)をゼロにしたうえに、貯金を引き出すためのインフラ(補給ライン)まで破壊する」ようなものです。
エネルギーを生産できず、回復に必要な水分・養分も満足に吸収できない「八方塞がり」の状態に陥り、そのまま体力が尽きて枯れてしまうリスクが非常に高まります。
もし両方行う場合の推奨スケジュール
もし根詰まりなどを起こしており、どうしても両方の作業が必要だと判断した場合は、必ず以下の順序と十分な回復期間を守ってください。
簡単な流れ
- まず「植え替え」を先に行う(最適時期:5月~6月):先に根の環境を整えます。この時点では葉を残しておくことで、葉の蒸散活動により根が水を吸い上げる力が働き、新しい土への順応が促進されます。また、葉の張り具合で「根が水を吸えているか」を視覚的に判断できます。
- 回復期間(最低でも2~3週間以上):植え替え後、ガジュマルを直射日光の当たらない「明るい日陰」で管理します。この期間は肥料を絶対に与えず、土の表面が乾いたら水を与える程度にします。
- 回復のサインを確認する:既存の葉がしおれずハリを保ち、新しい小さな芽が動き出すなど、明確な「回復のサイン」が見えたら、根が新しい土に順応し、体力が戻ってきた証拠です。
- 回復後に「丸坊主」を行う:根が万全の状態になってから、次のステップである地上部の手術(丸坊主)を行います。
丸坊主を先に行うのはダメか?
順番を逆にして「丸坊主を先に行い、その後に植え替える」のは、さらにリスクが高まるため推奨されません。
なぜなら、丸坊主にして葉がなくなると、植物は水分の蒸散をほぼ停止します。その「水をほとんど吸わない」状態で植え替え(根をいじる)を行うと、植え替え後の水やり管理が極めて難しくなります。
新しい土に根を張らせるためには水分が必要ですが、吸う力が弱いため、少しの水でも過湿になり、非常に高い確率で根腐れを誘発してしまうからです。
ガジュマルの体力を最優先に考え、「根(土台)を万全にしてから、地上部(樹形)を整える」という順序を必ず守るようにしましょう。焦りは禁物です。
室内での作業と注意点

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの丸坊主を室内で行う場合、屋外での作業と比べていくつか注意すべき点があります。特に、前述した「白い樹液」の扱いは、ご自身やご家族の健康、そして住環境を守るために重要です。
樹液の飛散と床の汚染
剪定時には、思った以上に樹液が垂れたり、ハサミを入れた瞬間に細かく飛散したりすることがあります。作業前には、ガジュマルの下に新聞紙やビニールシートを、想定しているよりも広範囲に敷いておくことを強く推奨します。
樹液がフローリングやカーペットに付着すると、ゴム質が固まって非常に取れにくいシミになるため、「これくらいで大丈夫だろう」という油断はせず、養生は徹底しましょう。
樹液によるかぶれとアレルギー(YMYL関連)
ガジュマルを含むフィカス属の植物が出す白い樹液には、体質によってアレルギー反応や皮膚のかぶれ(接触皮膚炎)を引き起こす可能性があるとされる成分(ラテックスなどが含まれると言われています)が含まれています。
安全に関するご注意
- 作業時は必ずゴム手袋や園芸用手袋を着用し、樹液が直接皮膚に触れないよう十分注意してください。
- 万が一、樹液が皮膚に付着した場合は、慌てずにすぐに水と石鹸でよく洗い流してください。かゆみや赤み、腫れなどが続く場合は、速やかに皮膚科専門医に相談してください。(参照:公益社団法人日本皮膚科学会「植物による皮膚炎」)
- 小さなお子様やペットがいるご家庭では、作業中に近づいたり、切り落とした枝や樹液が付着したシートに触れたりしないよう、特に厳重な注意が必要です。
また、作業中は樹液特有の青臭い匂いが室内にこもることがあります。アレルギーの有無に関わらず、窓を開けるなどして十分に換気を行いながら作業することをおすすめします。
ガジュマルを丸坊主にした後の管理術

観葉スタイル・イメージ
無事に丸坊主の作業が終わっても、まだ安心はできません。本当の勝負は「剪定後、新芽が安定するまで」の管理にかかっています。特に水やりは、剪定前とは全く異なる考え方が必要です。
参考
- 失敗しないための水やり管理
- 芽が出ないときの原因と対処法
- 根腐れを防ぐ水やりのコツ
- 肥料はいつ与えるべきか
- 水やりの最適なタイミング
失敗しないための水やり管理
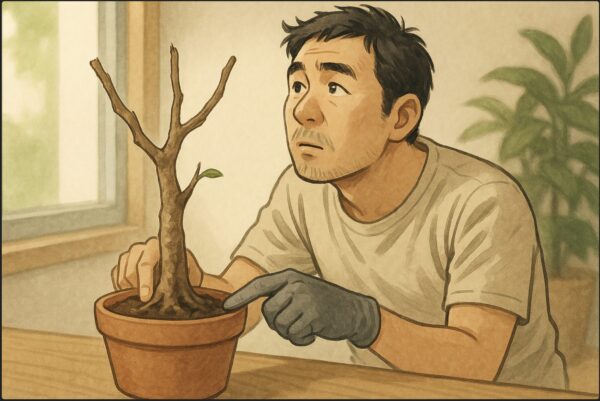
観葉スタイル・イメージ
ガジュマルを丸坊主にした後、最も多くの人が失敗し、そして枯らしてしまう最大の原因が「水やり」です。良かれと思って水を与えた結果、株を腐らせてしまうケースが後を絶ちません。
結論から言います。丸坊主後の水やり管理の方法はただ一つ、「水やりの頻度と量を剪定前よりも大幅に減らし、土を徹底的に乾燥気味に管理する」ことです。
なぜなら、植物は根から吸い上げた水分を、その9割以上を葉から蒸散(じょうさん)させていますが、丸坊主にして葉がすべてなくなると、水を排出する「ポンプ」が完全に停止した状態になります。水を吸い上げる力も、蒸散させる力もほぼゼロになるのです。
その状態で剪定前と同じように、あるいは「元気づけよう」と水を与え続けると、土の中は常に湿った状態になります。これが「根腐れ」の直接的な原因です。
根腐れ(ねぐされ)の本当のメカニズム
「根腐れ」とは、単に根が水でふやけることではありません。土の粒子間に水が充満し続けることで、根の呼吸に必要な「酸素」が土中から無くなる「窒息状態」を指します。
酸素不足で窒息し、弱った根は活動を停止します。そこへ、水分が多く酸素が少ない環境を好むカビ(フザリウム菌など)や雑菌が繁殖し、弱った根を文字通り腐らせていきます。一度腐り始めると、健康な部分にも伝染し、株全体が枯死してしまうのです。
丸坊主後の株は、この根腐れに対する抵抗力が著しく低下しています。そのため、意図的に「乾燥」状態を作り出し、根が窒息しない環境を保つことが最優先事項となります。
丸坊主後のNGな水やり管理
- スケジュールでの水やり:「3日に1回」「1週間に1回」などと決めて与えるのは最も危険です。葉がない状態では、土の乾く速度は天候や湿度に大きく左右されます。必ず「土の状態」を最優先してください。
- 幹への霧吹き(葉水):葉がないため、霧吹きは全く意味がありません。むしろ、剪定した切り口や幹肌を常に湿らせることで、カビの発生を助長し、切り口の回復を妨げるリスクがあります。
- 少量の「ちょこちょこ水やり」:「乾燥が怖いから少しだけ」と表面だけ湿らせる水やりもNGです。土の中層がずっと乾かず、鉢底付近の根が常に酸素不足の状態になってしまいます。
葉がないガジュマルは、いわば「水を飲む(蒸散する)口」を失っている状態です。そのため、水をほとんど必要としていません。「かわいそうだから」「早く元気になってほしいから」と水を与えるのは、残念ながら全くの逆効果です。
「放置気味」、「スパルタ管理」くらいが、この時期のガジュマルにとっては最も優しい管理方法なのだと覚えてください。
水やりの具体的な目安は、土の表面が乾いてからさらに数日~1週間以上待ち、土の中までしっかり乾いたのを確認してから与える程度で十分です。新芽がしっかりと出てくるまでは、とにかく「乾燥」を最優先にしましょう。
芽が出ないときの原因と対処法
「丸坊主にして2~3週間経つのに、まったく芽が出ない…」これは非常に不安になる状況です。しかし、芽が出ない場合、必ず何らかの原因が隠されています。
主な原因は「時期の間違い」「水のやりすぎ(根腐れ)」「日光・温度不足」の3つです。
適切な時期(5月~7月)に丸坊主にしたにも関わらず芽が出ない場合、その多くは根腐れか、回復に必要なエネルギー(光・温度)が不足していることが関係しています。
幹を軽く触ってみて、もしブヨブヨと柔らかくなっていたり、逆にカスカスに乾いていたりする場合は、残念ながら根腐れや枯れが進行している可能性が高いです。
| 主な原因 | 状況の例 | 対処法 |
|---|---|---|
| 1. 時期の間違い | 秋や冬(休眠期)に剪定してしまった。 | すぐに暖かい室内(最低15℃以上を維持)に取り込み、水やりをほぼ断水状態にして、春の回復を待つしかありません。ただし、そのまま枯れる可能性も高いです。 |
| 2. 水のやりすぎ | 葉がないのに剪定前と同じ頻度で水を与え、土が常に湿っている。幹がブヨブヨしている。 | 直ちに水やりを中止します。風通しの良い場所に置き、土を完全に乾燥させ、株の回復を待ちます。すでに根腐れが進行していると回復は困難です。 |
| 3. 日光・温度不足 | 剪定後、ずっと暗くて寒い玄関などに置いている。 | 剪定直後の1週間は日陰で休みますが、その後は明るい日陰やレースカーテン越しの光が当たる、風通しの良い暖かい場所(20℃以上推奨)に移動させます。 |
| 4. 株の衰弱 | 丸坊主にする前からすでに株が弱り切っていた。 | 上記の管理(乾燥気味、適切な温度と光)を徹底し、株の最後の生命力に期待するしかありません。 |
芽が出るまでの期間は個体差が大きく、早い個体で1~2週間、環境や株の状態によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。まずは上記の管理方法を見直し、幹がしっかりしている限りは、焦らずに待ってみましょう。
根腐れを防ぐ水やりのコツ
丸坊主後の管理において、根腐れは最も避けたい致命的なトラブルです。根腐れを防ぐ水やりの最大のコツは、「土が完全に乾いたことを確認してから、鉢底から流れ出るまでたっぷり与え、受け皿の水は必ず捨てる」というサイクルを徹底することです。
土の乾燥を確実に確認する方法
- 指で確認(確実):土の表面から指を第二関節くらいまで差し込み、土の中の湿り気を直接確認します。少しでも湿っていれば、水やりは絶対に不要です。
- 割り箸で確認:乾いた割り箸を土の奥まで刺し、数分後に抜いてみます。割り箸に湿った土が付着してこなければ乾燥しています。
- 鉢の重さで確認:水やり直後の重さと、乾燥時の重さを体感で覚えておきます。鉢を持ち上げて「明らかに軽い」と感じたら乾燥のサインです。
特に葉がない状態では、この「土が完全に乾いたことの確認」が非常に重要です。中途半端に湿っている状態での「心配だから」という「追い水」が、根腐れの最大の引き金となります。
そして、乾いたことを確認して水を与える際は、中途半端な量ではなく、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与えます。これは、土の中の古い空気を押し出し、根に必要な新しい酸素を供給する重要な役割も兼ねています。
肥料はいつ与えるべきか
「早く元気になってほしい」「新芽の成長を助けたい」という純粋な思いから、良かれと思って肥料を与えたくなる気持ちは非常によく分かります。
しかし、ガジュマルの丸坊主直後において、その行為は最も大きな間違いの一つであり、回復を助けるどころか、株に致命的なダメージを与えてしまう可能性があります。
丸坊主にした直後のガジュマルに、肥料は絶対に与えないでください。この時期のガジュマルは、地上部(葉)をすべて失い、剪定という大きな手術を受けたばかりの「重病人」と同じ状態です。回復のために全力を注いでおり、根も大きなダメージを負っています。
なぜ肥料が「負担」になるのか?
植物の根は、主に浸透圧の原理を利用して土中から水分を吸収しています。しかし、丸坊主直後の弱った根の周囲に高濃度の肥料成分(窒素、リン酸、カリなど)が来ると、根の内部よりも外(土壌)の濃度の方が高くなってしまいます。
その結果、根は水分を吸収するどころか、逆に根の内部の水分を土中に奪われてしまう「肥料焼け」という脱水症状を起こしてしまうのです。
これは、弱った胃腸に脂っこいステーキを無理やり詰め込むようなもので、栄養になるどころか、かえって根を傷め、腐らせ、回復を著しく遅らせる原因になります。
肥料を与える最適なタイミング
では、いつから肥料を与えて良いのでしょうか。その最適なタイミングは、「新しい芽が複数出そろい、それが葉としてしっかりと展開し、光合成を再開したことが確認できてから」です。
幹から緑色の芽がポツポツと見え始めた段階では、まだ早すぎます。
この段階では、ガジュマルはまだ幹や根に蓄えられた貯金(養分)だけで頑張っている状態です。肥料(新しい栄養)を必要とするのは、その新しい葉が開き、太陽の光を浴びて「光合成」というエネルギー生産活動を本格的に再開してからです。
肥料再開のステップバイステップ
簡単な流れ
- 【待機】剪定から約1ヶ月(目安):まずは水やり管理(乾燥気味)を徹底し、新芽が出るのをひたすら待ちます。この間、肥料は絶対に与えません。
- 【確認】新芽が「葉」になる:出てきた新芽が成長し、最低でも3〜4枚の葉がしっかりと開き、ツヤが出てきたことを確認します。
- 【開始】薄めた液体肥料から:観葉植物用の液体肥料を用意し、パッケージに記載されている規定の「2倍~3倍」に薄めたものを、水やりの代わりに少量与えます。これが「最初のごく薄いお粥」です。
- 【移行】徐々に通常の管理へ:最初の肥料やりから1~2週間様子を見て、新芽の成長が続くようなら、次の水やりのタイミングで規定通りの薄さの液体肥料を与えます。その後は、成長期(5月~9月)の間、2週間に1回程度のペースで液体肥料を与えます。
固形肥料(緩効性肥料)はいつから?
丸坊主後の回復期において、固形肥料(土の上に置くタイプや土に混ぜ込むタイプ)の使用は推奨されません。なぜなら、固形肥料は水やりのたびに少しずつ溶け出しますが、その濃度をコントロールできず、弱った根の近くで意図せず高濃度になってしまうリスクがあるためです。
固形の緩効性肥料を使い始めるのは、丸坊主から完全に回復し、葉が青々と茂り、明らかに安定した成長軌道に乗ってから(剪定から最低でも2~3ヶ月後、または翌年の成長期から)にしましょう。回復期は、濃度を確実にコントロールできる「液体肥料」一択と覚えてください。
水やりの最適なタイミング
この見出しでは、丸坊主後の「芽が出るまで」と「芽が出てから」で、水やりの最適なタイミングがどのように変化するかを、より具体的に解説します。
1.芽が出るまでの水やり(最重要:我慢の時期)
前述の通り、「土が中まで完全に乾き切ったら、ようやく水を与える」というタイミングです。葉がないため、土の乾燥は驚くほどゆっくりになります。室内環境によっては、2週間、あるいは3週間に1回程度の水やりで十分なことも珍しくありません。
「水やりを忘れる」くらいの感覚で、とにかく土の乾燥を徹底的に優先してください。この時期の過湿は、ほぼ確実に失敗に繋がります。
2.新芽が出始めてからの水やり(徐々に戻す時期)
幹のあちこちからポツポツと緑色の新芽が出始めると、ガジュマルは再び水を必要とし始めます。この新芽が、新しい「蒸散の口」になるためです。しかし、まだ葉が小さいため、急に水やりの頻度を剪定前に戻してはいけません。
新芽が成長し、葉が少しずつ開いてきたら、水やりの頻度を「土が完全に乾いたら」から「土の表面が乾き、中の湿り気が少なくなってきたら」というタイミングへ、徐々に移行させていきます。
新しい葉の成長速度や枚数に合わせて、水やりのペースを少しずつ、少しずつ戻していくイメージです。赤ちゃんの成長に合わせて食事(水)の量や回数を調整していくのに似ていますね。焦らず、ガジュマルの様子をよく観察しましょう。
ガジュマルの丸坊主を成功させるまとめ
最後にガジュマルを丸坊主にするという一大プロジェクトを成功させるための重要な鍵を、チェックリストとしてまとめます。
チェックリスト
- ガジュマルの丸坊主は樹形のリセットや健康回復が目的
- 実施する時期は「5月~7月」の成長期(気温20℃以上)が絶対条件
- 気温が15℃を下回る秋から冬の丸坊主は枯れるリスクが非常に高いため厳禁
- 剪定バサミは作業前に必ず火やアルコールで消毒する
- ガジュマルの白い樹液はかぶれる可能性があるため手袋を必ず着用する
- 樹液が床や服に付くと取れにくいため新聞紙などで広範囲を養生する
- 切り口には雑菌防止と乾燥防止のため癒合剤を塗ると安心
- 植え替えと丸坊主の同時作業は株に負担が大きすぎるため絶対に避ける
- 丸坊主直後の水やりは「徹底的に控える」ことが成功の最重要ポイント
- 葉がない状態では水分の蒸散がないため過湿は即、根腐れに繋がる
- 土が中まで完全に乾いたことを指や割り箸で確認してから水を与える
- 剪定直後の1週間は直射日光を避けた明るい日陰で休ませる
- その後はレースカーテン越しなど柔らかい光が当たる暖かい場所に置く
- 芽が出ない原因は「時期ミス」「水のやりすぎ(根腐れ)」「日光・温度不足」が主
- 肥料は剪定直後に絶対に与えない(肥料焼けの原因)
- 新芽が安定して成長を始めてから(約1ヶ月後~)薄めた液体肥料をごく少量から与える
