
観葉スタイル・イメージ
繊細な葉姿がおしゃれな観葉植物、エバーフレッシュ。その涼しげな見た目に惹かれて室内に迎えたものの、「エバーフレッシュがうまく育たないのですが、どうしてでしょうか?」と悩んでいませんか。
日中は葉を開き、夜は閉じて眠る可愛らしい特性を持つ反面、突然葉が黄色くなったり、ひょろひょろと元気がなくなったりと、デリケートな一面もあります。
特に室内での育て方には、いくつかのポイントがあります。
この記事では、「エバーフレッシュを室内で置くならどこに置くべき?」や「エバーフレッシュは毎日水やりが必要ですか?」といった基本的な疑問から、葉が落ちる原因、適切な剪定や曲げ方のテクニック、さらには虫や花への対処法まで、あなたが抱える悩みを解決します。
正しい耐陰性の知識や風通しの重要性を理解し、エバーフレッシュを生き生きと育てるための秘訣を詳しく解説していきます。
ポイント
- エバーフレッシュの基本的な育て方
- 葉が落ちるなど悩み別の具体的な対処法
- 樹形を美しく保つ剪定や曲げ方のコツ
- 害虫対策と健康な状態を維持する秘訣
コンテンツ
エバーフレッシュの育て方!室内での基本

観葉スタイル・イメージ
参考
- エバーフレッシュを室内で置くならどこに置くべき?
- エバーフレッシュは毎日水やりが必要ですか?
- 耐陰性と日当たりの最適なバランス
- 健康に育てるための風通しのコツ
- ひょろひょろにしないための剪定方法
エバーフレッシュを室内で置くならどこに置くべき?

観葉スタイル・イメージ
結論から言うと、エバーフレッシュを室内で置くのに最も適した場所は、レースカーテン越しに柔らかな日差しが入る明るい窓辺です。
この場所が、エバーフレッシュが持つポテンシャルを最大限に引き出し、健やかな成長を促します。
エバーフレッシュは本来、中南米などの暖かく日光が豊富な熱帯雨林地域が原産の植物です。そのため、生命活動の根幹である光合成を活発に行うためには、十分な日光が欠かせません。
しかし、原産地の木漏れ日のような光とは異なり、日本の特に夏場の強すぎる直射日光は、繊細な葉を傷つける「葉焼け」の大きな原因になってしまいます。
葉焼けを起こした部分は光合成の能力を失い、葉が白っぽく変色したり、パリパリに乾燥したりして、残念ながら元に戻ることはありません。
そこで、薄手のレースカーテンが優れたフィルターの役割を果たします。
強すぎる日差しを和らげ、まるで木漏れ日のような優しい光に変えてくれるため、葉焼けのリスクを回避しながら、成長に必要な光量を確保できる理想的な環境となるのです。
エアコンの風には要注意
エバーフレッシュを置く上で、日光と同じくらい注意したいのがエアコンの風です。多くの植物にとって、人工的な風は大きなストレスとなります。
特に乾燥した風が直接当たると、植物は葉の気孔から急激に水分を奪われ(蒸散が過度に進み)、葉がチリリになったり、最悪の場合、一晩で全ての葉を落としてしまったりすることもあります。
これは植物の防御反応ですが、株にとっては大きなダメージです。リビングなどに置く際は、エアコンの吹き出し口から最低でも1.5~2メートルは離れた場所を選んであげましょう。
また、一年を通して同じ場所に置きっぱなしにするのではなく、季節ごとに置き場所を微調整するのも上級者のテクニックです。
夏は日差しが強すぎるため少し窓から離し、壁際に置くことで反射光を利用するのも良いでしょう。
逆に、日照時間が短くなる冬は、できるだけ窓辺に近づけて貴重な光を最大限当ててあげると、元気に冬を越すことができます。
エバーフレッシュは毎日水やりが必要ですか?

観葉スタイル・イメージ
いいえ、エバーフレッシュは毎日水やりが必要なわけではありません。
むしろ、「毎日必ずあげる」というルールを決めてしまうことは、観葉植物を枯らしてしまう最も一般的な原因である「根腐れ」を引き起こす可能性を高めてしまいます。
水やりの最適なタイミングは、季節や室内の環境によって常に変化します。そのため、最も確実な方法は、「土の表面が乾いたのを確認してから」与えることです。
実際に指で土を数センチほど触ってみて、湿り気を感じなくなったら水やりのサインです。
与える際は、躊躇せず鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与えてください。この「乾湿のメリハリ」が、根を健康に保つ上で非常に重要になります。
季節に合わせた水やり頻度の調整
- 春~秋(生育期):気温の上昇とともに成長が活発になり、水をよく吸い上げるため、土の乾きも早くなります。土の表面が乾いたら、すぐに水を与えましょう。特に気温が高い夏場は蒸散も激しく、1~2日で土が乾くこともあります。こまめに土の状態をチェックする習慣が大切です。
- 冬(休眠期):気温が下がると成長が緩やかになり、水の必要量も格段に減ります。この時期に生育期と同じ感覚で水を与えると、土が常に湿った状態になり根腐れを起こしやすくなります。土の表面が乾いてから2~3日後を目安に水やりをし、少し乾燥気味に管理するのが冬越しのコツです。
ただし、冬場でもエアコンなどの暖房が常に効いていて、室温が20℃以上に保たれている場合は、エバーフレッシュが休眠に入らず、生育期と同じように水を欲しがることがあります。
このような場合は、冬だからと一括りにせず、あくまで「土の状態」を基準に判断することが、失敗しないための最も確実な秘訣です。
ちなみに、水の量が足りているかどうかのサインとして、昼間に葉がしっかり開いているかを確認する方法もあります。
エバーフレッシュは水分が不足すると、蒸散を抑えるために昼間でも葉を閉じ気味になります。
もし日中も葉がしょんぼりと閉じているようなら、それは水不足のサインかもしれませんよ。
耐陰性と日当たりの最適なバランス

観葉スタイル・イメージ
エバーフレッシュにはある程度の耐陰性(日陰に耐える力)がありますが、これは「暗い場所でも元気に育つ」という意味ではありません。
正しくは「ある程度の期間であれば、日陰の環境にも耐えることができる」という性質です。本来は日光を好む植物であるため、完全に日の当たらない暗い場所で長期間にわたって健康に育てるのは難しいと言えます。
耐陰性を過信して暗い場所に長期間置くと、植物は生き残るためにエネルギー消費を抑えようとし、いくつかの望ましくない変化を見せ始めます。
暗い場所で起こりうること
- 徒長(とちょう):わずかな光を求めて、茎や枝が通常よりも長く、間延びして伸びてしまいます。節と節の間が広がり、ひょろひょろとした弱々しい姿になるのが特徴です。
- 葉落ち:光合成が十分にできず、株全体の体力を維持するために、エネルギー効率の悪い古い葉や下葉から順番に落としていきます。
- 葉色の悪化:葉のツヤがなくなり、健康的な濃い緑色ではなく、色が薄くなることがあります。また、特徴である「就眠運動」をしなくなることもあります。
エバーフレッシュにとって理想的なのは、「明るい日陰」と表現される環境です。これは、直射日光は当たらないものの、日中は電気をつけなくても問題なく本が読める程度の明るさがある場所を指します。
具体的には、窓から少し離れたリビングの中央や、安定した光が差し込む北向きの窓辺などが該当します。
環境の急変に注意!
もし購入した園芸店が屋外などの非常に明るい場所だった場合、急に室内の暗い場所へ移動させると、光量の急激な変化という大きなストレスに驚いて、葉を大量に落としてしまうことがあります。
環境に適応するための生理現象ですが、見た目にも寂しくなってしまいます。
その場合は、最初の1週間は最も明るい窓辺、次の1週間は少し離れた場所、というように段階的に移動させて、1~2週間かけて徐々に目的の環境に慣らしてあげるのがおすすめです。
健康に育てるための風通しのコツ

観葉スタイル・イメージ
エバーフレッシュを室内で健康に、そして美しく育てる上で、日光や水やりと同じくらい、いや、時としてそれ以上に「風通し」が重要な要素となります。
多くの人が見落としがちなこのポイントは、病害虫の発生率に直接関わってきます。空気がよどんだ場所に置いていると、病気や害虫が活動しやすい環境を提供してしまい、様々なトラブルのリスクが格段に高まります。
風通しを良くすることには、主に2つの大きなメリットがあります。
- 病害虫の予防:多くのカビ系の病気(うどんこ病や炭そ病など)の胞子や、カイガラムシ、ハダニといった害虫は、湿気が多く空気が滞留する場所を好んで発生・繁殖します。人間が心地よいと感じるような適度な空気の流れがあることで、これらの発生を物理的に抑制し、植物をクリーンな状態に保つことができます。
- 土の乾燥促進と根の健康:水やり後、土がずっと湿ったままだと、土中の酸素濃度が低下し、根が呼吸困難に陥り「根腐れ」の原因になります。風通しが良いと土の表面が適度に乾き、鉢の中の水分が健全に循環するため、根が健康な状態を保ちやすくなります。
室内で理想的な風通しを確保するためには、以下のような日々の少しの工夫が有効です。特に集合住宅などで窓が限られている場合でも、実践できることはたくさんあります。
室内での風通し確保術
- 定期的な換気:基本ですが、最も効果的です。1日に5~10分でも窓を開けて、部屋の空気を新鮮な外気に入れ換える習慣をつけましょう。
- サーキュレーターの活用:空気を循環させるためのサーキュレーターや扇風機を使い、部屋の空気を緩やかに動かすのも非常に有効です。ただし、AND PLANTSの公式サイトにもあるように、植物に直接強い風を当て続けると乾燥の原因になるため、首振り機能を使ったり、壁に当てて間接的な風を送ったりする工夫が必要です。
- 配置の工夫:植物同士を密集させすぎず、それぞれの株周りに空気が通るための空間を作りましょう。壁際に置く場合も、少し隙間を空けることが大切です。
- 剪定の実施:後述する「剪定」を行い、葉の密集を防ぎ、株の内部まで風が通り抜けるようにします。
特に日本の梅雨の時期など、湿度が高くなりやすい季節は意識的に風通しを良くしてあげることが、エバーフレッシュを元気に夏越しさせるための重要な秘訣です。
ひょろひょろにしないための剪定方法

観葉スタイル・イメージ
エバーフレッシュが、まるで力なく空を目指すかのようにひょろひょろと細長く伸びてしまうのは、主に日照不足が原因で起こる「徒長(とちょう)」という典型的な現象です。
これを防ぎ、幹や枝がしっかりとした、バランスの取れた美しい樹形を維持・形成するために「剪定」が非常に効果的な手段となります。
剪定に最も適した時期は、植物の生命力が最も高まる5月~9月の生育期です。この時期に剪定を行うと、切り口からすぐに新しい芽が吹き、ダメージからの回復も非常に早くなります。
逆に、成長が止まる冬の寒い時期に大きな枝を切るなどの強い剪定を行うと、回復する体力がなく、株が大きなダメージを受けてしまう可能性があるので、軽い整枝程度にとどめ、大きな手術は避けましょう。
剪定の具体的な手順
- 理想の樹形をイメージする:作業を始める前に、まずはどのような形にしたいかを大まかにイメージします。ただ闇雲に切るのではなく、「全体の高さを現在の3分の2に抑えたい」「横の広がりをすっきりさせたい」といったゴールを決めることで、作業に一貫性が生まれます。
- 不要な枝を切り落とす(間引き剪定):明らかに間延びしている枝や、内側に向かって伸びて他の枝と交差している枝、枯れている枝などを、枝の付け根からきれいに切り落とします。これにより、株全体の風通しと日当たりが改善されます。
- 高さを調整する(切り戻し剪定):全体の高さを抑えたい場合は、一番太い幹や主となる枝を、思い切って好みの高さでカットします。この時、必ず「節」の少し上で切るのがポイントです。節には新しい芽を出す力があるため、カットした部分の少し下にある節から新しい脇芽が出てきて、そこから枝分かれしていきます。
剪定を怖がる必要は全くありませんよ。
エバーフレッシュは非常に生命力が強く、萌芽力(ほうがりょく:新しい芽を出す力)も旺盛なので、生育期であれば大胆にカットしても驚くほど元気に新芽を出してくれます。
失敗を恐れず、思い切ってチャレンジしてみましょう。
定期的な剪定は、ひょろひょろになるのを防ぐだけでなく、前述した「風通し」を良くする直接的な効果もあります。
さらに、剪定で出た元気な枝は、清潔な土に挿しておく「挿し木」に利用して、新しい株として増やすこともできるので、ぜひ試してみてください。
エバーフレッシュの育て方!室内のトラブル解決

観葉スタイル・イメージ
参考
- エバーフレッシュがうまく育たない原因は?
- 葉が落ちる、葉が黄色になる時の対処法
- 虫を発見した時の駆除と予防策
- エバーフレッシュに咲く花について
- 理想の樹形にするための曲げ方のコツ
エバーフレッシュがうまく育たない原因は?

観葉スタイル・イメージ
「日当たりや水やりに自分なりに気を使っているはずなのに、なぜかうまく育たない…」
と感じる場合、その原因は、環境の急激な変化へのストレスや、季節ごとの育て方のミスマッチなど、少し見方を変えることで見つかるかもしれません。
エバーフレッシュは比較的丈夫で育てやすい植物に分類されますが、環境の変化には意外と敏感な一面があります。
特に、園芸店から自宅に持ち帰った直後や、春から夏、秋から冬へと季節が大きく変わるタイミングで調子を崩すことが多いです。考えられる主な原因を、チェックリスト形式で見ていきましょう。
うまく育たない時にチェックしたい5つのポイント
- 置き場所は本当に適切か?:日中の数時間だけ強い西日が当たっていませんか?夜間、窓からの冷気で冷え込んでいませんか?エアコンの風が間接的にでも当たっていませんか?
- 水のやり方は本当に適切か?:「土が乾いたからあげる」のではなく「〇日に一回」と決めていませんか?鉢の大きさに対して与える水の量が少なすぎませんか?(鉢底から流れ出るまでが基本です)
- 根詰まりを起こしていないか?:購入してから2年以上一度も植え替えていない場合、鉢の中で根がぎゅうぎゅうになり、水も栄養も吸えない状態になっている可能性があります。これは非常によくある原因です。
- 季節に合った管理ができているか?:気温が下がり成長が止まっている冬に、良かれと思って栄養剤や肥料を与えていませんか?これは根を傷める「肥料焼け」の原因になります。
- 害虫は潜んでいないか?:葉の裏や茎の付け根など、見えにくい場所に小さな虫が付着していませんか?ベタベタした透明な液体が付着している場合も害虫のサインです。
これらのポイントを一つずつ、自分の育て方と照らし合わせて確認することで、不調の根本的な原因が見えてくるはずです。特に見落としがちなのが「根詰まり」です。
鉢底の穴から白い根が見えていたり、水やりをしても水の染み込みが極端に悪くなったりしたら、それは植え替えの明確なサインです。
生育期である春から秋の間に、現状の鉢より一回り(直径で3cm程度)大きな鉢に、新しい土で植え替えてあげることで、劇的に元気になることがあります。
葉が落ちる、葉が黄色になる時の対処法

観葉スタイル・イメージ
エバーフレッシュの葉が落ちる、または黄色くなるのは、言葉を話せない植物が体で示している重要なSOSサインです。
原因は一つとは限りませんが、症状の出方によってある程度の原因を推測することが可能です。最も一般的でよく見られる原因と、その具体的な対処法を表にまとめました。
| 症状 | 主な原因 | 具体的な対処法 |
|---|---|---|
| 葉がハラハラとポロポロ落ちる | 水切れ、日照不足、寒さ、環境の急変 | まず土を確認し、乾いていたらすぐに水をたっぷり与える。暗すぎる場合はより明るい場所に移動させる。冬場は最低でも10℃以上、できれば15℃程度を保てる暖かい場所に置く。購入直後や置き場所を変えた直後であれば、環境に慣れるまでの一時的な症状の可能性もある。 |
| 下の方の古い葉から黄色くなる | 根腐れ、根詰まり、自然な新陳代謝 | 水のやりすぎが最も疑われる。水やりの頻度を減らし、土が乾いてから与えるように徹底する。受け皿の水は必ず捨てる。鉢底から根が出ている場合は根詰まりの可能性が高いので、生育期に植え替えを検討する。数枚程度であれば、新しい芽を出すための自然な生理現象の場合もある。 |
| 葉先からパリパリに乾燥・変色する | 水不足、極度の空気の乾燥 | 土の乾きが早すぎる場合は水やりの頻度を増やす。霧吹きで葉に水をかける「葉水」を1日に数回行い、葉の周りの湿度を高める。エアコンの風が直接当たらない場所に移動する。加湿器の使用も非常に効果的。 |
| 全体的に葉が黄色く、ツヤがなく元気がない | 肥料の与えすぎ(肥料焼け)、日光の当てすぎ(葉焼け) | 冬場の肥料やりは絶対に中止する。生育期でも規定量以上与えないこと。肥料を与えすぎた場合は、一度たっぷりの水で土中の肥料を洗い流す応急処置もある。夏場の強すぎる直射日光を避け、レースカーテン越しに置く。 |
新芽は茶色いので心配無用!
これは重要なポイントですが、エバーフレッシュの新芽はもともと産毛に覆われた茶色っぽい色をしています。
まるで枯れているかのように見えるため、初めて見る方は驚くかもしれませんが、これは健康な新芽の証拠です。
成長と共に産毛が取れ、きれいな緑色に変化していきます。枯れていると勘違いして、大切な新芽を摘み取ってしまわないように注意してください。
葉が落ちたり黄色くなったりしても、幹や枝がしっかりしていれば、すぐに諦める必要はありません。原因を特定し、適切な環境を整えてあげることで、また元気な新芽を出してくれる回復力を持っています。
虫を発見した時の駆除と予防策

観葉スタイル・イメージ
どんなに気をつけていても、室内で育てているエバーフレッシュに虫(害虫)がついてしまうことがあります。
被害を最小限に抑えるためには、早期発見と、それぞれの害虫の特性に合わせた適切な対処が鍵となります。
ハダニ
0.5mm程度の非常に小さなクモの仲間で、主に葉の裏に寄生して栄養を吸います。乾燥した環境を好み、特にエアコンの効いた室内では発生しやすくなります。
被害が進行すると葉の色が白っぽくカスリ状に抜け、さらに増殖するとクモの巣のようなものを張ることもあります。
対処法:ハダニは水に非常に弱いため、シャワーで葉の裏までしっかり洗い流すのが最も手軽で効果的です。
数が少ないうちは、濡らしたティッシュや布で拭き取るだけでも駆除できます。多発してしまった場合は、市販の観葉植物用の殺虫剤を使用しましょう。「葉水」は日々の予防として極めて有効です。
カイガラムシ
白い綿のような姿をしたコナカイガラムシ類や、硬い殻をかぶったゴマ粒のような姿のカタカイガラムシ類が代表的です。
植物の栄養を吸うだけでなく、ベタベタした排泄物が原因で、葉が黒いススで覆われたようになる「すす病」というカビの病気を誘発することもあります。
対処法:成虫は硬い殻やロウ物質で覆われているため薬剤が効きにくいです。数が少なければ、歯ブラシやヘラのようなもので、こすり落として物理的に駆除するのが最も確実です。
幼虫が発生する春~初夏の時期であれば、アース製薬の害虫駆除マニュアルで推奨されているような専用の殺虫剤が有効です。
害虫を寄せ付けないための最大の防御策「予防」
害虫対策で最も重要なのは、発生させない環境を作ることです。日頃から以下の点を心がけるだけで、リスクを大幅に減らすことができます。
- こまめな葉水:霧吹きで葉の裏までしっかりと湿らせることで、乾燥を好むハダニの発生を効果的に予防できます。ホコリを洗い流す効果もあります。
- 風通しの確保:前述の通り、空気がよどまないように、定期的な換気や剪定を怠らないことが大切です。
- 日々の観察:水やりの際に、ついでに葉の裏や茎の付け根をチェックする習慣をつけましょう。どんな害虫も、数が少ないうちに対処するのが一番です。
エバーフレッシュに咲く花について

観葉スタイル・イメージ
エバーフレッシュは葉を鑑賞する観葉植物というイメージが強いですが、生育環境が良く、株が十分に成熟すると、可愛らしい花を咲かせることがあります。
その姿は、まるで夏の夜空に咲く線香花火のようです。
開花時期は主に気候が温暖な春から夏(5月~9月頃)にかけてで、枝の先に、タンポポの綿毛のような、丸くて黄色いふわふわとした花が複数まとまって咲きます。
この花には香りはありませんが、そのユニークな見た目は、育てている人へのささやかなプレゼントと言えるでしょう。
花が咲いた後は、条件が良ければ受粉し、赤いサヤエンドウのような特徴的なサヤができます。このサヤが熟すと、中から黒い光沢のある種が採れることもあります。
エバーフレッシュの和名である「アカサヤネムノキ(赤鞘合歓木)」は、まさにこの赤いサヤの姿に由来しています。
室内で管理している観葉植物に花を咲かせるのは、日照条件などから少し難しいとされていますが、不可能ではありません。
長年大切に育てていると、ある日突然、その愛らしい花を見せてくれるかもしれません。それは植物がその環境を気に入っている証拠でもあり、育てる上での大きな喜びの一つですね。
花が咲いた後の注意点
花を咲かせたり、その後に種子をつけたりすることは、植物にとって子孫を残すための非常に重要な活動であり、多くのエネルギーを消費します。
そのため、花が咲き終わった後は、株が一時的に体力を消耗して、葉が黄色くなったり、成長が鈍ったりすることがあります。
もし株の元気がなくなってきたと感じたら、鑑賞後は早めに花がらを摘み取ってあげることで、株の負担を軽減できます。
また、開花時期にはエネルギーを補給するために、水で薄めるタイプの液体肥料などを与えてサポートしてあげるのも良いでしょう。
理想の樹形にするための曲げ方のコツ
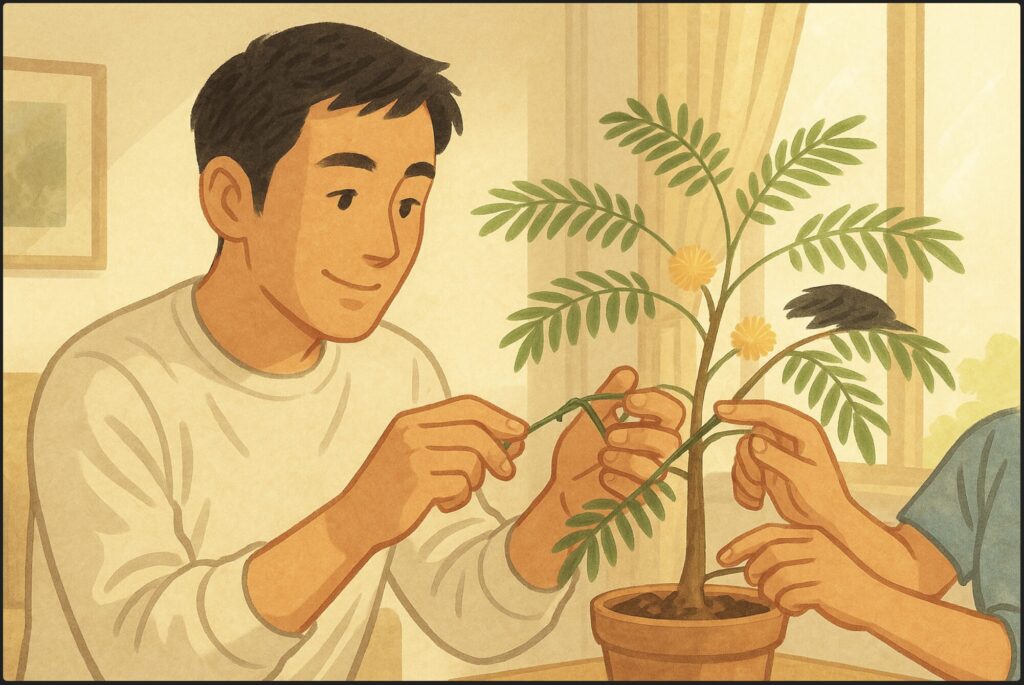
観葉スタイル・イメージ
エバーフレッシュの大きな魅力の一つは、そのしなやかな幹や枝を活かして、盆栽のように自分好みの樹形に仕立てられる点です。
市販されているまっすぐな姿も美しいですが、針金などを使って枝を緩やかに誘導する「曲げ方」のテクニックを取り入れることで、世界に一つだけの、より個性的で動きのあるおしゃれな姿を楽しむことができます。
この作業に最も適しているのは、枝がまだ柔らかく、細胞分裂が活発な春から夏の生育期です。この時期は癖がつきやすく、もし作業中に小さな傷がついても回復が早くなります。
すでに木質化して太く硬くなった幹を無理に曲げようとすると、「ポキッ」と折れてしまう危険性が非常に高いので、比較的新しく、鉛筆くらいの太さまでの若い枝を対象に行いましょう。
針金を使った基本的な曲げ方(整枝)
- 準備物:植物を傷つけにくいアルミ線や銅線など、手で容易に曲げられる園芸用の針金、そして針金を切るためのペンチを用意します。針金の太さは、曲げたい枝の太さの3分の1から半分程度が目安です。
- 針金を巻く:まず、曲げたい枝の根元(幹との分岐点など)に針金を数回巻きつけてしっかりと固定します。そこを起点として、枝先にむかって、45度くらいの角度を保ちながら、きつすぎず緩すぎず、らせん状に優しく巻き付けていきます。
- ゆっくりと曲げる:針金を巻き終えたら、枝を両手で支えながら、植物の声を聞くようなイメージで、決して無理な力を加えず、「ミシミシ」と音がしない範囲で、ゆっくりと理想のカーブになるよう曲げていきます。
- 固定と解放:数ヶ月から、長い場合は半年ほどそのままの状態で固定し、枝に癖がついたことを確認したら、針金を外します。外す際は、枝を傷つけないようにペンチで針金を細かく切って取り除くのが安全です。
焦りは禁物!成功への近道は「ゆっくり」
一度に理想の形まで曲げようとせず、今日は少し、一週間後にもう少し、というように数週間から数ヶ月かけて徐々に曲げていくのが成功のコツです。
また、植物は成長して太くなるため、針金が枝に食い込んでしまうことがあります。定期的に様子を見て、食い込みがひどい場合は、一度外して少し緩めに巻き直しましょう。
この曲げ方の技術を使えば、直線的な株を優雅なS字カーブにしたり、四方八方に広がる枝をまとめたりと、より愛着の湧くあなただけの一鉢に育て上げることができます。
エバーフレッシュの育て方!室内で楽しむ要点まとめ
チェックリスト
- 置き場所はレースカーテン越しの明るい窓辺が最適
- 強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるため避ける
- エアコンの風が直接当たる場所は厳禁
- 水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと与える
- 水のやりすぎによる根腐れに注意する
- 受け皿に溜まった水は必ず捨てる
- 冬は水やりを控えめにし乾燥気味に管理する
- ある程度の耐陰性はあるが真っ暗な場所は不向き
- 病害虫予防のために風通しを良くする
- ひょろひょろに伸びたら生育期に剪定を行う
- 葉が落ちる原因は水切れや日照不足など様々
- 葉が黄色くなるのは根腐れや根詰まりのサイン
- ハダニやカイガラムシは早期発見と対処が重要
- 予防としてこまめな葉水が効果的
- 元気な株は黄色くふわふわした花を咲かせることがある
