
観葉スタイル・イメージ
おしゃれなインテリアグリーンとして、不動の人気を誇るパキラ。中でも、数本の幹が芸術的に編み込まれたパキラは、空間に洗練された雰囲気と生命力をもたらす存在感があり、お部屋のシンボルツリーとしても活躍しますよね。
「発財樹」や「Money Tree」という縁起の良い別名もあり、贈り物としても喜ばれます。この魅力的な編み込みパキラを「自分の手で作り上げてみたい」と思ったことはありませんか?
しかし、いざパキラの挿し木から編み込みに挑戦しようとすると、「作り方は専門知識がないと難しいのでは?」「パキラの編み込みの時期はいつですか?」といった具体的な疑問や、「パキラの挿し木から根が出るまでどのくらいかかりますか?」という成功までの期間に対する不安が湧いてくるものです。
また、愛情を込めて自作した後の寿命や、成長して形が崩れた際の仕立て直し、美しい樹形を保つための剪定方法も気になりますよね。
「編み込みパキラは枯れやすい?」という気になる噂や、実際に枯れやすいとされる原因、予期せぬ害虫への対策、そして多くの人が経験するよくある失敗は、始める前にしっかりと把握しておきたいところでしょう。
この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消し、具体的な編み込みパキラの切り戻し方法は?といった一歩進んだテクニックまで、専門店のスタッフに相談するような感覚で深く理解できるよう、網羅的に解説していきます。
ポイント
- パキラの挿し木から編み込みまでの具体的な手順がわかる
- 失敗しないための注意点や管理のコツがわかる
- 枯れる原因や害虫などのトラブル対処法がわかる
- 剪定や仕立て直しなど長く楽しむ方法がわかる
コンテンツ
パキラの挿し木から編み込みまでの基本手順

観葉スタイル・イメージ
参考
- 自作するための基本的な作り方
- パキラの編み込みの時期はいつですか?
- 挿し木から根が出るまでどのくらい?
- よくある失敗と成功させるコツ
- 適切な剪定で樹形を整える
自作するための基本的な作り方

観葉スタイル・イメージ
結論から言うと、編み込みパキラは正しい手順といくつかのコツさえ押さえれば、ご自宅で十分に自作することが可能です。お店で販売されているような、幹ががっしりと絡み合った立派な姿を目指すには時間と愛情が必要ですが、その過程こそが園芸の醍醐味です。
最も大切なのは、編み込みに適した若い苗を選ぶことと、パキラの成長を妨げない丁寧な作業を心がけること。この2点を守ることで、成功率は格段に上がります。
準備するもの
作業をスムーズに進めるため、まずは必要な道具をリストアップして確実に揃えましょう。特に苗の選び方と土の準備は、その後のパキラの健康を左右する非常に重要なポイントになります。
【準備リスト】
- パキラの苗(2〜5株):幹がまだ緑色で若く、指で軽く曲げられるほど柔らかい「実生苗(みしょうなえ)」を30cm程度の高さで用意するのが理想です。3本あれば三つ編みが作れます。
- 鉢:植える苗の数や成長を見越して、4〜5号サイズ(直径12〜15cm)から始めると良いでしょう。デザインだけでなく、鉢底穴がしっかり開いている排水性の良いものを選びます。
- 観葉植物用の土:市販されている観葉植物専用の培養土がおすすめです。軽石などが配合され水はけが良く、初期生育に必要な肥料が含まれているため、初心者でも安心して使えます。
- ハサミ:植物の細胞を潰さないよう、切れ味の良い清潔な剪定バサミを準備します。使用前にはアルコールで刃を拭き、病気の感染を防ぎましょう。
- 紐、支柱:編み込みを固定するための麻紐やビニールタイ、苗が倒れないように支えるための細い支柱が必要です。幹に食い込みにくい柔らかい素材の紐を選びます。
- その他:鉢底に敷く鉢底ネットと鉢底石、作業中の土汚れを防ぐ園芸シートや新聞紙、手を保護する手袋があると便利です。
パキラには、種から発芽させて育てた「実生苗」と、成長した株の枝(幹)を切り、それを土に挿して発根させた「挿し木苗」の2種類が存在します。
編み込みになぜ実生苗が適しているかというと、幹が若く柔軟性に富み、これから成長して太くなるポテンシャルを持っているからです。実生苗は根元がぷっくりと膨らんでいることが多く、これが一つの見分けるポイントになります。
一方、市販の安価なパキラの多くは海外から輸入された幹を挿し木にしたもので、すでに幹が木質化して硬く、成長してもほとんど太くならないため、編み込み作業には向きません。
編み込みの手順
すべての道具が揃ったら、いよいよ編み込み作業のスタートです。焦らず、一つひとつの工程を丁寧に進めていきましょう。
- 苗の準備(剪定):まず、編み込み作業の邪魔になる、それぞれの苗の幹の下半分から出ている小さな枝や葉を、清潔なハサミで元から切り落とします。幹だけのすっきりした状態にすることで、作業が格段にしやすくなります。
- 寄せ植え:新しい鉢の底に鉢底ネットを敷き、鉢底石を2〜3cmの高さまで入れます。その上に観葉植物用の土を鉢の半分ほど入れ、苗をポットから優しく取り出します。根が固まっている(根鉢)場合は、底の部分を少しだけ手でほぐし、それぞれの苗を配置します。2本なら平行に、3本なら正三角形を描くように、幹同士が10cm程度の間隔を保てるように植え付けます。隙間に土を足し、割り箸などで軽くつつきながら根の間に土をいきわたらせます。
- 編み込み:いよいよハイライトの編み込みです。苗の幹を三つ編みの要領で、優しく、そして「ゆるく」交差させていきます。将来幹が太くなることを想定し、編み目の間に指が1本スムーズに入るくらいの余裕を持たせるのが最大のコツです。無理にきつく編むと、成長した際に幹同士が締め付け合い、枯れる原因になります。高さの半分から3分の2程度まで編み上げればOKです。
- 固定:編み終わりの部分が自然にほどけてしまわないよう、麻紐やビニールタイで軽く結んで固定します。この時も、将来の成長を妨げないように、きつく縛りすぎないことが大切です。株全体が不安定で倒れそうな場合は、中心に支柱を立てて支えてあげましょう。
- 仕上げの剪定:最後に、株全体を眺めてみましょう。葉が重なり合って密集している部分は、光が当たらず風通しも悪くなります。バランスを見ながら、内側に向いている葉や不要な葉を数枚剪定して、株全体が呼吸しやすいように整えます。
これであなただけのオリジナル編み込みパキラの完成です。作業後は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与え、その後は風通しの良い明るい日陰で1週間ほど休ませて(養生させて)から、通常の置き場所での管理に移行してください。
パキラの編み込みの時期はいつですか?

観葉スタイル・イメージ
パキラの編み込みや植え替えといった、株に負担のかかる作業に最適な時期は、植物の生命力が最も高まる生育期の5月〜7月です。この期間は、人間で言えば最もエネルギッシュな成長期にあたり、作業によるストレスからの回復力が格段に高まります。
その理由は、日本の気候とパキラの成長サイクルにあります。春から初夏にかけては、気温が上昇し日照時間も長くなるため、パキラは活発に光合成を行い、新しい根や芽を伸ばすためのエネルギーを豊富に蓄えています。
植物の成長を促すホルモンも活性化しているため、多少のダメージを受けてもすぐに修復し、新たな環境に適応しようとする力が強いのです。
逆算すると、8月の厳しい猛暑日や、成長が緩やかになり始める秋以降の作業は避けるのが賢明です。特に、夜間の気温が15℃を下回るような季節に作業を行うと、パキラは回復するための十分なエネルギーを生み出せず、最悪の場合、そのまま弱って枯れてしまうリスクが高まります。
気象庁の過去のデータなどを参考に、お住まいの地域で気温が安定してくる時期を見計らって計画を立てるのが良いでしょう。冬はパキラにとって休眠期にあたるため、このような負担の大きい作業は原則として行いません。
作業を避けるべきタイミングとその理由
- 真夏の猛暑日(8月):過度な高温と強い日差しは、植え替え直後の弱った株には大きなストレスとなります。人間が夏バテするように、植物も体力を消耗します。
- 秋(10月以降):気温の低下とともに成長が鈍化し始めます。これから来る冬に備えてエネルギーを蓄える時期なので、体力を消耗させる作業は禁物です。
- 冬期(12月〜2月):成長がほぼストップする休眠期です。この時期に受けたダメージは回復できず、春を待たずに枯れてしまう可能性が非常に高いです。
このように、パキラの気持ちになって成長カレンダーを理解し、最も活動的な時期に作業を行ってあげることが、編み込みプロジェクトを成功に導くための愛情のこもった配慮と言えるでしょう。
挿し木から根が出るまでどのくらい?

観葉スタイル・イメージ
剪定した枝を利用して挿し木でパキラを増やし、それを将来の編み込み材料にしたい場合、発根までにかかる期間はおおよそ10日〜2週間が目安となります。これは、5月〜7月の最適な時期に、元気の良い挿し穂(切った枝)を使い、適切な環境で管理した場合のスムーズな例です。
植物の成長には個体差があり、挿し穂の健康状態や、その後の温度・湿度管理によって、発根までの期間は変動します。
時には1ヶ月以上かかることもありますが、挿し穂の幹がしっかり硬く、葉が緑色を保っている限りは、水面下で発根の準備が着々と進んでいます。焦らず、気長に見守ってあげましょう。
土に挿した場合、発根したかどうかは見た目では分かりにくいですよね。そんな時は、挿し穂を指でつまんで、ごく軽い力で真上に引っ張ってみてください。少し抵抗を感じるようなら、土の中で新しい根が張り始めている証拠ですよ。
くれぐれも強く引っ張りすぎないように注意してくださいね!
発根を早め、成功率を上げるコツ
少しでも発根の成功率を高め、プロセスを早めたい場合は、いくつかの園芸テクニックが有効です。ひと手間加えることで、結果が大きく変わることもあります。
- 発根促進剤の活用:挿し穂の切り口に粉末状の発根促進剤をまぶしたり、水揚げの際に液体タイプのものを規定量混ぜたりすると、植物ホルモン(オーキシンなど)の働きで細胞分裂が活発になり、発根が劇的に促されます。園芸店やホームセンターで手軽に入手可能です。
- 水揚げを徹底する:土に挿す前に、切れ味の良い刃物で挿し穂の切り口を斜めにカットし直します。断面積を広げることで吸水効率が上がります。その後、1〜2時間ほど清潔な水に浸けておく「水揚げ」を行うことで、挿し穂が発根に必要な水分を十分に蓄えることができます。
- 無菌・無肥料の土を使う:挿し木には、栄養分が含まれていない清潔な土(バーミキュライト、赤玉土小粒、鹿沼土など)を使用するのが鉄則です。栄養豊富な培養土は、デリケートな切り口を腐らせる原因となる雑菌が繁殖しやすいため、発根するまでは避けましょう。
目で見て楽しむ「水挿し」という選択肢
土に挿す方法とは別に、透明なガラス瓶やコップに水を入れ、そこに挿し穂を活けておくだけの「水挿し」という簡単な方法もあります。この方法の最大のメリットは、日々の成長を目で見て確認できること。白い根が少しずつ伸びてくる様子は、生命の神秘を感じさせてくれます。
| 水挿し | 土挿し | |
|---|---|---|
| メリット | ・発根の様子が観察できる ・手軽に始められる ・キッチンなどでも清潔に管理できる | ・発根後の植え替えが不要 ・根がしっかり張りやすい ・比較的失敗が少ない |
| デメリット | ・水が腐りやすく、こまめな水替えが必要 ・土への植え替え時に根が環境変化に戸惑うことがある | ・発根の様子が見えない ・土や鉢の準備が必要 |
水挿しで根が5cmほどに伸びたら、土に植え替えるタイミングです。どちらの方法にも一長一短があるので、ご自身のライフスタイルや好みに合わせて選んでみてください。
よくある失敗と成功させるコツ

観葉スタイル・イメージ
手作りの編み込みパキラは非常に魅力的ですが、挑戦する過程でいくつかの落とし穴に陥りがちです。ここでは、多くの人が経験する典型的な失敗例と、それを未然に防ぎ、プロジェクトを成功に導くための具体的なコツを詳しく解説します。
| ありがちな失敗例とその心理 | 成功に導くための黄金ルール |
|---|---|
| きつく編み込みすぎる (愛情のあまり、きっちり綺麗に仕上げたいという思いから) | 将来の成長という「時間軸」を想像することが重要です。幹が成長して太くなることを見越し、編み目の中に指が1本スムーズに入るくらいの「遊び」を持たせてゆるく編みます。成長と共にその隙間は自然と埋まり、がっしりとした風格のある編み込みに育ちます。 |
| 苗の選択を間違える(挿し木苗で挑戦) (手に入りやすい安価な苗で始めてしまう) | スタートラインが肝心です。編み込みには、幹が若く柔軟で、これからの成長で太くなるポテンシャルを持つ「実生苗」を必ず選びましょう。硬く木質化した挿し木苗で無理に編もうとすると、幹に傷がつき、そこから枯れ込む原因になります。 |
| 作業する時期を考慮しない (思い立ったが吉日と、季節を問わずに始めてしまう) | 植物の成長サイクルに敬意を払いましょう。株に十分な体力があり、ダメージからの回復力が最も高い生育期(5月〜7月)に作業を行うのが鉄則です。休眠期である冬の作業は、植物にとって致命傷になりかねません。 |
| 寄せ植えの際に苗を密集させすぎる (小さな鉢にコンパクトにまとめようとしてしまう) | 根にもパーソナルスペースが必要です。寄せ植えの際は、それぞれの苗の根が将来伸びる空間を確保するため、最低でも10cm以上の間隔をあけて植え付けます。これにより、根同士の過度な競争や、根元の蒸れによる根腐れを防ぎます。 |
| 編み込み後のケアを怠る (作業が終わった安心感から、すぐに通常管理に戻してしまう) | 作業直後のパキラは、人間でいえば手術後の安静が必要な状態です。すぐに直射日光に当てるなどはせず、風通しの良い明るい日陰で1週間ほど養生させましょう。株が新しい環境にゆっくりと適応する時間を与えることが、その後の順調な成長につながります。 |
このように、単に技術的な問題だけでなく、少し先の未来を想像し、植物の立場に立って考えることが大切です。
特に「ゆるく編む」という点は、美しい完成形を目指す気持ちとは裏腹に感じるかもしれませんが、パキラが元気に、そして力強く育つための最も重要な愛情表現だと覚えておいてください。
適切な剪定で樹形を整える

観葉スタイル・イメージ
手作りの編み込みパキラを、時が経っても美しい芸術品のような状態で楽しむためには、戦略的かつ適切なタイミングでの剪定が不可欠です。
剪定は、単に伸びすぎた枝を切って見た目を整えるだけではありません。風通しを劇的に改善して病害虫の発生を防いだり、株の内部まで光を届けたり、さらには植物のエネルギーをどこに集中させるかをコントロールする、非常に重要な管理作業なのです。
剪定のタイミングとそれぞれの目的
剪定は、主に以下の3つの重要なタイミングで行います。それぞれの目的を理解することで、より効果的な剪定が可能になります。
- 編み込み前の準備剪定:これは編み作業をスムーズに行うための下準備です。編み込む予定の幹の下半分から出ている小さな枝や葉を、付け根から綺麗に整理します。これにより、幹だけのすっきりした状態になり、絡まりや間違いなく編み込み作業に集中できます。
- 編み込み直後の調整剪定:寄せ植えと編み込みによって、複数の株の葉が特定の場所に密集し、重なり合ってしまいます。この密集地帯は、光が当たらず風通しも悪くなるため、病気や害虫の温床になりがちです。不要な葉を間引くように剪定し、すべての葉が呼吸できる快適な空間を作ります。
- 成長過程での維持剪定:生育期になると、新しい枝葉が勢いよく伸びてきます。この時が樹形をコントロールするチャンスです。徒長(間延びしてひょろひょろと伸びること)した枝や、内側に向かって伸びて全体のバランスを崩す枝などを切り戻し、理想のシルエットを維持、あるいは創造していきます。
枝をどこで切るかによって、その後の樹形は大きく変わります。枝をよく見ると、葉の付け根の少し上などに、わずかに膨らんだ「節」のような部分があります。
これが「成長点」です。パキラは基本的に、この成長点の1〜2cm上で切ると、そこから新しい芽を力強く吹き出します。次にどちらの方向に枝を伸ばしたいかをイメージしながら切る場所を選ぶのが、上級者のテクニックです。
剪定に対して「かわいそう」と感じ、ためらってしまう方も少なくありません。ですが、植物にとって剪定は、健康を維持し、より力強く成長するための「健康診断」や「散髪」のようなものです。
特に生命力の強いパキラは、生育期であれば、思い切って切り戻しても、すぐに新しい芽で応えてくれます。失敗を恐れずにチャレンジしてみましょう!
剪定作業も、株への負担を最小限にするため、編み込みと同様に生育期の5月〜9月に行うのが基本です。作業には必ずアルコールなどで消毒した清潔なハサミを使い、切り口からの病気の感染リスクを徹底的に減らしましょう。
パキラの挿し木で編み込み後の管理とトラブル対処法
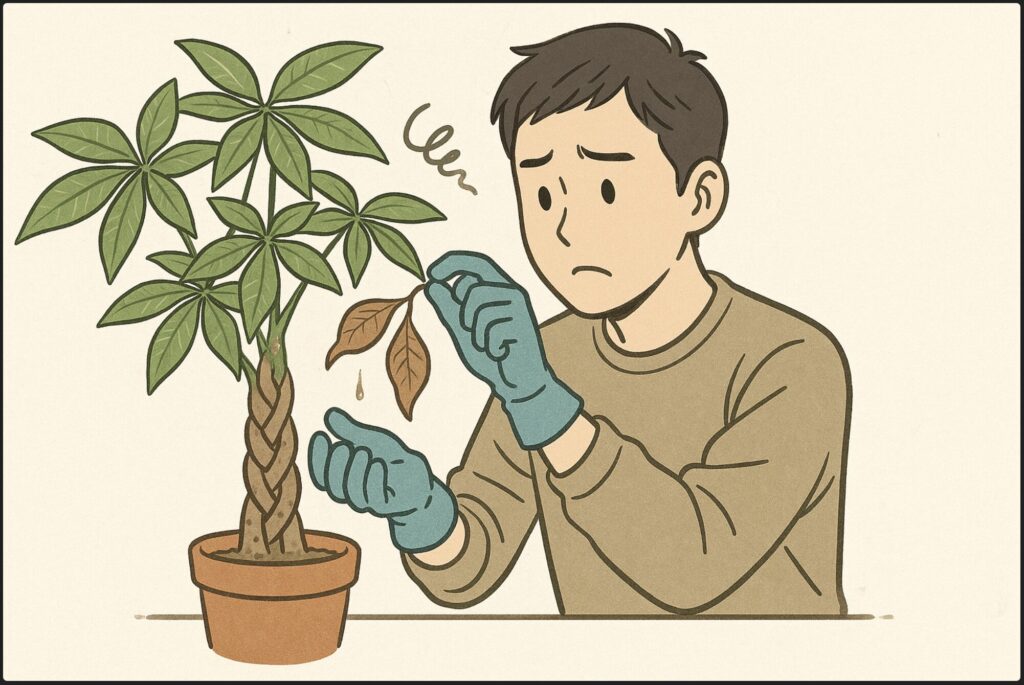
観葉スタイル・イメージ
参考
- 編み込みパキラは枯れやすい?主な原因
- 気になる編み込みパキラの寿命
- 編み込みパキラの切り戻し方法は?
- 成長後の仕立て直しはできる?
- 注意したい害虫とその対策
- パキラの挿し木と編み込みに挑戦しよう
編み込みパキラは枯れやすい?主な原因

観葉スタイル・イメージ
「編み込みパキラは管理が難しく、枯れやすい」という話を耳にしたことがあるかもしれません。この噂は半分本当で、半分は誤解です。単独で植えられたパキラに比べて、編み込みパキラ特有の、いくつかの枯れやすい要因を内包していることは事実です。
しかし、それらの原因を正しく理解し、適切な対策を講じれば、何年も元気に育てることが可能です。
主に注意すべき原因は、以下の4つのポイントに集約されます。
1. 幹同士の物理的な締め付け
編み込みパキラが成長し、それぞれの幹が太くなる過程で、編み込まれた部分がお互いを強く圧迫し合います。
この締め付けが限界を超えると、植物の血管ともいえる道管や師管が潰され、水や栄養の供給がストップしてしまいます。結果として、特定の幹だけが栄養失調に陥り、枯れてしまうのです。
対策:すべての基本は、編み込みの初期段階にあります。将来の成長を信じて、十分な余裕を持たせて「ゆるく」編むこと。これが最も効果的で、根本的な対策です。
2. 株元や葉の密集による蒸れ
複数の株が近距離で密集しているため、根元や葉が茂った部分の風通しが悪くなりがちです。空気の流れが滞ると湿度が高い状態が続き、土の表面にカビが発生したり、最悪の場合、根が呼吸困難に陥って腐ってしまう「根腐れ」を引き起こす原因となります。
対策:第一に、風通しの良い場所に置くこと。そして、定期的に鉢を回転させて、株全体に空気が当たるようにしましょう。水やり後に受け皿に溜まった水は、根腐れを誘発する最大の要因の一つなので、必ず毎回捨てる習慣をつけてください。
3. 水やり管理の難しさと根腐れ
株が複数あるため、鉢の中の土がどれくらいの速さで乾くのか、どれくらいの水量を必要としているのか、その見極めが単独の鉢植えよりも格段に難しくなります。
良かれと思って与えた水が過剰になり、根腐れに直結することは、編み込みパキラが枯れる最大の原因と言っても過言ではありません。
対策:「水やりは乾かし気味に」を徹底します。土の表面が乾いてから、さらに2〜3日、あるいはそれ以上待ってから水やりをするくらいで丁度良いことが多いです。季節や環境によりますが、土の中に指を第二関節まで入れてみて、中の湿り気を確認するアナログな方法が最も確実です。
4. 内部への日光不足
葉が立体的に密集するため、どうしても中心部や下の方にある葉には日光が届きにくくなります。植物にとって光はエネルギーの源です。光合成が十分にできない葉は、自ら栄養を作り出すことができず、やがて黄色く変色し、落葉してしまいます。
対策:定期的な剪定によって葉の量をコントロールし、株の内部まで光が差し込むように「透かし」てあげることが重要です。また、特定の方向からだけでなく、レースカーテン越しの明るい場所に置くなど、均一で優しい光を長時間当ててあげることが理想的な環境です。
愛情を込めて育てていても、編み込みのうち1本だけが枯れてしまうことはあります。その場合は、決して放置せず、早めに対処しましょう。枯れた幹は柔らかくなっているので、清潔なハサミで少しずつ切断しながら、生きている幹を傷つけないように慎重に取り除きます。
根元部分は無理に引き抜かず、次の植え替えの際に土の中から優しく抜き取ってあげれば大丈夫です。残った株は、少しスペースができますが、その分元気に育ちます。
気になる編み込みパキラの寿命
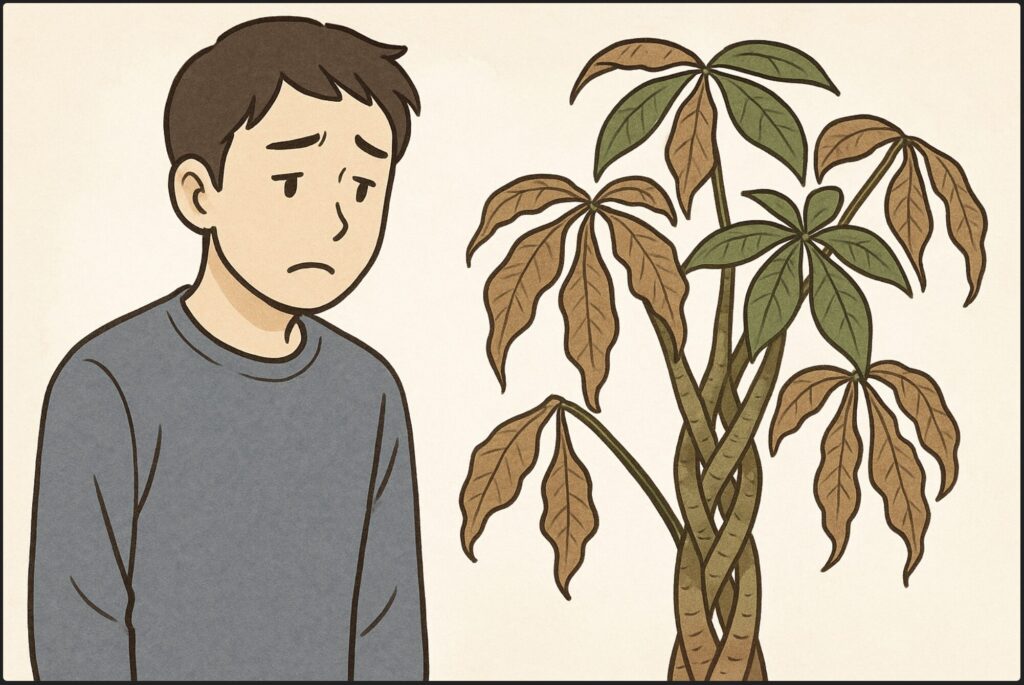
観葉スタイル・イメージ
パキラという植物そのものは、原産地では大木にまで成長するほど生命力が強く、非常に長寿な植物です。適切な環境で育てれば、文字通り一生を共に過ごすパートナーとなり得ます。
しかしながら、デザイン性の高い編み込みパキラの寿命は、単独で伸び伸びと育てられているパキラに比べて、残念ながら短くなる傾向があると言わざるを得ません。
その最大の理由は、これまで繰り返し述べてきたように、一つの鉢という限られた空間に複数の株が同居していることによる「慢性的なストレス」です。
- 根の生存競争:限られた土の中で、複数の株が水分や栄養を奪い合う状態が続きます。
- スペースの限界:根が伸びる物理的なスペースがすぐに限界に達し、「根詰まり」を起こしやすくなります。
- 物理的な圧迫:成長に伴う幹同士の締め付けは、植物にとって絶え間ない物理的ストレスです。
- 病気のリスク:蒸れやすい環境は、根腐れや病原菌の温床となり、一株の不調が全体に広がるリスクをはらんでいます。
これらの複合的な要因が、単独で育つ場合よりも株の老化を早め、寿命を縮める可能性があるのです。
ですが、これはあくまで「何もしなかった場合」の話です。少しがっかりさせてしまったかもしれませんが、ご安心ください。
適切なメンテナンスを愛情を持って続けることで、編み込みパキラも10年、15年と元気に育てることは十分可能ですよ。むしろ、そのひと手間が園芸の楽しさでもあります。
寿命を延ばし、末永く楽しむための秘訣
編み込みパキラの健康寿命を延ばし、末永くその美しい姿を楽しむためには、定期的な「健康診断」と「環境改善」が鍵となります。
- 毎年の植え替えという「リフレッシュ」:通常のパキラの植え替えは2〜3年に1度が目安ですが、根詰まりを起こしやすい編み込みパキラは、毎年春の生育期に、一回りだけ大きな鉢へ植え替えてあげるのが理想です。この時、固まった根鉢を優しくほぐし、古い土を落として新しい土に替えることで、根が伸びるスペースを確保し、土壌環境を劇的にリフレッシュできます。
- 戦略的な剪定による「健康管理」:成長に合わせて不要な枝葉を定期的に剪定することは、見た目を整えるだけでなく、風通しと日当たりを常に良好な状態に保つための重要な健康管理です。
- 熟練の水やり管理:根腐れは寿命を縮める最大の敵です。水のやりすぎには細心の注意を払い、常に「土が乾いてから、さらに数日待つ」という「乾かし気味」の管理を徹底するのが、長寿の最大のコツです。
日々の細やかな観察を怠らず、パキラが発する小さなサインに気づいてあげること。それが、手間をかけた分だけ生き生きとした姿で応えてくれるパキラとの、素晴らしい関係を築く第一歩です。
編み込みパキラの切り戻し方法は?

観葉スタイル・イメージ
「切り戻し」とは、伸びすぎたり、形が大きく乱れたりした枝や幹を、思い切って短く剪定することで、新しい芽の発生を促し、樹形を根本から再生させるパワフルな園芸テクニックです。
例えば、日照不足で間延びしてひょろひょろになった(徒長した)編み込みパキラや、上部だけが不格好に茂ってしまった場合などに、この切り戻しが非常に有効です。
切り戻しの手順と成功のポイント
切り戻しは株にとって大きな手術のようなものですから、必ず植物に十分な体力がある生育期の5月〜7月に行いましょう。基本的な手順と、成功させるためのポイントは以下の通りです。
- 理想の樹形を明確にイメージする:作業を始める前に、まず「どこまでの高さに切り戻したいか」「最終的にどのようなシルエットにしたいか」を具体的に、そして明確にイメージします。この完成図が、どこにハサミを入れるかのガイドラインになります。
- 「成長点」の少し上を狙って切る:次に、切るべき枝をよく観察し、葉の付け根などにある節の少し膨らんだ部分、すなわち「成長点」を探します。この成長点から新しい芽が力強く伸びてくるため、芽が出てほしい位置を正確に予測し、その1〜2cm上で切るのがセオリーです。
- 清潔で切れ味の良いハサミで一気に切る:アルコールで消毒した、切れ味抜群の剪定バサミを用意します。ためらわずに、一気にスパッと切断することが重要です。切れ味が悪いハサミで何度も切ると、切り口の細胞が潰れてしまい、その後の回復に悪影響を及ぼすことがあります。
- 手術後の丁寧なケア:切り戻し作業の後は、植物も体力を消耗しています。直射日光の当たらない、風通しの良い明るい場所で静かに休ませてあげましょう。新しい芽がしっかりと動き出すまでは、水の吸収量も減っているので、水やりは通常よりも控えめにし、土が完全に乾いてから与えるようにしてください。
パキラは非常に強健な植物ですが、一度にすべての葉を切り落として「丸坊主」の状態にしてしまうと、光合成を行う場所がなくなり、エネルギーを作り出せずにそのまま弱ってしまうことがあります。
株の安全を考えるなら、少なくとも数枚は健康な葉を残した状態で切り戻しを行うと、再生の成功率がぐっと高まります。
そして嬉しいことに、切り戻しで出た元気な枝は、そのまま健康な挿し穂として利用することができます。株を美しく再生させると同時に、新しい命を増やして次の編み込みに備えることもできるので、まさに一石二鳥の作業と言えるでしょう。
成長後の仕立て直しはできる?

観葉スタイル・イメージ
愛情を込めて育てている編み込みパキラが成長するにつれて、「少し形を変えたい」「もっと独創的なスタイルにしたい」と感じることもあるでしょう。
成長後の仕立て直しが可能かどうかは、そのパキラが「購入したもの」か「自分で若木から編み込んだもの」かによって、その自由度が大きく異なります。
購入した編み込みパキラの場合
園芸店などで販売されている完成品の編み込みパキラは、多くの場合、幹がある程度の太さにまで成長し、表面が硬い樹皮で覆われる「木質化」という状態になっています。さらに、長年編み込まれた幹同士が癒着していることも少なくありません。
そのため、一度この編み込みをほどいて、再度編み直す、というような根本的な仕立て直しは非常に困難です。無理に力を加えると、幹が音を立てて折れてしまう危険性が極めて高いでしょう。
しかし、アレンジの余地が全くないわけではありません。既存の編み込み幹の上部から新たに伸びてくる、まだ若く柔らかい枝葉を利用して、新しい表情を加えることは可能です。
- 伸びすぎた枝を定期的に剪定して、全体のフォルムをより引き締まったコンパクトな印象に整える。
- 数本の新しい枝を、優しくねじり合わせたり、三つ編みにしたりして、ビニールタイなどで軽く固定し、トップに新しいデザインポイントを作る。
このように、土台となる既存の編み込みはそのままに、上部のヘアスタイルを変えるような感覚でスタイリングを楽しむことができます。
自分で若木から編み込んだパキラの場合
若い実生苗からご自身の手で編み込みを始めた場合、その仕立て直しの可能性は無限に広がります。
パキラが元気に成長し、最初に編み込んだ部分から新しい幹がまっすぐに上に伸びてきたら、それこそが次のクリエイティブなステップの始まりです。その新しく伸びた、まだ柔らかい部分を、さらに編み足していくことができるのです。
この「成長と共に編み育てていく」というプロセスこそが、自作編み込みパキラの最大の醍醐味と言えるでしょう。
時間をかけて、少しずつ形を変え、時には思いもよらない美しいフォルムに育っていく様子は、まるで生きたアート作品を創造していくような、他では味わえない深い喜びを与えてくれます。
注意したい害虫とその対策

観葉スタイル・イメージ
編み込みパキラは、その構造上、どうしても株元や葉の密集部分の風通しが悪くなりがちです。この「空気がよどみやすい環境」は、残念ながら害虫にとって格好の住処となってしまいます。早期発見と適切な対策で、大切なパキラを害虫の被害から守りましょう。
水やりや葉のチェックの際に、以下のような症状が見られたら要注意です。葉や幹が光を反射してベタベタしていたり、白い綿のような塊や黒いすすのような汚れが付着していたりしたら、それは害虫が発生しているサインです。
また、なぜかアリが幹を頻繁に行き来している場合も、害虫が出す甘い排泄物に集まっている可能性が高いです。
代表的な害虫と具体的な対処法
パキラに発生しやすい代表的な害虫と、その効果的な対処法を知っておきましょう。
| 害虫の種類 | 特徴と被害 | 効果的な対処法 |
|---|---|---|
| カイガラムシ | 白や茶色の硬い殻や綿に覆われた虫。植物の汁を吸って生育を阻害し、排泄物が「すす病」を誘発する。成虫は殻で守られ薬剤が効きにくい。 | 幼虫のうちなら薬剤が有効。成虫は数が少なければ、歯ブラシやティッシュ、ヘラなどで物理的にこすり落とすのが最も確実です。 |
| ハダニ | 0.5mm程度と非常に小さく、主に葉の裏に寄生し汁を吸う。被害が進むと葉がかすれたように白っぽくなる。高温乾燥を好む。 | 水に非常に弱いため、定期的な葉水(葉の裏までしっかり濡らす)が最高の予防になります。発生してしまった場合は、シャワーで洗い流すか、専用の薬剤を散布します。 |
| アブラムシ | 新芽や若葉などの柔らかい部分に集団で発生し、汁を吸う。ウイルス病を媒介することもある。 | 数が少なければ、粘着テープで貼り付けて取るか、手で潰します。大量発生した場合は、牛乳をスプレーして窒息させる方法や、市販の薬剤が有効です。 |
最大の対策は「予防」にあり
害虫対策で最も効果的かつ重要なのは、そもそも害虫が発生しにくい、あるいは住み着きにくい環境を作ることです。日頃から以下の3点を心がけるだけで、リスクを大幅に減らすことができます。
- 風通しの確保:全ての基本です。空気がよどむ場所に置かない、定期的に鉢の向きを変える、剪定で風の通り道を作る、といった対策で湿度をコントロールします。
- 定期的な葉水:葉の表裏に霧吹きで水をかける習慣は、ハダニの予防に絶大な効果を発揮します。また、葉の表面のホコリを洗い流し、植物の呼吸を助けると共に、害虫が付きにくい清潔な状態を保てます。
- 日々の観察眼:水やりのついでで構いません。葉の裏や新芽、幹の付け根などを「ちらっと見る」習慣をつけましょう。どんな害虫も、初期段階で発見できれば被害は最小限に抑えられます。
もし害虫が大量に発生してしまった場合は、他の植物への感染を防ぐためにも、まずは被害株を隔離しましょう。その上で、状況に応じて適切な薬剤を使用することを検討してください。
園芸薬品メーカーのウェブサイト(例:KINCHO園芸「病害虫ナビ」)などで、症状から害虫を特定し、効果のある薬剤を調べることができます。
パキラの挿し木と編み込みに挑戦しよう
この記事では、オリジナルの編み込みパキラを自らの手で作り上げるための、挿し木から編み込みまでの具体的な手順、そしてその後の日々の管理方法や予期せぬトラブルへの対処法について、深く掘り下げて解説しました。
最後に、この挑戦を成功に導くための重要なポイントをリストで振り返ります。
最初は少し難しく感じるかもしれませんが、この記事で得た知識を元に、一つひとつのステップを愛情を持って丁寧に行えば、きっとあなただけの特別な編み込みパキラを育て上げることができるはずです。
生命の成長を間近で感じながら、自分だけのアート作品を創造する喜びを、ぜひ味わってみてください。
チェックリスト
- 編み込みパキラは正しい知識と手順を踏めば誰でも自作できる
- 成功の鍵は幹が若く柔らかい「実生苗」を選ぶこと
- 作業は株の回復力が最も高い生育期の5月〜7月が絶対条件
- 挿し木が発根するまでの目安は約10日から2週間
- 編み込む際は将来の幹の成長を見越して「ゆるく」が最大のコツ
- 適切な剪定は美しい樹形の維持と株の健康に不可欠
- 編み込みパキラは単独株より枯れやすい特有の要因を持つ
- 主な枯れる原因は「幹の締め付け」「株の蒸れ」「根腐れ」「日光不足」
- 寿命は日々の丁寧な管理、特に毎年の植え替えで延ばすことが可能
- 伸びすぎた樹形は「切り戻し」というテクニックで劇的に再生できる
- 購入品の編み直しは困難だが、伸びた枝でのアレンジは楽しめる
- 害虫対策は治療よりも「予防」が最も重要
- 日々の「風通し」と「葉水」が最高の予防策になる
- トラブルが起きても原因を正しく知れば慌てずに対処できる
- 手間と時間をかけた分だけ、世界に一つだけの愛着ある一鉢になる
