
観葉スタイル・イメージ
育てているドラセナがひょろひょろになってしまい、お困りではありませんか。購入した時はあんなに元気で、幹もしっかりしていたのに、いつの間にか茎が細いまま上へ上へと伸びすぎて、まるで別の植物のようになってしまった…と、どうすればよいか悩んでしまう方も多いようです。
ドラセナがひょろひょろになる主な原因は、日照不足や水やりの頻度、置き場所といった日々の管理方法が、ドラセナ本来の性質と合っていないことにあるかもしれません。
この記事では、初心者向けに、ドラセナがひょろひょろになってしまう根本的な原因と、元気な姿に戻すための具体的な対策を、専門的な視点から詳しく解説します。
季節に合わせたお手入れの方法から、思い切って幹を切る剪定の正しい手順、どうすれば新芽がうまく出てくれるのか、そして多くの人が悩む「幹を太くする」ためのコツまで、網羅的にご紹介します。
ポイント
- ドラセナがひょろひょろになる主な原因
- 元気な姿に戻すための剪定(切り戻し)の手順
- 剪定後に新芽をうまく出させるコツ
- 日々の管理で幹を太くし、徒長を防ぐ方法
コンテンツ
ドラセナがひょろひょろになる原因
参考
- 茎が細いのは日照不足が原因
- 室内での基本的な管理方法
- 適切な水やりの頻度とは
- 初心者向けの育て方のコツ
- 作業に適した季節と時期
茎が細いのは日照不足が原因

観葉スタイル・イメージ
ドラセナがひょろひょろと力なく伸びてしまう最大の原因は、「日照不足」です。この現象は「徒長(とちょう)」と呼ばれ、植物が光を求めて必死に伸びているサインに他なりません。
植物は光合成によって生きるためのエネルギーを作り出します。室内の暗い場所に長期間置かれていると、ドラセナは少しでも多くの光を浴びようとして、茎や枝が間延びしたように不自然に伸びてしまいます。
これは、植物ホルモンの一種である「オーキシン」が、光の当たらない側に多く集まり、細胞の伸長を促進するために起こる現象です。
光合成が十分に行えないため、エネルギー不足に陥り、以下のような二次的な問題も発生します。
- 新しく出てくる葉が小さくなる。
- 葉の色が薄くなり、健康的な濃い緑色を失う。
- 茎が細く軟弱になり、葉の重みを支えきれなくなる。
- 病気や害虫に対する抵抗力が低下する。
「耐陰性」と「日当たりを好む」は違います
ドラセナは「日陰でも育つ(耐陰性がある)」観葉植物として販売されていることが多いです。しかし、これは「暗い場所でもすぐに枯れることはない」という意味であり、本来は明るい光を好む植物です。
ドラセナの多くの品種は、熱帯アフリカなどの日当たりの良い場所に自生しています。そのため、健康的に、幹をしっかりさせて育てるためには、一定量の日光が不可欠なのです。
室内での基本的な管理方法

観葉スタイル・イメージ
ドラセナのひょろひょろ(徒長)を防ぎ、健康な状態を維持するためには、「置き場所」、「温度・湿度」、そして「風通し」の3つの要素が非常に重要です。
置き場所
室内で管理する場合、レースカーテン越しの柔らかい光がコンスタントに当たる、明るい窓際が最も理想的な場所です。光が強すぎると葉が焼けてしまうため、直射日光が当たらないよう調整することがポイントです。
もし、玄関や北向きの部屋など、どうしても暗い場所に置きたい場合は、以下のような工夫が必要になります。
- ローテーション:1週間のうち数日は明るいリビングなどに移動させ、光合成をさせてあげる。
- 植物育成ライト:光量を補うために、市販の植物育成ライト(LEDライトなど)を導入する。
温度と風通し
ドラセナは極端な乾燥と急激な温度変化を嫌います。エアコンの暖房や冷房の風が直接当たる場所は、人間が快適でも植物にとっては過酷な環境です。急激な乾燥で葉が傷み、水分を失ってしまうため、必ず避けるようにしましょう。
また、空気の流れが滞る場所では、土が乾きにくく根腐れの原因になったり、ホコリが溜まって害虫(特にハダニやカイガラムシ)が発生しやすくなったりします。窓を開けて換気する、サーキュレーターで空気を循環させるなど、適度な風通しを確保することも病害虫予防の観点から重要です。
さらに、多くの品種は寒さに弱いです。大手園芸メーカーの情報によれば、多くの観葉植物は冬場でも最低5℃〜10℃以上の室温を保つことが推奨されています。(参照:株式会社ハイポネックスジャパン「冬の観葉植物、枯らさずに管理するコツは?」)
特に夜間は窓際が外気で急激に冷え込むため、部屋の中央に鉢を移動させたり、段ボールや発泡スチロールで鉢の周りを囲ったりする防寒対策も有効です。
- 最適:レースカーテン越しの明るい窓際
- 次善:暗い場所+週数回の移動、または植物育成ライトの活用
- NG:エアコンの風が直撃する場所
- NG:直射日光(特に夏)や、冬場に5℃以下になる寒すぎる場所
適切な水やりの頻度とは

観葉スタイル・イメージ
水やりは、観葉植物管理の中で最も奥深く、失敗しやすいポイントです。特にドラセナは、「季節に合わせたメリハリ」が最も大切になります。
ドラセナは、土が常にジメジメと湿った状態を極端に嫌います。水のやりすぎは土の中の酸素が不足する状態を招き、「根腐れ」を引き起こします。
根が呼吸できずに窒息し、腐敗してしまうと、もう水分や養分を吸い上げることができなくなり、葉が垂れたり枯れたりします。これは、ドラセナが枯れる原因の第一位とも言われるほどです。
一方で、水が不足しすぎても、葉の先端から枯れこんだり、葉全体が力なく垂れ下がったりします。季節ごとの水やりの目安を正しく理解することが、健康な株を育てる鍵となります。
水やりの基本中の基本は、「土の表面が乾いたのを(指で触って)確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。そして、受け皿に溜まった水は雑菌の繁殖や根腐れの原因になるため、必ずすぐに捨てること。このメリハリが根を健康に保ちます。
| 季節 | 水やりの目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 春・秋 (生育期) | 土の表面が乾いたら、たっぷりと与える。(目安:1〜2週間に1回程度) | 生育が活発になる時期です。土の乾き具合をしっかり指で触って確認しましょう。肥料もこの時期に与えます。 |
| 夏(生育期) | 土の表面が乾いたら、すぐに与える。(目安:週に1〜2回程度) | 最も水切れしやすい季節です。ただし、日中の高温時は鉢内が蒸れるため避け、朝夕の涼しい時間帯に水やりをしてください。 |
| 冬(休眠期) | 土が乾いてから、さらに2〜3日(または4〜5日)空けてから与える。(目安:2〜3週間に1回程度) | 乾燥気味に管理することが最大のコツです。水のやりすぎは根腐れに直結します。暖かい日の日中に、水道水そのままではなく、常温に戻した水を与えるのが理想です。 |
「葉水(はみず)」も非常に効果的です
水やりとは別に、霧吹きなどで葉に直接水をかける「葉水」は、植物にとって多くのメリットがあります。エアコンで乾燥しがちな室内では、空中湿度を保つことで葉の乾燥を防げます。
また、ハダニなどの害虫は乾燥した環境を好むため、葉水は害虫予防にも高い効果を発揮します。 ただし、日中の直射日光が当たる時間帯に行うと、水滴がレンズ代わりになって葉焼けすることがあるため、朝夕や曇りの日に行うとよいでしょう。
初心者向けの育て方のコツ
ドラセナを元気に育てる最大のコツは、教科書通りのスケジュールを守ることではなく、「目の前にある植物の状態をよく観察すること」に尽きます。
難しく考える必要はありません。まずは、「土を指で触ってみる」習慣をつけましょう。園芸のプロは必ず土に指を入れます。表面が乾いて見えても、指を第二関節(約2〜3cm)まで入れてみると、中はまだ湿っていることがよくあります。この状態で水を与えると過湿(根腐れ)の原因になります。
また、葉や幹の状態も健康のバロメーターです。植物は言葉を話せませんが、様々なサインを出しています。
- 葉が力なく垂れ下がっている→水不足の典型的なサインです。土を確認し、乾いていればすぐに水を与えてください。(根腐れで水を吸えない場合も同じ症状が出ます)
- 葉先が茶色く枯れてきた→根詰まり(鉢の中で根がパンパンになっている)、空気の乾燥、葉焼け、肥料のやりすぎなど、様々な原因が考えられます。
- 葉の色が薄くなってきた→日照不足による光合成不足のサインです。より明るい場所への移動を検討しましょう。
- 鉢底から根が飛び出している→「根詰まり」のサインです。次の生育期に一回り大きな鉢への植え替えが必要です。
このように、植物が出す小さなサインに早めに気づき、対処することが、ひょろひょろになるのを防ぐ第一歩となります。
作業に適した季節と時期
もし、ドラセナがひょろひょろになってしまい、仕立て直し(剪定)や、鉢がパンパンになった「根詰まり」を解消するための植え替えを考える場合、作業に適した「時期」を厳守することが非常に重要です。
これは、植物が人間の手術を受けるのとまったく同じで、株の体力が万全な「ベストな時期」を選ぶことが、成功率を左右し、その後の回復スピードを決定づけるからです。
最適な時期は、植物の生育期にあたる5月〜7月頃です。この時期は、ドラセナの生命力が年間で最も高まるタイミングです。
生育期(5月〜7月)が最適な理由
- 気温の安定:最低気温が15℃以上で安定し、植物の成長ホルモンの分泌が最も活発になります。
- 回復力の高さ:剪定で幹を切っても、切り口から新芽が素早く出てくる回復力があります。
- 発根の速さ:植え替えで根を整理したり、多少傷つけたりしても、新しい根を出すスピードが速く、株が弱りにくいです。
特に、日本の気候で言えば「梅雨」の時期(6月頃)は、高温多湿で空中湿度が高く保たれるため、剪定後の切り口の乾燥を防ぎ、同時に「挿し木」の成功率も格段に上げてくれるボーナスタイムとも言えます。
真夏(8月)の作業は避けるのが無難
8月も暦の上では生育期ですが、気温が35℃を超えるような「猛暑日」が続く時期は、植物にとっても過酷な環境です。
人間が夏バテするように、植物も高温下では成長を一時的に緩め、体力を消耗しています。この時期の剪定や植え替えは、かえって回復を遅らせる可能性があるため、猛暑が始まる前の7月中旬まで、もしくは暑さが和らぐ9月中旬以降(気温が30℃を下回ってから)に行うのが賢明です。
冬場の剪定・植え替えは厳禁です
ひょろひょろな姿が冬の間ずっと気になっていたとしても、絶対に冬場(一般的に最低気温が10℃〜15℃を下回る10月下旬〜4月頃)に剪定や植え替えを行わないでください。
冬のドラセナは「休眠期」に入り、成長を完全に止めています。この状態は、エネルギーを消費せず、春までじっと耐える「冬眠」のようなものです。
この時期に幹を切ったり、根をいじったりする行為は、回復する力(エネルギー)が全くない状態で植物に大怪我をさせるのと同じです。切り口から雑菌が入って幹が腐り込んだり(枯れ込み)、植え替えのストレスに耐えきれず、春を待たずに枯れてしまうリスクが非常に高くなります。
どんなに姿が気になっても、必ず春になり、新芽が動き出すエネルギーに満ちた時期まで待ちましょう。
ドラセナのひょろひょろを仕立て直す
参考
- 伸びすぎた枝の対処法
- 剪定(切り戻し)のやり方
- 幹を切る位置と高さの目安
- 剪定後の新芽を吹かせるコツ
- 幹を太くする方法はある?
伸びすぎた枝の対処法
すでにひょろひょろと伸びすぎてしまったドラセナを見て、「なんとか元のずんぐりとした姿に戻したい」と考える方も多いかもしれません。しかし、残念ながら、一度「徒長(とちょう)」によって間延びしてしまった茎を、元の状態に戻す魔法のような方法はありません。
植物の茎は、成長するにつれて細胞壁がリグニンという物質で固まり、「木質化(もくしつか)」していきます。一度木質化して固まった茎は、その後にどれだけ日光に当てても、縮んだり太くなったりすることはなく、形は元に戻らないのです(これは不可逆的な変化です)。
支柱を立てるのは根本解決にはなりません
伸びすぎて倒れそうになった茎を「支柱」で支える方法もあります。これは、見た目を整え、折れるのを防ぐ一時的な対処法としては有効です。しかし、植物の徒長という根本的な問題は解決しておらず、上部はさらに光を求めてひょろひょろと伸び続けてしまいます。
このため、伸びすぎたドラセナの見た目をリセットし、再び元気でバランスの取れた姿に再生させるための最も効果的かつ唯一の対処法が「剪定(せんてい)」、一般に「切り戻し」と呼ばれる作業です。
「切り戻し」とは?
「幹を切る」と聞くと、「枯れてしまったらどうしよう」と勇気がいる行為に感じるかもしれません。しかし、ドラセナは観葉植物の中でもトップクラスの生命力と再生能力を持っており、非常に剪定に強い植物です。
その理由は、幹のあちこちに「成長点(せいちょうてん)」と呼ばれる、新芽になる準備をしている組織を無数に隠し持っているためです。幹の途中で切られても、その刺激がスイッチとなり、切り口の少し下にある成長点が目覚め、新しい芽(新芽)が2〜3本(時にはそれ以上)出てくる性質があります。
剪定(切り戻し)の主なメリット
- 樹形のリセット:ひょろひょろと伸びすぎた部分を取り除き、高さをリセットできる。
- ボリュームアップ:1本だった幹が剪定後に複数に枝分かれするため、葉の数が増え、こんもりとした茂った姿になる。
- 株の再生(挿し木):切り取った上部(葉が付いている側)は、「挿し木」として利用でき、新しい株として増やすことが可能。
このドラセナの強い再生能力を利用し、あえて幹を好みの高さで切り、低い位置から新しい芽を複数出させて、株全体を若返らせ、仕立て直すことこそが「切り戻し」の最大の目的なのです。
剪定(切り戻し)のやり方
のやり方.jpg)
観葉スタイル・イメージ
剪定(切り戻し)の成功の鍵は、生育期に行うことはもちろん、「清潔な道具で思い切って切る」ことです。
準備するもの
- よく切れる清潔な剪定バサミ:必須アイテムです。切れ味が悪いハサミは、幹の細胞(道管や師管)を潰してしまい、そこから枯れ込む原因になります。また、他の植物に使ったハサミをそのまま使うと、病原菌を移してしまう可能性があります。使用前にアルコール(消毒用エタノール)で刃先を拭くか、ライターの火で炙る(熱湯消毒する)など、必ず消毒してから使いましょう。
- 癒合剤(ゆごうざい):(推奨)太い幹を切った場合、切り口を保護するための薬剤(ペースト状のものが多い)です。無くてもドラセナは回復しますが、あると安心です。大手園芸薬品メーカーの製品情報にもあるように、切り口からの水分の蒸発を防ぎ、雨水や雑菌の侵入をブロックする役割があります。(参照:KINCHO園芸「トップジンMペースト」)
剪定の手順
手順
1.まず、枯れた葉や明らかに弱っている枝、変色した葉を取り除き、株全体を整理します。
2 次の「幹を切る位置と高さの目安」を参考に、仕立て直したい高さを決めます。複数の幹がある場合は、高低差をつけると自然な仕上がりになります。
3.決めた位置で、幹を水平にスパッと一気にカットします。ためらって何度も切りつけると、切り口が汚くなり、回復が遅れる原因になります。
4.(推奨)切り口から樹液が出てくる場合はティッシュなどで軽く拭き取り、切り口が少し乾いたら、癒合剤を指やヘラで隙間なく塗り込みます。
切った枝は「挿し木」に挑戦できます
剪定でカットした上の部分(葉が付いている方)は、「挿し木」として再利用できます。生命力が強いため、初心者でも成功しやすいです。 切った枝を10〜15cm程度の長さに切り分け、上部の葉を2〜3枚残して他は取り除きます(葉が大きい場合は、蒸散を防ぐために半分にカットします)。
切り口を水に数時間つけた後、清潔な挿し木用の土(赤玉土やバーミキュライトなど)に挿しておくと、数週間〜数ヶ月で根が出て新しい株として育てられます。水挿し(水を入れたコップに入れておく)でも発根することがあります。
幹を切る位置と高さの目安
剪定で最も悩むのが「どこで切るか」ですが、目安は非常にシンプルです。
新芽は、「切った場所のすぐ下」にある「成長点」から出てきます。ドラセナの幹をよく見ると、葉が落ちた跡が「節(ふし)」としてリング状に残っていたり、小さなポツポツとした膨らみ(これが成長点)が見えたりします。
幹が切られると、その刺激で最も切り口に近い位置にある、元気な成長点が動き出す仕組みです。多くの場合、1箇所ではなく2〜3箇所の成長点が動き出し、複数の新芽が出てきます。
このため、コツは「新芽が出た後の完成形をイメージして高さを決める」ことです。
例えば、床から約30cmの高さでこんもりとさせたい場合は、30cmよりも少し上(例:35cm)の位置でカットします。そうすることで、30cm付近から複数の新芽が横に展開し、以前よりもボリュームのある理想の樹形に近づきます。
切る位置の目安:節(ふし)の少し上
幹をよく見ると、葉が落ちた跡が「節(ふし)」として残っています。新芽はこの節のあたりから出やすいため、節の5mm〜1cmほど上で切るのが最も理想的とされています。
ただし、ドラセナは非常に強いため、特に節が見当たらなくても、好みの高さで切れば問題なく新芽は出てきますので、あまり神経質になる必要はありません。
剪定後の新芽を吹かせるコツ
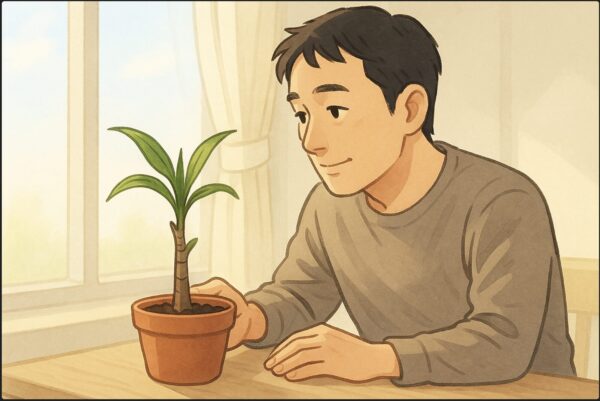
観葉スタイル・イメージ
剪定(切り戻し)は、植物にとって体の一部を失う大手術であり、大きなストレスがかかる行為です。いわば「集中治療室」に入ったような状態です。この術後のケアが、新芽がうまく出るかどうか、そして株全体が回復できるかを左右します。
植物は今、「傷口の治癒」と「新しい芽の形成」という2つの重いタスクを同時にこなそうとしています。このデリケートな時期を乗り切らせる最大のコツは、矛盾するように聞こえますが「新芽を出すためのエネルギー(光)は必要、しかし根からの水分(水)は不要」という状態を理解することです。
具体的には、「置き場所」「水やり」「肥料」の3つの管理が鍵となります。
1.置き場所:新芽を出すエネルギー(光)の確保
剪定後の株は、新芽を出すために膨大なエネルギーを必要とします。葉がなくなった今、そのエネルギーは幹や根に蓄えられた養分と、幹自体が行うわずかな光合成によって作られます。
そのため、剪定前よりも少し明るい場所に置いてください。「光が当たる」という刺激が、休眠していた成長点を目覚めさせるスイッチの役割も果たします。
ただし、この「明るい場所」には注意が必要です。
- 最適:レースカーテン越しの柔らかい光が当たる窓辺。
- NG(弱る):暗すぎる部屋。エネルギーが作れず、新芽が出るきっかけも掴めません。
- NG(枯れる):直射日光。デリケートな幹が日焼け(幹焼け)を起こし、致命的なダメージを受けます。
「風通し」も切り口の治癒に重要です
もう一つのポイントが「風通し」です。空気が全く動かないジメジメした場所に置くと、剪定した切り口が乾かず、そこからカビが生えたり、雑菌が入って腐敗したりする(枯れ込む)原因になります。空気が緩やかに循環する、風通しの良いリビングなどが適しています。
2.水やり:徹底した「乾燥管理」が成功の鍵
これが剪定後の管理で最も重要であり、最も失敗しやすいポイントです。
結論から言うと、新芽がしっかり展開して葉を開くまでは、水やりは「徹底的に控える」ことが成功の最大のコツです。
なぜ水やりを控えるのか?葉がない=水分が消費されない
植物は、根から吸い上げた水の9割以上を、葉の裏にある「気孔(きこう)」から蒸散(じょうさん)させて消費しています。剪定で葉をすべて失うと、植物は水を消費する「口」を失ったことになります。
それなのに今まで通り水を与えると、土は全く乾かず、常に湿った状態が続きます。すると、土の中の酸素がなくなり、根が呼吸できずに窒息し、腐ってしまいます。これが「根腐れ」です。
剪定後の失敗で最も多いのが、この「かわいそうだから」という親切心の水のやりすぎによる根腐れです。
新芽が動き出すまでは、土が完全に乾いてから、さらに数日待つくらい、徹底的に乾燥気味に管理してください。目安としては、普段の倍以上の間隔を空けるイメージです。
鉢が乾いたかどうかわからない場合は、以下の方法で確認できます。
- 鉢を持ち上げる:水を含んだ鉢は重いです。持ち上げてみて「軽い」と感じたら乾いています。
- 水分計を使う:市販の水分計(サスティなど)を挿しておくと、内部の乾き具合が色でわかります。
- 竹串を挿す:鉢の底まで竹串を挿し、数分後に抜いてみて、土がついてこなければ乾いています。
水やりを控える代わりに、霧吹きで幹全体や土の表面を湿らせる「葉水(この場合は幹水)」をこまめに行うのは非常に有効です。これは土を過湿にすることなく、株の乾燥を防ぎ、空中湿度を保つのに役立ちます。
3.肥料:新芽が育つまで「絶対NG」
剪定後の弱った株に肥料を与えるのは、手術直後で点滴を受けている患者に、無理やりステーキを食べさせるようなものです。
弱った根は肥料成分を吸収する力がないため、土の中に使われない肥料分(塩類)が溜まっていきます。
すると、浸透圧の差で逆に根から水分が奪われてしまい、根が傷んでしまいます。これは「肥料焼け」と呼ばれ、根に深刻なダメージを与えます。(参照:株式会社ハイポネックスジャパン「もっと知りたい肥料! vol4 肥料やけってなに?」)
肥料は、新芽がしっかり展開し、新しい葉が3〜4枚開いて「光合成を再開したな」と確認できてから、薄めた液体肥料から与え始めてください。
活力剤(メネデールなど)は使っても良い?
肥料(チッソ・リンサン・カリ)とは異なり、「活力剤(かつりょくざい)」は植物のストレス軽減や発根を促すためのものです。
これは「食事」ではなく「ビタミン剤」や「点滴」に近いため、剪定直後から使用しても問題ありません。必須ではありませんが、水やりの代わりにごく薄めた活力剤を霧吹きで幹に与えるのは、回復を助ける一つの方法です。
幹を太くする方法はある?

観葉スタイル・イメージ
ひょろひょろのドラセナを見て、「この細い幹を後から太くしたい」と考える方は非常に多いですが、残念ながら「一度細く育った(木質化した)幹を、後から急激に太くするのは非常に困難」です。
特にドラセナ・コンシンネ(レインボーなど)は、その品種の特性として、元々幹が太くなりにくい(細くしなやかに伸びる)性質を持っています。
残念ながら、細い幹を数ヶ月で丸太のように太くする魔法のような方法はありません。ですが、今後の管理次第で、幹を「硬く締まった丈夫な状態」に育てたり、将来的に新しく出てくる部分を太く育てたりすることは可能です。
①日光と風に当てる(最も重要)
幹を太く(丈夫に)するためには、何よりも十分な光合成が必要です。室内でもできるだけ明るい場所で管理し、エネルギーを最大限作らせることが基本です。
もし可能であれば、春から秋にかけては屋外の半日陰(直射日光が絶対当たらない明るい場所)で管理するのも一つの方法です。適度な風に当たることで、植物は倒れまいとして幹を硬く、丈夫にしていきます。
ただし、急に室外に出すと葉焼けするため、最初は日陰から、徐々に明るい場所へ移す「慣らし運転」が必要です。
②肥料を適切に与える
植物が成長するためには栄養が必要です。生育期(春・秋)に、観葉植物用の緩効性肥料(置き肥)や、液体肥料を規定通りに与えることで、株全体の成長が促進されます。
肥料には「三要素」と呼ばれるチッソ(N)・リンサン(P)・カリ(K)があります。
園芸メーカーの解説によれば、チッソ(N)は「葉肥え」で葉を大きくし、リンサン(P)は「花肥え」、カリ(K)は「根肥え」と呼ばれ、根や幹を丈夫にする働きがあるとされています。(参照:株式会社ハイポネックスジャパン「肥料の基礎知識」)
バランスの取れた肥料を与え、株全体を健康に育てることが、結果的に幹をしっかりさせることに繋がります。
③剪定を繰り返す
これは長期的な方法ですが、剪定で枝分かれさせると、その分の葉を支えるために、根元の幹が徐々に太くなろうとします。ひょろひょろに伸び切ってしまう前に、早め早めに剪定(摘心)し、枝数を増やしていくことも、将来的に幹を太く育てるための一つの技術です。
ドラセナのひょろひょろを防ぐ方法のまとめ
最後にこの記事の要点をリストでまとめます。ひょろひょろを防ぎ、元気なドラセナを育てるための参考にしてください。
チェックリスト
- ひょろひょろの最大の原因は「日照不足」
- ドラセナは暗い場所に耐えられるが、本来は明るい場所が好き
- 室内ではレースカーテン越しの窓際が最適
- エアコンの風が直接当たる場所は避ける
- 水やりは「土が乾いたらたっぷり」が基本
- 水のやりすぎは根腐れの原因になるため注意
- 冬は水やりの回数を減らし、乾燥気味に管理する
- 葉水は乾燥や害虫の予防に効果的
- 剪定や植え替えは、生育期の5月〜7月に行う
- 冬場の剪定や植え替えは避ける
- 一度ひょろひょろに伸びた幹は元に戻らない
- 仕立て直しは「剪定(切り戻し)」が唯一の方法
- 剪定は清潔なハサミで、新芽が欲しい位置の少し上を切る
- 剪定後は「明るい場所」で「水やりを控えて」管理する
- 幹を後から太くするのは難しいが、日照と肥料で丈夫にはなる
