
観葉スタイル・イメージ
ポトスは耐陰性があり、室内で育てやすい観葉植物として人気です。しかし、「本当に日陰でも育つのか」「暗い部屋に置いたら枯れてしまった」といった疑問や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実際、ポトスの耐陰性には品種による違いがあり、暗い場所に適した育て方にはいくつかのコツが必要です。元気な苗の選び方から、季節ごとの管理、育ちすぎた際の摘芯、植え替えのタイミングまで、知っておくべきポイントは多岐にわたります。
また、日陰で育てるからこそ注意したい病気や害虫の対策、万が一の地植えの可能性についても気になるところです。この記事では、ポトスの耐陰性に関するあらゆる疑問に答え、日陰でも元気に育てるための具体的な方法を詳しく解説します。
ポイント
- ポトスの耐陰性の具体的なレベル
- 暗い場所に向いている品種の見分け方
- 日陰でポトスを育てる際の管理方法
- 暗所で発生しやすいトラブルと対策
コンテンツ
ポトスの耐陰性を活かす育て方
参考
- 耐陰性に差がつく品種の選び方
- 元気なポトスの苗を選ぶポイント
- 基本の育て方と置き場所
- 季節ごとの水やりと管理方法
- 根詰まりを防ぐ植え替えの時期
耐陰性に差がつく品種の選び方

観葉スタイル・イメージ
ポトスは「耐陰性がある」観葉植物として広く知られていますが、この言葉は「暗くても元気に成長する」という意味ではありません。実はすべての品種が同じように暗さに強いわけではなく、品種の特性を理解することが、日陰でポトSスを育てるための重要な最初のステップとなります。
ポトスの耐陰性は、葉に含まれる「葉緑素(クロロフィル)」の量と深く関係しています。
葉緑素は、植物が光のエネルギーを使って水と二酸化炭素から養分(糖)を作り出す「光合成」を行うための場所です。この葉緑素の量が多いほど、少ない光でも効率よくエネルギーを生産できるため、暗い環境への耐性が強くなります。
葉の「斑(ふ)」の量で判断する
最も簡単な見分け方は、葉の模様、つまり「斑(ふ)」の量や色です。
- 緑一色の品種(例:ポトス・パーフェクトグリーン)
葉全体が濃い緑色の品種は、葉のほぼ全体に葉緑素を持っています。そのため、ポトスの中で最も耐陰性が強く、オフィスや北向きの部屋など、日照が限られる場所でも比較的健康を維持しやすいです。 - 斑入り品種(例:ゴールデンポトス、ポトス・エンジョイ)
最も一般的なゴールデンポトスは、緑色の葉に黄色の斑が入ります。ポトス・エンジョイは白に近い斑が特徴です。これらの斑の部分には葉緑素がほとんど、あるいは全く含まれていません。そのため、緑一色の品種と比べると光合成の効率が下がり、耐陰性はやや劣ります。暗すぎると斑が減ることもあります。 - 白斑が多い品種(例:ポトス・マーブルクイーン)
葉の白い部分の割合が非常に多い品種は、見た目が涼しげで美しい一方、葉緑素の量が極端に少なくなります。これらの品種は耐陰性が弱く、十分な光(レースカーテン越しの明るい光など)を必要とします。暗い場所に置くと、生育不良を起こしたり、葉の白さを保てなくなったりしやすいです。
| 耐陰性の強さ | 特徴 | 代表的な品種 |
|---|---|---|
| 強い | 葉が緑一色で、葉緑素が豊富。 | ポトス・パーフェクトグリーン |
| 普通 | 黄色の斑が入り、最も一般的。 | ゴールデンポトス |
| 普通〜やや弱め | 白や淡黄色の斑がはっきり入る。 | ポトス・エンジョイ、ポトス・ステータス |
| 弱い | 葉の白い部分(白斑)が多く、光合成の効率が低い。 | ポトス・マーブルクイーン、ポトス・テルノ スノービー |
「先祖返り」とは?
斑入りの品種を暗い場所に長く置くと、新しく出てくる葉の斑が少なくなり、緑色の部分が増えることがあります。
これを「先祖返り」と呼びます。これは、植物が光合成の効率を上げようとして、葉緑素をより多く作ろうとする生存本能によるものです。一度緑色に戻った葉は、明るい場所に戻しても元の斑入りには戻りません。
「耐陰性」=「暗くても育つ」ではない
ポトスは本来、熱帯雨林で木漏れ日を浴びて育つ植物であり、日光を好みます。
耐陰性があるとは、「暗い場所でも枯れずに耐えられる」という性質であり、「暗い場所で元気に成長する」という意味ではありません。日陰で育てる場合でも、植物の健康を維持するためには限界があり、成長は非常に緩やかになることを理解しておきましょう。
元気なポトスの苗を選ぶポイント

観葉スタイル・イメージ
日陰という、植物にとっては少し厳しい環境で育てることを考えると、スタート地点である「苗選び」は非常に重要です。はじめから健康で体力のある苗を選ぶことで、環境の変化にも耐えやすく、その後の管理が格段に楽になります。
園芸店やホームセンターでポトスの苗を選ぶ際は、以下の4つの重要なポイントをじっくりとチェックしてください。
1.葉の色とつや
健康なポトスは、葉にハリとみずみずしいつやがあります。品種本来の色が濃く、生き生きとしているものを選びましょう。
葉が全体的に黄色がかっていたり、茶色いシミや斑点があったり、葉先が枯れているものは避けましょう。また、元気がなく垂れ下がっているものは、根が傷んでいるか、極端な水切れを経験している可能性があります。
2.茎の状態(節間の詰まり具合)
茎が太く、葉と葉の間(節間=せっかん)がキュッと詰まっている苗は、良い環境で光をしっかり浴びて健康に育った証拠です。
逆に、茎が細くヒョロヒョロと力なく伸び、葉と葉の間隔が不自然に広いものは「徒長(とちょう)」している状態です。これは日照不足のサインであり、体力がないため、購入後の環境変化で弱りやすいです。株元がグラグラしているものも避けましょう。
3.根の状態
見落としがちですが、最も重要なのが根の健康です。鉢をそっと持ち上げ、底にある排水穴を確認します。鉢底から白く健康的な根がわずかに見えている程度なら、根が元気に張っている良い証拠です。
ただし、根が鉢底でぐるぐる巻きになっていたり、穴からはみ出して塊になっているものは「根詰まり」を起こしています。また、根が黒ずんでいたり、異臭がしたりする場合は「根腐れ」の疑いがあるため、絶対に選んではいけません。
4.害虫の有無
害虫は、室内で育て始めると一気に増殖することがあります。特に葉の裏側や新芽の部分、茎の付け根は、ハダニやカイガラムシ、アブラムシなどが付きやすい場所です。
白い綿のようなもの(カイガラムシ)や、クモの巣のように細い糸(ハダニ)、ベタベタした透明な液(害虫の排泄物)がないか、しっかり確認しましょう。
お店に並んでいる中で、最も葉の色が濃く、茎がしっかりしていて、株全体がこんもりと茂っているものを選ぶのが、日陰で育てるための最初のコツですよ!
基本の育て方と置き場所
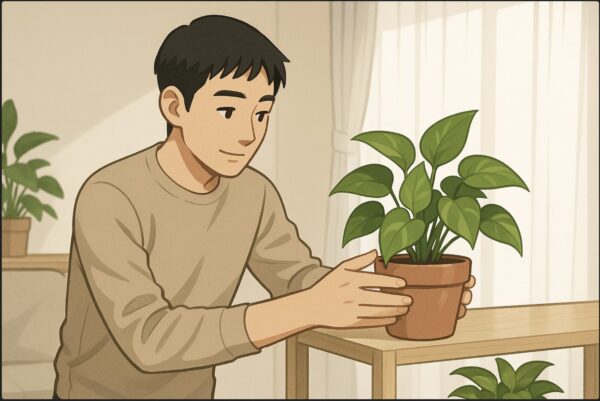
観葉スタイル・イメージ
ポトスの耐陰性を活かすには、置き場所と日々の管理(水やり、湿度)のバランスが重要です。「暗さに耐えられるから」といって、植物にとって過酷な環境に放置すると、元気がなくなってしまいます。
ポトスが耐えられる「日陰」のレベル
一口に「日陰」と言っても、植物にとっては明るさが全く異なります。植物の育成に必要な光の強さは「ルクス(lx)」という単位で示されます。
- 明るい日陰(半日陰)
直射日光は当たらないものの、日中は電気を点けなくても新聞や本が読める程度の明るさがある場所。目安として1,000〜2,500ルクス程度。例:レースカーテン越しの窓辺、窓から少し離れた(1〜2m)リビングなど。 - 日陰
間接光も少なく、一日を通して薄暗い場所。本を読むには照明が必要な明るさ。目安として500〜1,000ルクス程度。例:北向きの部屋、廊下、部屋の奥など。 - 完全な日陰
光がほとんど入らない場所。目安として500ルクス以下。例:窓のないトイレ、浴室、地下室など。
ポトスが健康を維持し、枯れずに耐えられる明るさの限界は、一般的に「日陰(500ルクス)」程度までと言われています。窓のないトイレや浴室のような「完全な日陰」では、光合成がほぼできず、蓄えた養分を使い果たしていずれ枯れてしまいます。
理想の置き場所と「ローテーション」
最も理想的なのは、レースカーテン越しの柔らかい光が当たる「明るい日陰」です。この場所なら、ポトスは元気に成長します。
もし玄関や廊下など暗い場所に置きたい場合は、「ローテーション」が非常に効果的です。
例えば、2鉢用意し、1週間ごとに「暗い場所」と「明るい日陰」の鉢を入れ替えるのです。これなら、常に元気なポトスを暗い場所で楽しむことができます。1鉢しかない場合でも、週に2〜3回、数時間だけでも「明るい日陰」に移動させて光合成をさせてあげましょう。
日陰で育てる際の管理方法
暗い場所は、明るい場所と比べて環境が異なります。その違いを意識した管理が重要です。
- 水やり
土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。ただし、日陰は光が少なく光合成が活発でないため、土の乾きが非常に遅くなります。常に土が湿っていると「根腐れ」の最大の原因になるため、「土の表面が乾いたこと」を指で触ってしっかり確認してから水やりをしてください。 - 葉水(はみず)
霧吹きで葉に水をかける「葉水」は、熱帯雨林の多湿な環境を再現し、湿度を保つ効果があります。また、葉の表面のホコリを落とし、光合成の効率を上げる助けにもなります。 - 風通し
室内の日陰は空気がよどみがちです。風通しが悪いと土がさらに乾きにくくなり、病害虫の発生源にもなります。サーキュレーターで空気を循環させたり、時々窓を開けて換気したりすることを心がけましょう。
エアコンの風が直接当たる場所は、極端な乾燥や急激な温度変化で葉が傷んでしまいます。人間が快適でも植物には過酷な環境ですので、必ず避けてください。
季節ごとの水やりと管理方法

観葉スタイル・イメージ
ポトスは熱帯原産の植物です。そのため、一年中温度が安定している原産地とは異なり、日本の四季、特に「気温」の大きな変化に合わせて水やりの頻度や肥料の有無を調整する必要があります。
春・夏・秋(生育期:目安として4月〜10月)
気温が15℃以上を安定して超えるようになると、ポトスは活発に成長を始めます。この時期は「生育期」と呼ばれ、水も養分も必要とします。
- 水やり
土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。特に夏場は生育旺盛で水をよく吸うため、日陰で管理している場合でも、水切れさせないよう土の乾き具合をこまめにチェックしましょう。受け皿に溜まった水は、根腐れの原因になるため必ず捨ててください。 - 肥料
生育を助けるため、2ヶ月に1回程度の緩効性肥料(土の上に置くだけの錠剤など)を施すか、10日に1回程度の液体肥料を水やり代わりに与えます。ただし、日陰でゆっくり育てたい場合や、頻繁に植え替えている場合は、肥料は控えめでも問題ありません。
冬(休眠期:目安として11月〜3月)
気温が10℃を下回ると、ポトスの生育は非常に緩慢になります。これは寒さから身を守るための「休眠期」です。
- 水やり
冬場は水やりを大幅に控えめにします。土が乾いているのを確認してから、さらに2〜3日待ってから水を与える程度で十分です。日陰の室内では土の乾きがさらに遅くなるため、1週間に1回でも多すぎる場合があります。「土が完全に乾いてから水やりをする」ことを徹底し、根腐れを防ぎましょう。 - 葉水
冬は暖房の影響で空気が非常に乾燥します。根への水やりは控えますが、葉水はこまめに行い、葉の湿度を保ちましょう。これはハダニの発生を予防する上でも非常に重要です。 - 肥料
冬場に肥料を与えると、休眠中の根が養分を吸収できずに「肥料焼け」を起こし、かえって株を弱らせる原因となります。冬場の肥料は絶対にやめてください。
冬の置き場所(最低温度)
ポトスは寒さに非常に弱く、健康に冬越しさせるには最低でも5℃以上をキープする必要があります。特に冬の夜、窓際は外気と変わらないほどに冷え込みます。日陰に置いている場合も、夜間は部屋の中央など、窓から離れた暖かい場所(ただし暖房の風が直接当たらない場所)に移動させましょう。
根詰まりを防ぐ植え替えの時期
ポトスは生育旺盛な植物です。日陰で育てていて上部(葉や茎)の成長がゆっくりに見えても、鉢の中では根が成長を続けています。1〜2年に1回を目安に、鉢の中の状態をチェックし、必要であれば植え替えを行いましょう。
植え替えが必要なサイン
以下のサインが見られたら、鉢の中で根が窮屈になっている「根詰まり」の合図です。
- 鉢底の穴から根が飛び出している。
- 水を与えても、土への染み込みが悪くなった(水が表面に溜まる)。
- 鉢の表面の土が盛り上がってきた、または鉢がパンパンに張っている。
- 下葉が黄色くなったり、葉が小さくなったり、元気がなくなってきた(根から養分や水をうまく吸えない)。
植え替えの最適な時期
植え替えは、植物にとって少なからずダメージとなる作業です。
そのため、ダメージからの回復が最も早い生育期の初期(5月〜7月)に行うのがベストです。この時期であれば、植え替えで多少根が傷んでもすぐに新しい根を伸ばし、活発に成長を再開します。気温が下がる秋以降や、真夏の猛暑日の植え替えは、回復が遅れるため避けましょう。
植え替えの手順
手順
- 準備:現在よりも「一回り大きな」(直径で3cm程度)鉢と、水はけのよい市販の「観葉植物用の培養土」、鉢底石、鉢底ネットを用意します。
- 引き抜き:鉢の縁を軽く叩いて土をほぐし、株元を持ってポトスを慎重に引き抜きます。
- 根の整理:古い土を手で優しく揉んで、1/3程度落とします。このとき、黒ずんで腐った根や、古く硬くなった根があれば、清潔なハサミで切り落とします。根がガチガチに固まっている場合は、少しほぐしてあげます。
- 植え付け:新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を敷き、土を少し入れます。ポトスを中央に配置し、高さを調整しながら隙間に新しい土を入れていきます。割り箸などで土を軽く突き、根の隙間まで土を充填します。
- 水やりと養生:植え替え後は、鉢底から透明な水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。その後、1〜2週間は直射日光の当たらない「明るい日陰」で休ませ、新しい環境に慣らさせます。
樹液による「かぶれ」に注意
ポトスはサトイモ科の植物です。茎や葉を切った際に出る樹液には、「シュウ酸カルシウム」という針状の結晶成分が含まれています。この樹液が肌に付着すると、体質によってはかぶれたり、強い痒みや炎症を起こしたりする場合があります。
厚生労働省も、シュウ酸カルシウムを含む植物による食中毒や皮膚炎について注意喚起を行っています(参照:厚生労働省「自然毒のリスクプロファイル」)。 植え替えや剪定の際は、念のためゴム手袋などを着用することを強くおすすめします。もし樹液に触れてしまった場合は、すぐに流水でよく洗い流してください。
ポトスの耐陰性とトラブル対策
参考
- 日陰で弱った時の対策とは
- 暗い場所で注意すべき病気
- 風通しと害虫の予防
- 徒長を防ぐ摘芯のやり方
- ポトスの地植えは可能か
- ポトスの耐陰性を理解しよう
日陰で弱った時の対策とは
日陰でポトスを育てていて、「葉の色がおかしい」「ヒョロヒョロしてきた」と感じたら、それは植物からのSOSサインです。耐陰性があるポトスでも、その限界を超えると様々な不調をきたします。
主な原因は、日陰という環境特有の「極度の日照不足」または「水のやりすぎによる根腐れ」であることがほとんどです。
症状1:茎が間延びする(徒長)
茎が細長くヒョロヒョロと力なく伸び、葉と葉の間隔(節間)が異常に広がる現象を「徒長(とちょう)」と呼びます。
これは、ポトスが光を求めて必死に明るい方へ伸びているサインです。暗すぎると、光合成が十分にできず、茎を支えるための体力も作れないため、このような不格好な姿になってしまいます。徒長した株は見た目が悪いだけでなく、病害虫への抵抗力も弱まります。
対策:まずは、より明るい場所へ移動させることが基本です。移動が難しい場合は、前述した「ローテーション」を試すか、植物育成用のLEDライトを導入して人工的に光を補うことを検討しましょう。一度徒長した部分は元には戻らないため、後述する「摘芯」で切り戻す必要があります。
症状2:葉の色が薄くなる・斑が消える
暗い場所に長期間置くと、植物は光合成の効率を最大限に高めようとして、葉緑素を増やします。その結果、斑入り品種の特徴である美しい斑(模様)が消え、葉全体が緑色っぽくなる「先祖返り」が起こることがあります。これは日照不足の典型的な症状です。
対策:徒長と同じく、より明るい場所へ移動させることが唯一の対策です。一度消えた斑は戻りませんが、明るい場所で新しく生えてくる葉には、再び斑が入る可能性があります。
症状3:葉が黄色くなる・落ちる
葉が黄色くなる原因は複数考えられ、日陰の環境では特に判断が難しいですが、主に以下の3つが疑われます。
- 水のやりすぎ(根腐れ):日陰で最も多い原因です。土が乾きにくいのに水やりを続けた場合、根が呼吸できず酸欠状態になり腐ってしまいます。根が機能しなくなると、水や養分を吸えなくなり、葉が黄色くなり、ポロポロと落ち始めます。土から異臭がしたり、株元が黒ずんで柔らかくなったりする場合は重症です。
- 水切れ:根腐れとは逆に、水やりを忘れ続けた場合も葉は黄色くなります。ただし、日陰で水切れになるケースは稀です。土がカラカラに乾き、鉢から剥離しているようなら水切れです。
- 根詰まり:長期間植え替えをしていない場合、根詰まりを起こして養分不足になり、主に下葉(古い葉)から黄色くなってきます。
対策:まずは土の状態を注意深く確認します。常に湿っていてジメジメしているなら根腐れの可能性が高いです。すぐに水やりを止め、鉢から抜いて黒ずんだ根を取り除き、新しい土で植え替える緊急手術が必要です。カラカラに乾いているなら水切れ、鉢底から根がびっしりなら根詰まりですので、それぞれ適切な対処(水やり、植え替え)を行います。
暗い場所で注意すべき病気
日陰の室内は、「湿度が高くなりやすい」(空気がこもるため)一方で「風通しが悪くなりがち」です。このような環境は、カビ(糸状菌)が原因となる病気にとって非常に好都合な条件です。
炭そ病(たんそびょう)
カビが原因で起こる代表的な病気です。葉に灰色や黒褐色、茶褐色の斑点が現れます。
初期は小さな点ですが、次第に拡大し、同心円状の模様(輪紋)ができたり、斑点が融合したりします。放置していると斑点の中心が破れて穴が空いたり、葉が枯れたりします。高温多湿の時期、特に梅雨に発生しやすいです。
対策:症状が出た葉は早めに切り取って処分し、病気の拡大を防ぎます。水やりは株元に行い、葉に水がかからないようにすることも予防に繋がります。
病気の予防策
病気の多くは、風通しを良くすることで予防できます。日陰に置く場合でも、空気がよどまないよう、定期的に換気を心がけましょう。サーキュレーターなどで室内の空気を緩やかに循環させるのは非常に効果的です。
また、葉が過密になってくると株内部の風通しが悪くなります。後述する「摘芯(剪定)」で葉を整理し、風通しを良くしてあげることも、病気の予防に直結します。
風通しと害虫の予防
日陰で風通しが悪い環境は、病気だけでなく害虫にとっても格好の住処となります。特に室内で発生しやすく、一度発生すると厄介なのが「ハダニ」と「カイガラムシ」です。
ハダニ
ハダニは0.5mm程度と非常に小さく、肉眼での確認が難しい害虫です。高温で乾燥した環境を好み、特に冬場、暖房で乾燥した室内は要注意です。
葉の裏側に寄生し、養分を吸うため、被害が進むと葉の色がカスリ状に抜け(「葉水」の症状と似ています)、元気がなくなります。大量に発生すると細い糸を引くこともあります。
予防・対策:ハダニは水に非常に弱いため、こまめな葉水(霧吹き)で葉の表裏を濡らすことが、最も効果的な予防法です。発生してしまった場合は、シャワーなどで洗い流すか、数が多ければ園芸用の殺虫剤(ハダニ専用のもの)を使用します。
カイガラムシ
白い綿のようなもの(コナカイガラムシ)や、硬い殻をまとったもの(カタカイガラムシ)が葉や茎に付着します。これも養分を吸汁し、株を弱らせます。さらに、排泄物(甘露)がベタベタするため、これが原因でカビが発生し、葉が黒くなる「すす病」を誘発することもあります。
予防・対策:成虫は殻で覆われているため薬剤が効きにくい厄介な害虫です。見つけ次第、歯ブラシやティッシュ、ピンセットなどで物理的にこすり落とすのが最も確実です。幼虫の時期であれば、専用の殺虫剤も有効です。(参照:アース製薬「カイガラムシ(貝殻虫)の生態と種類」)
葉水は、湿度を保って植物を元気にするだけでなく、ハダニの予防にもなる、一石二鳥のお手入れなんですよ! 葉の裏側にもしっかりかけるのがコツです。
徒長を防ぐ摘芯のやり方

観葉スタイル・イメージ
暗い場所で育てていると、どうしても茎が間延び(徒長)しがちです。ヒョロヒョロと伸びて見栄えが悪くなってきたら、「摘芯(てきしん)」または「剪定」を行い、姿を仕立て直しましょう。
摘芯の効果
摘芯とは、伸びすぎたツルの先端(頂芽)を切り詰めることです。
植物には、先端の芽の成長を優先する「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質がありますが、先端を切り取ることでこの性質が解除されます。その結果、切った箇所のすぐ下の節に残っていた「脇芽(わきめ)」が目を覚まし、新しいツルとして伸びてきます。
これにより、一本調子だったツルが分岐し、株全体のボリュームが増し、こんもりとしたバランスの良い姿に仕立て直すことができます。また、茂りすぎた葉やツルを整理することで、株内部の風通しが良くなり、病害虫の予防にも繋がります。
摘芯の時期と方法
- 時期:植え替えと同様、植物の体力がある生育期(5月〜10月)に行います。切った後の回復が早いです。
- 方法:間延びしたツルを選び、お好みの長さでカットします。どこで切っても基本的には大丈夫ですが、葉の付け根にある「節」の少し上で切るのがポイントです。節には新しい芽を出す「生長点」があるため、ここから新しい芽が伸びやすくなります。
切ったツルは「挿し木」で増やせます
摘芯で切ったツルは、捨てる必要はありません。「挿し木(さしき)」として簡単に増やすことができます。
- 切ったツルを、葉が1〜2枚付くように(1節〜2節)切り分けます。
- 水を入れたコップや花瓶に挿しておくだけで(水差し)、数週間で節から新しい根が出てきます。水は毎日取り替えて清潔に保ちましょう。
- 根が十分(5cm程度)伸びたら、観葉植物用の土に植え替えて、新しい株として育てることができます。
ポトスの地植えは可能か

観葉スタイル・イメージ
「ポトスは地植えできるのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、結論から言うと、日本のほとんどの地域(沖縄や小笠原諸島などの一部の亜熱帯・熱帯地域を除く)で、ポトスを屋外で地植えにして冬を越させることは不可能です。
不可能な理由:耐寒性の低さ
ポトスはソロモン諸島などの熱帯雨林地域が原産の植物です。そのため、寒さに非常に弱く、生育には最低でも10℃以上、冬越しには最低5℃以上の温度が求められます。日本の冬の気温は、氷点下になることも珍しくなく、ポトスにとっては致命的です。霜が一回降りただけでも枯れてしまいます。
原産地では、地植えのポトスは木々などに絡みつきながら、葉が1メートル近くになるほど巨大に成長します。この巨大化したポトスは、ある条件が揃うと花を咲かせることもありますが、日本の室内で鉢植えで育てている環境では、まず開花することはありません。
夏だけ屋外に出す場合の注意点
春から秋にかけての暖かい時期に限り、屋外の「日陰」(直射日光が絶対に当たらない場所)で管理することは可能です。
しかし、冷房の効いた室内から真夏の酷暑の屋外へ急に出すと、強烈な温度変化や湿度変化、紫外線量といった環境の激変に耐えられず、大きなダメージ(葉焼けや「夏バテ」)を受ける可能性があります。
もし屋外に出す場合は、気温が安定した春や秋に、最初は1〜2時間だけ日陰に出し、徐々に屋外の環境に慣らしていく「順化(じゅんか)」の期間が必要です。
また、屋外は害虫の被害に遭いやすくなります。秋になって室内に取り込む際に、害虫も一緒に持ち込んでしまうリスクがあるため、基本的には一年を通して室内で管理することが最も安全で推奨されます。
ポトスの耐陰性を理解する為のまとめ
最後にこの記事の要点をまとめます。ポトスの耐陰性を正しく理解し、品種選び、置き場所、水やりなど、その環境に合わせた適切な管理を行うことが、日陰で長く元気に楽しむための鍵です。
チェックリスト
- ポトスの耐陰性には品種によって大きな差がある
- 葉が緑一色の品種(パーフェクトグリーンなど)が最も暗さに強い
- 斑入り、特に白斑が多い品種(マーブルクイーンなど)は耐陰性が弱い
- 「耐陰性」は「暗くても成長する」ではなく「枯れずに耐えられる」という意味
- 元気な苗は葉につやがあり、茎の節間が詰まっているものを選ぶ
- ポトスが健康に耐えられるのは「明るい日陰」(500ルクス以上)まで
- 窓のない「完全な日陰」ではいずれ枯れてしまう
- 暗所に置く場合は「ローテーション」や定期的な日光浴が必要
- 日陰では土の乾きが遅いため水のやりすぎ(根腐れ)に最大の注意を払う
- 冬場は水やりを大幅に控え、土が乾いてから数日あける
- 冬場の肥料は「肥料焼け」の原因になるため厳禁
- 葉水は乾燥を防ぎ、ハダニの予防に非常に効果的
- 1〜2年に1回は生育期(5〜7月)に植え替えを行う
- 徒長(間延び)は日照不足のサインであり、摘芯で仕立て直せる
- ポトスは寒さに極めて弱く、日本の地植えでの冬越しは不可能
