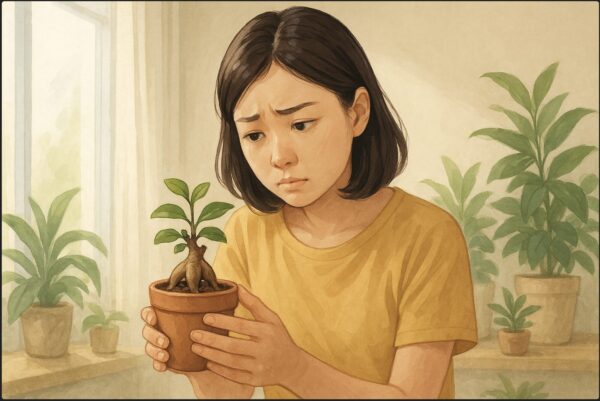
観葉スタイル・イメージ
大切に育てているガジュマルから新芽が出ないと、本当に心配になりますよね。「もしかして枯れるのでは?」「育て方が悪いのだろうか」と不安になるかもしれません。
ガジュマルの新芽が出ない原因は、病気や室内の環境、培養土の状態など、実に様々です。また、元気な姿を取り戻そうとして行う植え替えや摘芯も、時期を間違えると逆効果になり、新芽の成長に影響することもあります。
一方で、ガジュマルは「多幸の樹」とも呼ばれ、スピリチュアルな意味を持つ植物としても知られています。
その新芽には特別な意味が込められているとも言われ、木質化した古い幹からでも力強く芽吹く姿は、私たちに生命力を感じさせてくれます。種類による新芽の違いを知ることも、ガジュマルを育てる大きな楽しみの一つです。
この記事では、ガジュマルの新芽が出ない、あるいは枯れるといったトラブルの原因を深掘りし、元気な新芽を育てるための正しい管理方法を、初心者の方にも分かりやすく詳しく解説します。
ポイント
- ガジュマルの新芽が出ない・枯れる原因の特定
- 新芽を元気に出すための剪定や摘芯のコツ
- 新芽を守るための病害虫対策と室内環境の整え方
- ガジュマルの種類による新芽の特徴やスピリチュアルな意味
コンテンツ
ガジュマルの新芽が出ない?原因と対処法

観葉スタイル・イメージ
参考
- 新芽が枯れるのはなぜ?
- 考えられる病気と害虫
- 室内での置き場所は適切か
- 培養土や根詰まりが原因か
- 植え替え直後は新芽が出にくい?
新芽が枯れるのはなぜ?
ガジュマルの新芽が枯れる、あるいは黒くなってしまう主な原因は、水やりの失敗や急激な環境変化が最も多く考えられます。
新芽は、人間で言えば生まれたての赤ちゃんのようなもので、非常にデリケートです。株本体が何らかのストレスを感じると、生命維持に関わる太い幹や根を守ることを優先し、最も繊細な新芽への水分や養分の供給を止めてしまうことがあります。
1.水やりの失敗(根腐れ・水切れ)
特に水やりは、新芽の育成において最も重要な管理の一つです。
- 水のやり過ぎ(根腐れ):土が常に湿っていると、土の中の酸素が不足し「根腐れ」を引き起こします。根が呼吸できずに腐敗し始めると、水分や養分を吸収できなくなり、真っ先に繊細な新芽から枯れていきます。
- 水切れ:逆に水切れが続くと、株全体が乾燥し、生命維持に必要な水分を新芽まで送ることができなくなってしまいます。特に夏場の水切れは致命的になりやすいです。
2.急激な環境変化(順化不足)
購入したばかりの株や、室内から屋外へ移動させた直後なども注意が必要です。植物は「順化(じゅんか)」といって、新しい環境(光の強さ、温度、湿度)にゆっくりと適応する時間が必要です。店頭という理想的な環境から、急に自宅の環境に変わると、植物は大きなストレスを感じます。
この適応期間中は、植物が新しい環境に対応するためにエネルギーを優先的に使うため、一時的に新芽の成長が止まったり、古い葉を落としたり、新芽が枯れたりすることがあります。
水やりの基本とメリハリ
ガジュマルの水やりは、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」のが基本です。
そして、受け皿に溜まった水は、根腐れの原因になるため必ず捨ててください。常に土が湿っている状態は避け、「乾湿のメリハリ」をつけることが健康な根を育て、元気な新芽につながります。
考えられる病気と害虫

観葉スタイル・イメージ
新芽が正常に育たない場合、または新芽が黒くなったり、ベタベタしたり、変形したりする場合は、病気や害虫の被害が強く疑われます。
新芽は成葉に比べて非常に柔らかく、栄養分が集中しているため、害虫にとって格好の的(まと)です。被害が新芽に集中する主な害虫と、湿度が高まると発生しやすい病気について、その特徴と対策を詳しく解説します。
ハダニ(葉ダニ)
室内でガジュマルを育てる際に最も発生しやすい害虫の一つがハダニです。非常に小さく(0.5mm程度)、肉眼では点にしか見えません。高温と乾燥を好み、特にエアコンの効いた部屋や冬場の乾燥した室内で爆発的に増えることがあります。
- 症状:葉の裏側に寄生し、汁を吸います。初期症状は、葉に「かすり状」の白い小さな斑点が現れ、徐々に葉全体の色素が抜けたように白っぽくなります。新芽が被害にあうと、養分を奪われて縮れたように変形し、そのまま枯れてしまいます。数が増えると、葉や新芽の先にクモの巣のような細い糸を張ることもあります。
- 予防と対策:ハダニは「水」と「湿度」を極端に嫌います。
予防に最も効果的なのは、霧吹きで葉の表裏に水をかける「葉水(はみず)」です。これは湿度を高めるだけでなく、物理的にハダニを洗い流す効果もあります。新芽が元気ないと感じたら、まずは葉の裏をよく観察してみてください。
発生してしまった場合は、葉水で洗い流すか、数が多い場合は専用の殺ダニ剤(殺虫剤ではなく「殺ダニ剤」)を使用します。ハダニは薬剤抵抗性を持ちやすいため、一度で全滅させようとせず、数日おきに2~3回散布するのが効果的です。
カイガラムシと「すす病」
ガジュマルの幹や葉がベタベタしている場合、その原因はカイガラムシである可能性が非常に高いです。カイガラムシには白い綿のようなワタカイガラムシや、茶色く硬い殻を持つカタカイガラムシなどの種類がいます。
- 症状:枝の付け根や葉の裏に張り付き、植物の汁を吸います。新芽の付け根に取り付かれると、新芽は萎縮してしまいます。
- ベタベタの正体(すす病):カイガラムシの排泄物は糖分を多く含み、これが葉や幹に付着してベタベタします。さらに、この排泄物を栄養源にして「すす病」という黒いカビが発生します。葉が黒いススで覆われたようになり、光合成を妨げて株全体を弱らせます。
- 対策:成虫は硬い殻やロウ物質で覆われているため、薬剤が効きにくいのが特徴です。(参考:アース製薬「カイガラムシの特徴と防除方法」)数が少なければ、歯ブラシやティッシュでこすり落とすのが最も確実です。薬剤を使用する場合は、幼虫が発生する5月~7月頃に散布するのが最も効果的です。
アブラムシ(油虫)
アブラムシも新芽を好む代表的な害虫です。春から初夏にかけて、屋外で管理していると発生しやすいです。
- 症状:非常に小さな虫が、新芽や若い葉の先にびっしりと群生します。汁を吸うため、新芽は変形し、成長が止まります。
- 対策:カイガラムシ同様、アブラムシも甘い排泄物を出し、「すす病」の原因となります。発生初期であれば、水で洗い流すか、ガムテープなどで取り除けます。数が多い場合は、専用の殺虫剤(オルトランなど)を使用してください。
炭疽病(たんそびょう)
これは害虫ではなく、カビ(糸状菌)が原因で発生する病気です。特に湿度が高い梅雨時期や、風通しが悪い場所で発生しやすくなります。
- 症状:葉に茶色や黒の円い斑点(病斑)ができます。放置すると斑点は次第に大きくなり、やがてその部分が破れて穴が空きます。新芽がこの病気に感染すると、黒くなってそのまま枯れ落ちてしまいます。
- 予防と対策:炭疽病は水滴によって胞子が運ばれるため、予防が何よりも重要です。水やりの際に葉に水がかからないように注意し、特に夜間に葉が濡れたままにならないようにします。また、枝葉が混み合っていると湿気がこもりやすいため、剪定して風通しを良く保ちましょう。
- 発生した場合:症状が出た葉は、他の葉に感染が広がるのを防ぐため、すぐに切り取って処分してください。症状が広がる場合は、「ベニカXファインスプレー」や「ダコニール1000」などの殺菌剤を散布します。(参考:KINCHO園芸「ベニカXファインスプレー」)
病害虫対策の基本
病害虫は、発生してから対処するよりも「発生させない環境づくり」が最も重要です。
- 風通しを良くする(剪定・サーキュレーター)
- 適切な湿度を保つ(乾燥させすぎず、蒸れさせすぎない)
- 毎日観察する(特に葉の裏側と新芽)
日々の「葉水」と「観察」が、元気な新芽を守る一番の近道です。
室内での置き場所は適切か
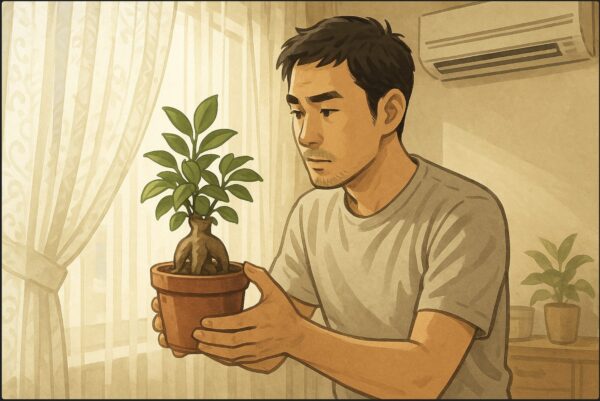
観葉スタイル・イメージ
ガジュマルは原産地では強い日差しを浴びて育つ植物です。室内での置き場所が、新芽の成長に大きく影響します。
最も多い失敗例は、日照不足です。「耐陰性(日陰に耐える力)がある」と紹介されることが多いため、「暗い場所でも大丈夫」と誤解されがちです。しかし、これは「暗くても元気に育つ」という意味ではなく、あくまで「耐える」ことができるだけです。成長には一定の光が不可欠です。
光が全く入らない暗い場所に長期間置くと、株はわずかな光を求めて枝が細く、葉と葉の間隔が異常に開いてひょろひょろと間延び(徒長)してしまいます。このような状態では株が弱り、新芽を出す元気がなくなります。
室内で管理する場合は、レースのカーテン越しに柔らかい光が当たる窓辺が最も理想的です。明るい場所で育てることで、光合成を活発に行い、幹が太く、葉の色艶も良くなり、元気な新芽が育ちます。
ただし、光が強すぎても問題です。特に真夏の直射日光は、葉緑素を破壊して「葉焼け」を起こし、新芽や葉が黒く焦げたように枯れる原因になります。室内であっても、西日が強く当たる窓際などは、夏場は避けるか、レースカーテンで遮光してください。
エアコンの風は厳禁!風通しは重要
もう一つの注意点は、エアコンの風が直接当たる場所です。冷暖房の風は空気を極度に乾燥させます。
植物は葉から水分を蒸散させていますが、乾燥した風が当たり続けると蒸散が異常に促進され、根からの水分補給が追いつかなくなります。結果として、最も水分を保持する力が弱い新芽から乾燥し、枯れてしまうのです。
エアコンの風が当たらない、温度変化の少ない場所に置きましょう。ただし、空気の循環は重要です。サーキュレーターなどで部屋の空気を優しく動かし、風通しを良くすることは、病害虫の予防にもつながります。
培養土や根詰まりが原因か
新芽の勢いがなくなってきた、または新芽が出ても以前より葉が小さいと感じたら、鉢の中の培養土や根の状態を確認してみましょう。
ガジュマルを同じ鉢で長年(2年以上)育てていると、土の中の養分がなくなるだけでなく、土の物理性(構造)も悪化します。培養土は時間と共に「団粒構造」というフカフカした構造が崩れ、微塵(みじん)となって固まり、水はけや通気性が悪くなっていきます。
水はけが悪い土壌では、根が常に湿った状態になり、酸素不足や根腐れを起こしやすくなります。これでは、いくら水や肥料を与えても新芽は元気に育ちません。
また、ガジュマルの成長スピードは速く、鉢の中で根が育ちすぎると「根詰まり」を起こします。鉢の中で根がぎゅうぎゅうになると、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、水分や養分の吸収効率が著しく低下します。
根詰まりのサイン
- 鉢底の穴から根が飛び出している:根が新しいスペースを求めて外に出てきています。
- 水が染み込みにくい:鉢の中が根でいっぱいになり、水の通り道がなくなっています。
- 土が乾くのが異常に早い:土の量が減り、根がすぐに水を吸い上げてしまう状態です。
- 新しい葉が小さくなってきた:養分や水分が不足し、大きな葉を作る体力がありません。
これらのサインが見られたら、植え替えの時期です。2年に1回を目安に、成長期の5月~9月に一回り大きな鉢に新しい観葉植物用の培養土で植え替えることをおすすめします。
植え替え直後は新芽が出にくい?
根詰まりを解消するために植え替えをしたのに、新芽が止まってしまった、というケースもよくあります。
これは、植物が植え替えによるストレスを感じているためです。植え替えは、人間で言えば「大きな手術」のようなもので、どんなに丁寧に行っても古い土をほぐす際に細い根が切れ、多かれ少なかれダメージを受けます。この負荷から回復するために、ガジュマルは一時的に成長をストップさせます。
ガジュマルは植え替えのダメージから回復するために、まず新しい根(特に水分を吸収する細かな「細根」)を張り、水分を吸収する体制を立て直すことにエネルギーを集中させます。そのため、一時的に地上部(新芽や葉)の成長が止まるのは、むしろ正常な反応と言えます。
この「養生(ようじょう)」期間は非常に重要です。植え替え直後は、直射日光を避けた明るい日陰で管理し、土が乾いてから水を与えるようにします。
また、弱った根に肥料を与えると、逆に「肥料焼け」を起こしてさらなるダメージを与えるため、植え替え後1ヶ月程度は絶対に肥料(特に化学肥料)を与えてはいけません。
新しい根が張り始め、株が安定してくれば、再び元気な新芽が出てくるようになりますので、焦らずに見守りましょう。肥料分のない活力剤(メネデールなど)の使用は、発根を助けるため有効です。
ガジュマルの新芽を元気に育てる管理方法
参考
- 新芽を出す剪定の時期
- 摘芯による新芽の増やし方
- 木質化した幹から芽吹かせる
- 種類によって新芽の特徴は違う?
- 新芽が持つスピリチュアルな意味
新芽を出す剪定の時期
ガジュマルの新芽を元気に、そして意図した場所から出させるためには、剪定(せんてい)が非常に有効です。剪定に最適な時期は、成長期にあたる5月~9月頃です。
この時期は気温が安定して高く、光合成も活発に行われるため、ガジュマルの生命力が年間で最も高まります。植物の成長ホルモンが活発に働くため、剪定で枝を切っても、切り口の下や幹からすぐに新しい新芽が次々と芽吹いてきます。剪定によるダメージからの回復も早いのが特徴です。
剪定する際は、枝の「節(ふし)」と呼ばれる少し膨らんだ部分のすぐ上で切ることがポイントです。この節には新しい芽になる「成長点」が隠れているため、ここから新芽が伸びやすくなります。節から離れた場所で切ると、中途半端に残った枝が枯れ込むことがあるので注意しましょう。
剪定の注意点
- 時期を守る:気温が下がる秋以降や冬場の剪定は避けてください。冬はガジュマルの休眠期にあたり、成長が緩慢になります。この時期に大きな剪定を行うと、体力が回復できずに春になっても新芽が出なくなったり、最悪の場合枯れてしまったりするリスクが高まります。
- 道具を清潔に:剪定に使うハサミは、必ず清潔なものを使用してください。汚れたハサミを使うと、切り口から雑菌が入り、病気の原因になります。ライターで炙るか、アルコールで消毒すると安心です。
- 樹液に注意:ガジュマルはゴムの木の仲間(フィカス属)で、枝を切ると白い樹液(ラテックス)が出ます。この樹液は皮膚が弱いとかぶれることがあるため、手袋をして作業することをおすすめします。
摘芯による新芽の増やし方
「摘芯(てきしん)」は、新芽を増やして葉を密に茂らせるための園芸テクニックで、剪定の一種です。
多くの植物には「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。これは、枝の先端にある芽(頂芽)が優先的に成長し、そこから成長ホルモン(オーキシン)が分泌されることで、脇の芽(側芽)の成長を抑制するというものです。
ガジュマルもこの性質を持つため、放置すると特定の枝だけがひょろひょろと上に伸びてしまいがちです。
摘芯は、この先端の芽(新芽)を指や清潔なハサミで摘み取る作業を指します。先端の成長点がなくなることで頂芽優勢が破られ、これまで抑えられていた脇の芽(側芽)が「自分の出番だ」とばかりに一斉に成長を始めます。
摘芯の効果
これにより、枝分かれが促進され、一本の枝から二本、三本と新しい芽が伸び、こんもりとしたバランスの良い樹形に仕立てることができます。
ひょろひょろと上にばかり伸びてしまう場合の樹形リセットや、ボリュームアップに非常に有効な方法です。剪定と同様、必ず成長期(5月~9月)に行いましょう。
木質化した幹から芽吹かせる

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの大きな魅力の一つは、その驚異的な生命力にあります。他の多くの観葉植物では諦めてしまうような、葉がすべて落ちてしまった状態からでも復活できる可能性を秘めています。
一見するとただの「木」にしか見えない、葉がまったくない茶色く木質化した太い幹からでも、適切な環境下であれば新芽を芽吹かせることができます。この現象は、ガジュマルの幹が持つ「不定芽(ふていが)」のおかげです。
不定芽とは、枝や葉の付け根といった決まった場所(節)ではなく、幹の途中や根など、予期しない場所から出てくる芽のことです。
普段は眠っていますが、植物が強いストレス(剪定や枝折れ、葉がすべてなくなるなど)を受けると、「生命の危機だ」と察知して目を覚ます、予備の芽のようなものです。
ガジュマルの強さの秘密
ガジュマルはこの不定芽を幹のいたるところに持っているため、大胆に切り戻しても、残った幹から新しい枝葉を展開して再生することができるのです。
例えば、根腐れや病気、冬の深刻な水切れで葉がすべて落ちてしまった株でも、すぐには諦めないでください。まずは「生きているか」を確認します。
幹や根元を触ってみて、ブヨブヨと柔らかくなっていなければ(=腐っていなければ)、復活の可能性があります。清潔なカッターナイフなどで幹の表面を薄く削ってみて、中が緑色であれば、その株はまだ生きています。
生きていれば、「丸坊主」と呼ばれる強剪定(きょうせんてい)で再生を図ることができます。
木質化させた幹から新芽を出す手順
再生作業は、植物への負担が最も少ない成長期(5月~9月)に必ず行ってください。気温が低い時期に行うと、回復できずにそのまま枯れてしまうリスクが非常に高いです。
手順
- 清潔な道具の準備:剪定バサミや、幹が太い場合はノコギリを準備します。切り口から雑菌が入ると致命的になるため、必ず火で炙るか、アルコールで消毒してください。
- 思い切って剪定する:枯れている枝、弱っている枝をすべて根元から切り落とします。どのくらい残すか迷う場合は、好みの樹形の高さより少し低い位置で、幹や太い枝を水平にカットします。
- 切り口の保護(推奨):太い幹を切った場合、切り口から水分が蒸発したり、雑菌が入ったりするのを防ぐため、「癒合剤(ゆごうざい)」(トップジンMペーストなど)を塗っておくと安心です。(参考:KINCHO園芸「切り口の保護(癒合剤)」)
剪定後(丸坊主後)の管理方法
ここからの管理が、新芽が出るかどうかの最大の分かれ道です。葉がまったくない状態は、植物にとって「光合成ができない」「水分を蒸散できない」という異常事態です。
- 置き場所:直射日光は絶対に避けてください。葉がないため、幹が日焼けしてしまいます。ただし、芽を出すエネルギーは光が必要なため、真っ暗な場所もNGです。「レースのカーテン越しの明るい日陰」が最適です。
- 肥料:絶対に与えてはいけません。根が弱っている状態で肥料を与えると、根が「肥料焼け」を起こし、とどめを刺すことになります。新芽が数枚展開して成長が安定するまで(最低1~2ヶ月)は我慢してください。
丸坊主後の「水やり」が最重要
葉が一枚もない状態のガジュマルは、ほとんど水を消費しません。(葉からの蒸散がないため)
この状態で、葉があった時と同じペースで水やりを続けると、土がずっと湿ったままになり、残った根も確実に腐ってしまいます。水やりは、土の表面が乾いてから、さらに数日待つ(あるいは土の中まで乾燥しているのを確認する)くらいで十分です。
むしろ、土を乾燥気味に保つことで発根を促す効果もあります。「水やりを我慢する」ことが、再生への一番の近道だと覚えておいてください。
この管理を続けると、早ければ2~3週間、遅くとも1~2ヶ月ほどで、幹の途中からポツポツと小さな緑色の新芽が顔を出し始めます。この瞬間は、ガジュマルの生命力を最も実感できる、感動的な瞬間です。生命力を信じて、焦らずに見守ってあげましょう。
種類によって新芽の特徴は違う?
「ガジュマル」と一口に言っても、いくつかの種類(園芸品種)が流通しており、それぞれ新芽や葉の形に特徴があります。
代表的な種類の特徴を下の表にまとめます。
| 種類 | 葉の特徴 | 新芽の傾向 |
|---|---|---|
| パンダガジュマル | 葉が丸く、肉厚で光沢がある。一般的なガジュマルより成長がゆっくり。多くは接ぎ木で生産される。 | 葉の形と同様に、丸みを帯びた可愛らしい新芽が出ます。新芽も肉厚で、開くまでに時間がかかることがあります。 |
| 黄金ガジュマル | 新芽がライムグリーンや鮮やかな黄色になる品種。 | 明るい黄緑色の新芽が特徴。日光によく当てることで、この美しい発色が維持されます。光が不足すると緑色に戻りがちです。 |
| センカクガジュマル | 沖縄の尖閣諸島原産とされる。一般的なガジュマルより葉が小さく、枝が横に広がりやすい(ほふく性)。 | 非常に小さな新芽が出ます。枝が密に出やすいため、盆栽のように仕立てるのにも向いています。 |
| ニンジンガジュマル | 品種名ではなく、人参のような形の根(塊根)を持つ「仕立て方」の名称。 | 新芽は一般的なガジュマルと同じです。ユニークな根(塊根)との対比が楽しめます。 |
このように、品種ごとの違いを知っておくと、新芽が出てきたときの楽しみがさらに増えます。特にパンダガジュマルや黄金ガジュマルは、その新芽の愛らしさから人気があります。
新芽が持つスピリチュアルな意味

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルは沖縄などで「キジムナー」という精霊が宿る木とされ、古くから「多幸の樹(たこうのき)」と呼ばれる非常に縁起の良い植物です。(出典:青の洞窟Core)このため、単なるインテリアグリーンとしてだけでなく、スピリチュアルな存在として生活に取り入れる方も少なくありません。
その中でも、ガジュマルから「新芽が出る」という現象は、その強い生命力を目に見える形で示す、特別なサインとされています。
新芽が象徴する主なスピリチュアルな意味
- 再生と新たな始まり:木質化した古い幹からでも芽吹く姿は、困難や停滞を乗り越え、新しく物事を始める力(再生)を象徴します。
- 成長と発展:上向きに伸びる新芽は、運気の上昇、仕事や学業の発展、家族の成長を示唆します。
- 幸運の訪れ:「多幸の樹」から新しい生命が生まれること自体が、家庭に新しい幸運や喜びが舞い込む前触れとされています。
特に、葉が全て落ちて丸坊主になった状態からでも芽吹くその力強い生命力は、持ち主に「諦めない力」や「何度でもやり直せる」というポジティブなエネルギーを与えてくれると信じられています。
この「再生」のイメージが、新しいことを始めようとする人や、困難な状況にある人にとって、強力なお守りのような存在となるのです。
風水から見た新芽のエネルギー
風水においても、植物は「生気(せいき)」を生み出す重要なアイテムとされています。
ガジュマルのように上向きに成長する植物は、活発なエネルギーである「陽の気」を持つとされます。
特に「新芽が次々と出る」状態は、その空間のエネルギーが活性化している証拠です。また、ガジュマルの持つ丸みを帯びた葉は、人間関係の調和や、金運を穏やかにする力があるとも言われています。
そのため、新芽が元気に出ているガジュマルをリビングや玄関に置くことで、家全体の運気を高め、良いご縁や幸運を呼び込むと考えられています。
逆に、ガジュマルから新芽が全く出ない状態が続くことは、スピリチュアルな観点では「運気の停滞」のサインと捉えられることもあります。しかし、これは悪いことが起きる前兆というよりは、「環境の見直しが必要」という植物からのメッセージです。
それは、日当たりや水やりといった「植物の環境」かもしれませんし、風水の観点では「部屋の気の流れ(風通しや整理整頓)」かもしれません。
植物の状態は、住環境や気の流れを映す鏡とも言えます。新芽が出ないことをきっかけに、身の回りの環境を整えてみることが、結果として運気を好転させることにつながるでしょう。
ガジュマルの新芽を育てるポイント

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの元気な新芽を育てるための、これまでのポイントを以下にまとめます。
チェックポイント
- ガジュマルの新芽はデリケートで環境の変化に敏感
- 新芽が枯れる主な原因は水の過不足(根腐れ・水切れ)
- 日照不足やエアコンの直風も新芽の成長を妨げる
- 室内ではレースカーテン越しの明るい窓辺が最適
- 害虫(ハダニ、カイガラムシ)は柔らかい新芽の大敵
- 葉水はハダニ予防と湿度維持に効果的
- 土が古い、または根詰まりを起こすと新芽が出にくくなる
- 2年に1回は成長期(5~9月)に植え替えを行う
- 植え替え直後はストレスで新芽が止まることがある
- 植え替え後1ヶ月は肥料を与えない(活力剤はOK)
- 新芽を出すための剪定は成長期の5月~9月が最適
- 冬の剪定は株が弱るため避ける
- 新芽を増やしたい場合は「摘芯」が有効
- 木質化した幹からでも新芽は出る(不定芽)
- パンダガジュマルは丸い新芽、黄金ガジュマルは黄緑色の新芽が特徴
- スピリチュアルな意味では新芽は「幸運のサイン」
