
観葉スタイル・イメージ
ガジュマルを地植えにしたいと考えたことはありませんか。観葉植物として人気のガジュマルですが、その独特の樹形と「多幸の木」という縁起の良さから、お庭のシンボルツリーにしたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、その強靭な生命力の裏には、安易に地植えすると将来的に大きな問題を引き起こす可能性があるという側面も存在します。
特に関東のような冬に寒さが厳しくなる地域での地植えは、冬越しの問題が非常に深刻です。一方で、温暖な九州などの地域では、地植えによって驚くほど大きく成長する事例も報告されています。
ガジュマルの地植えを成功させるには、こうした地域ごとの特性を深く理解することが不可欠です。
この記事では、ガジュマルの地植えに関する具体的なリスク、地植えに向く品種ごとの特性、適切な置き場所や植え替えの時期について、専門的な視点から詳しく解説します。
さらに、地植えに必要な材料の選び方、成長をコントロールするための正しい剪定の方法、万が一元気がない状態になった時の原因と対処法まで、あなたが抱える疑問に総合的にお答えしていきます。
ポイント
- ガジュマルの地植えが「家を壊す」と言われる理由
- 関東と九州における地植えの可否と地域差
- 鉢植えから地植えへ植え替える具体的な手順
- 地植え後の剪定方法や元気がない時の対処法
コンテンツ
ガジュマルを地植えするリスクと適正
参考
- 庭に植えると家を壊す?
- 地植えに適した品種はある?
- 関東での地植えは可能か
- 九州など暖地の地植え事例
- 育てる置き場所の選び方
庭に植えると家を壊す?

観葉スタイル・イメージ
ガジュマルを庭に地植えすることには、想像以上に重大なリスクが伴います。結論から申しますと、ガジュマルの根は非常に強力で、家の基礎(土台)やコンクリート、アスファルト、ブロック塀を物理的に破壊する可能性が十分にあります。
この最大の理由は、ガジュマルの持つ強靭な生命力と、特徴的な根の成長の仕方にあります。ガジュマルは別名「締め殺しの木(Strangler fig)」とも呼ばれます。
これは、原産地では気根(幹や枝から出る根)が他の樹木に絡みつき、最終的にその木を枯らしてしまう生態に由来しますが、この力は無機物に対しても発揮されます。
地植えにすると、根は水分や養分を求めて四方八方に力強く伸びていきます。そして、アスファルトやコンクリートのわずかな亀裂や隙間にも入り込み、成長と共に太くなることで内部から強大な力で押し広げ、最終的には割ってしまうのです。
実際に、原産地である沖縄では、ガジュマルの太い根が歩道を盛り上げたり、住宅のブロック塀を押し倒したりする光景も珍しくありません。「家の近くには植えてはいけない」という現地の言葉は、この植物の計り知れないパワーを物語っています。
地植えがもたらす深刻なリスク
- インフラの破壊:根がコンクリートや基礎を持ち上げ、ひび割れや亀裂を生じさせます。
- 配管の破損:地中に埋設された水道管やガス管、下水管に根が侵入し、破損や詰まりを引き起こす恐れがあります。
- 撤去の困難さ:一度地植えにして数年経過すると、根は地中深くまで広範囲に広がります。その結果、撤去作業は重機が必要になるほど大掛かりになり、多額の費用が発生する可能性があります。
鉢植えでの管理が難しくなった(大きくなりすぎた)場合でも、地植えは最終手段ではなく、「避けるべき選択肢」として認識し、リスクを再検討することが非常に重要です。
地植えに適した品種はある?

観葉スタイル・イメージ
私たちが観葉植物としてよく目にする、幹の根元がぷっくりと膨らんだものは「ニンジンガジュマル」と呼ばれるタイプが一般的です。これらは実生(種から育てる)や挿し木で生産されています。
しかし、ガジュマル(学名:Ficus microcarpa)には、いくつかの園芸品種が存在し、中には比較的寒さや日陰に強いとされるものもあります。
例えば、「パンダガジュマル」や「センカクガジュマル」といった品種が知られています。これらは一般的なニンジンガジュマルに比べて葉が丸く肉厚で、耐寒性や耐陰性にやや優れているという情報があります。
特にパンダガジュマルは、海外(南フロリダなど)で庭木や生垣として植栽されている事例も見られます。
ただし、ここで強調しておきたいのは、これらの品種が日本の本州(特に関東以北)での地植えや屋外での冬越しを保証するものではないということです。
あくまで「一般的なガジュマルと比較して、やや強い」という程度であり、地植えに伴う前述のリスクがゼロになるわけではないことを、深く理解しておく必要があります。
ガジュマルの主な園芸品種と特徴
地植えを検討する以前に、品種ごとの特性を知っておくことは重要です。
| 品種名 | 主な特徴 | 耐寒性(目安) |
|---|---|---|
| ニンジンガジュマル | 最も流通量が多い。根元が人参のように膨らんでいる。 | 弱い(5℃程度まで) |
| パンダガジュマル | 葉が丸く肉厚で、光沢がある。成長は比較的遅め。 | やや強いとされる |
| センカクガジュマル | 尖閣諸島原産とされる。葉は小さめで丸く肉厚。 | やや強いとされる |
| 黄金ガジュマル | 台湾原産の園芸品種。新芽が美しい黄金色(ライムグリーン)になる。 | 弱い(5℃程度まで) |
もし温暖な地域で地植えに挑戦する場合でも、これらの品種ごとの特性を理解し、万全の防寒対策と植え場所の選定が求められます。
関東での地植えは可能か

観葉スタイル・イメージ
結論から申し上げますと、関東地方の屋外でのガジュマル地植えは、原則として不可能と考えた方が賢明です。
ガジュマルは熱帯・亜熱帯性の植物であり、その耐寒性は非常に低いです。多くの専門的な情報源で、生育可能な最低気温は5℃程度が限界とされており、それを下回る環境が続くと葉を全て落とし、株全体が枯死してしまいます。
気象庁の過去の気象データを参照すると、関東地方の主要都市(東京、横浜、さいたま等)では、冬期(12月〜2月)の最低気温の平均が5℃を下回り、氷点下(0℃以下)になる日も珍しくありません。このような環境下で、ガジュマルが地植えのまま冬を越すことは極めて困難です。
過去には、千葉県船橋市という比較的温暖な沿岸部で、アパートの軒下に放置されていたガジュマルが2年間冬を越し、1m以上に成長したという稀な事例もブログなどで報告されています。
しかし、これは「軒下」という霜や冷たい北風を直接避けられる特殊な環境であったことや、建物自体が持つ輻射熱(ふくしゃねつ)の影響など、複数の幸運な要因が重なった例外的なケースと考えるべきです。
関東での基本的な管理方法
関東地方でガジュマルを安全に楽しむためには、鉢植えでの管理が必須です。
- 春〜秋:気温が十分高い時期(5月〜10月頃)は、屋外の日当たりの良い場所で育てると元気に成長します。
- 秋〜冬:気温が下がり始める秋(最低気温が10℃〜15℃を下回る前)には、速やかに室内に取り込みます。
- 冬越し:室内の日当たりの良い窓辺などで管理します。ただし、冬の窓辺は夜間に急激に冷え込むため、夜間は部屋の中央に移動させるなどの工夫が必要です。また、暖房の温風が直接当たる場所は極端な乾燥を招くため避けてください。
九州など暖地の地植え事例
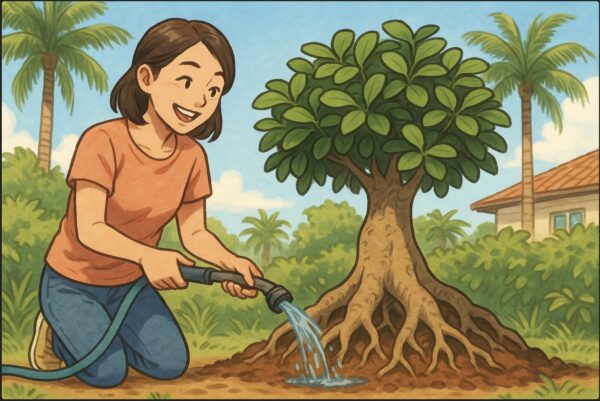
観葉スタイル・イメージ
関東地方とは対照的に、九州南部(宮崎県、鹿児島県など)や沖縄県のような、年間を通して温暖で霜がほとんど降りない地域では、ガジュマルの地植えが可能です。
ガジュマルは本来、日本では沖縄や屋久島などに自生する植物です。そのため、原産地に近い気候を持つこれらの地域では、地植えにすることでガジュマル本来の生育力を存分に発揮し、屋外での冬越しも問題なく行えます。
地植えにされたガジュマルは、鉢植えとは比較にならないほどのスピードで成長し、現地では樹高が20メートルを超える巨木になることも珍しくありません。
例えば、名護市ではガジュマルが市のシンボルとされており(出典:那覇市公式サイト)、公園や街路樹として、その雄大な姿を見ることができます。有名な「キジムナー(沖縄の精霊)が宿る木」として知られるガジュマルの多くは、このように地植えで大きく育ったものです。
九州でも全域が安全なわけではありません
「九州だから大丈夫」と安易に考えるのは早計です。九州であっても、北部(福岡県、佐賀県など)や、熊本県、大分県の内陸部の山間地では、冬に気温が5℃以下に下がったり、積雪や霜が降りたりすることがあります。
地植えが現実的に可能なのは、あくまで年間の最低気温が5℃を下回ることが稀で、霜がほとんど降りない沿岸部の温暖な地域(例:宮崎市や鹿児島市の沿岸部など)に限られると認識しておく必要があります。
育てる置き場所の選び方
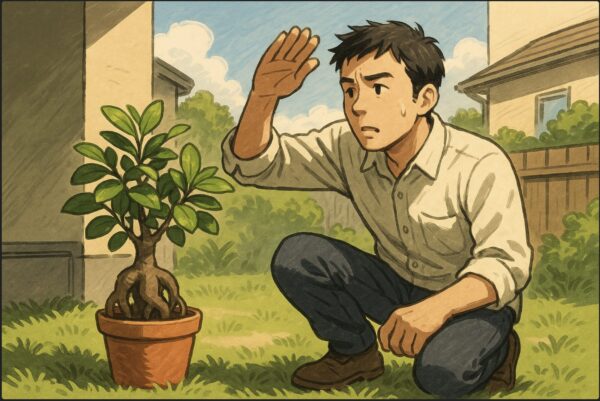
観葉スタイル・イメージ
ガジュマルの地植えを成功させるか、あるいは数年後に深刻なトラブルを引き起こすかは、「どこに植えるか」という最初の選択で決まると言っても過言ではありません。
これは、地植えが可能な温暖な地域(九州南部や沖縄など)にお住まいの方が、根が持つ破壊のリスクを承知の上で行う場合の、最も重要な判断基準となります。
植え付け場所の選定ミスは、後から修正することがほぼ不可能です。以下の「日当たり・風」、「建物との距離」、「土壌」の3つの条件を、植え付け前に必ず確認してください。
日当たりと風通し
ガジュマルは基本的に日光を好む植物ですが、置き場所選びには繊細な配慮が必要です。特に、これまで長期間室内やベランダの遮光下で管理されていた鉢植えの株を、いきなり強烈な直射日光が当たる場所に地植えにすると、環境の急変に耐えられません。
葉が光に適応できず、白っぽく変色したり、部分的に茶色く焦げたように枯れたりする「葉焼け(はやけ)」を起こしてしまいます。これを防ぐため、理想的なのは、「午前中は柔らかい日が当たり、午後の強すぎる西日は建物の陰になる」ような「明るい半日陰」の場所です。
また、耐寒性の低さを補うため、冬の冷たい北風や霜(しも)は大敵です。可能な限り、建物の南側や東側の壁際など、冷たい北風を物理的にブロックでき、霜が降りにくい場所を選ぶことが、冬越し成功の確率を上げる重要な鍵となります。
逆に、一日中まったく日が当たらない暗すぎる場所(建物の真北など)では、光合成が十分にできずに株が弱々しく育つ「徒長(とちょう)」の原因となり、健康な成長が見込めないため避けてください。
建物との距離
これが最も重要な注意点であり、将来の財産的な損害を防ぐ最大のポイントです。前述の通り、ガジュマルの根はコンクリートをも破壊するほど強力であり、その成長力を侮ってはいけません。
【最重要】根による破壊リスクの回避
地植えにしたガジュマルの根は、水分と養分を求めて地中を広範囲に、かつ力強く伸長します。その結果、数年後から数十年後に以下のような深刻な被害を引き起こす可能性があります。
- 建物の基礎(土台)への侵入、持ち上げ、ひび割れ
- コンクリート製の駐車場(土間コン)やアプローチの破壊、隆起
- 地中に埋設された水道管、ガス管、下水管への侵入と破損
- 浄化槽やブロック塀の押し出し、破壊
これらの取り返しのつかないリスクを最小限に抑えるため、最低でも建物やコンクリート構造物から5メートル以上、理想を言えば10メートル近く離れた、十分すぎるほどのスペースを確保できる場所に植え付けてください。
「まだ小さいから大丈夫だろう」という安易な判断が、将来的に多額の修繕費用を伴う深刻な事態を招きます。
土壌の条件(排水性)
ガジュマルは原産地では高温多湿な気候を好みますが、それは「空気中の湿度」が高いことを好み、土壌(根)が常に水浸しである状態を極端に嫌います。
水はけの悪い粘土質の土壌(雨が降ると水たまりがなかなか引かないような土地)にそのまま植え付けると、根が常に湿った状態になり、呼吸ができずに腐ってしまう「根腐れ」を確実に起こします。これは、ガジュマルが枯れる主要な原因の一つです。
植え付ける場所は、水はけ(排水性)の良い、やや乾燥気味の土壌を選ぶことが必須です。簡単な確認方法として、植え穴を掘った後に一度バケツで水を溜めてみて、水がなかなか引かないような場所は地植えに不向きです。
水はけが悪い場合の「土壌改良」
もし庭の土が粘土質で固く、水はけが悪いことが判明した場合は、そのまま植え付けるのではなく、必ず以下の「土壌改良」を行ってください。
- 植え穴を、予定している鉢のサイズよりも二回り以上大きく(例:直径・深さともに最低50cm以上)掘ります。
- 掘り上げた土の3〜4割ほどの量の「腐葉土」や「パーライト(または軽石小粒)」を準備します。
- 掘り上げた土と、これらの改良用土をしっかりと混ぜ合わせます。
- この「水はけが良くなった土」で植え付けます。
この一手間を加えることで、土壌に物理的な隙間が生まれ、根の呼吸を助ける通気性と余分な水を排出する排水性が格段に向上し、根腐れのリスクを大幅に減らすことができます。
ガジュマルを地植えする時の管理と対処法
参考
- 植え替えに適した時期
- 植え替えに必要な材料
- 鉢植えからの植え替え手順
- 剪定で大きさを調整するコツ
- 地植えで元気がない時の原因
植え替えに適した時期
ガジュマルの植え替えは、その後の生育を左右する非常に重要な作業です。鉢植えから地植え、あるいは鉢のサイズアップ(鉢増し)であっても、最適な時期は「生育期の前半」である5月中旬から7月頃です。
この理由は、ガジュマルの生態的なリズムにあります。熱帯・亜熱帯原産のガジュマルは、春になり気温が安定して20℃以上を保てるようになると、休眠から覚め、最も活発に新しい根や葉を展開する「生育期」に入ります。
植え替え作業は、どれだけ慎重に行っても根の一部を傷つけてしまい、植物にとって大きなストレスとなります。しかし、この成長エネルギーが最大になる時期に行うことで、受けたダメージからの回復が非常に早くなります。新しい根がすぐに伸び始め、新しい環境に迅速に適応できるのです。
梅雨時期(6月頃)のメリットと注意点
生育期の中でも、特に梅雨時期は植え替えに適しているという考え方もあります。これは、空気中の湿度が高いため、葉からの水分の蒸散(じょうさん)が抑えられ、植え替え直後の「水切れ」のリスクを軽減できるためです。
ただし、これには注意点も伴います。地植えの場合、長雨によって植え付けた場所の土壌が常にジメジメとした過湿状態になると、新しい根が呼吸できずに「根腐れ」を起こす危険性も高まります。よほど水はけが良くない限り、雨が続く日の作業は避け、梅雨の晴れ間を狙うのが理想です。
避けるべきタイミング
「生育期」の枠内であっても、避けた方が賢明なタイミングがあります。
- 真夏(8月)の酷暑期:気温が30℃を連日超えるような時期は避けてください。気温が高すぎると、根が受けたダメージに対して植物全体の消耗(蒸散)が激しくなり、かえって株を弱らせる可能性があります。
- 初春(3〜4月)の早すぎる時期:暖かくなり始めても、まだ気温が不安定です。「寒の戻り」によって急激に冷え込むリスクがあり、回復しかけた根が再びダメージを受けてしまう恐れがあるためです。
秋以降の植え替えは「厳禁」です
植物にとって植え替えは、人間の「手術」と同じです。手術後の回復には十分な体力(適切な気温と日光)が必要です。
気温が下がり始める秋(9月以降)や冬場に植え替えを行うのは、絶対に避けてください。
この時期に植え替えを行うと、以下のような最悪の事態を招きます。
- (1)回復の停止:気温の低下と共にガジュマルの生育(代謝)は停止します。根がダメージを受けても、新しい根を伸ばして回復する体力が残っていません。
- (2)致命的な根腐れ:活動を停止した傷ついた根が、冷たく湿った土の中に長期間さらされることで、そのまま腐敗し、春を迎えることなく株全体が枯死してしまいます。
「まだ暖かいから大丈夫だろう」という判断は非常に危険です。植え替えは、必ず株に十分な「回復期間」が残されている、初夏までに行うのが鉄則です。
植え替えに必要な材料
鉢植えで育てていたガジュマルを地植えに植え替える場合、以下の材料を事前に準備しておくと、作業がスムーズに進み、植え付け後の活着率(根付く確率)も高まります。
地植えへの植え替え:準備リスト
| 材料 | 目的・役割 |
|---|---|
| 腐葉土または堆肥 | 庭の土に混ぜ込む土壌改良材。土壌に有機質を補給し、微生物の活動を促し、水はけと水持ち(保水性)のバランスを改善します。 |
| パーライトまたは軽石(小粒) | 庭土が粘土質で特に水はけが悪い場合に使用します。土に物理的な隙間を作り、通気性と排水性を劇的に高めます。 |
| スコップ(大小) | 大きなスコップは植え穴を掘るために、小さなスコップ(移植ごて)は土を調整するために使います。 |
| 園芸用のハサミ(剪定バサミ) | 鉢から取り出す際に、傷んだ根や黒ずんだ根を整理するために使います。病気を防ぐため、必ず清潔で切れ味の良いものを用意してください。 |
なお、鉢植えで使用する「鉢底石」や「鉢底ネット」は、地植えの場合は水はけを妨げる可能性があるため基本的に不要です。ただし、植える場所の水はけが極端に悪い場合は、穴の底に軽石を一層敷くことで排水層とする場合もあります。
鉢植えからの植え替え手順

観葉スタイル・イメージ
鉢植えで大きくなったガジュマルを地植えにする際は、根へのダメージを最小限に抑えることが成功の鍵です。以下の手順で慎重に作業を進めましょう。
手順
- 穴を掘る:まず、選定した植え付け場所に、ガジュマルが入っていた鉢よりも直径・深さともに二回りほど大きな植え穴を掘ります。大きく掘ることで、根が張りやすい環境を作ります。
- 土壌の準備:掘り上げた庭の土の半分量に対して、腐葉土やパーライトを3〜4割ほど混ぜ込み、水はけの良い「植え付け用の土」を作っておきます。
- 鉢から取り出す:ガジュマルを鉢から丁寧に取り出します。根が鉢の側面に張り付いて抜けない場合は、鉢の側面を外側から軽く叩いて振動を与えると、土と鉢の間に隙間ができて抜けやすくなります。
- 根の整理:取り出した株の根鉢(根と土が固まった部分)を確認します。根が鉢の形でガチガチに固まっている(根詰まりしている)場合は、底の部分を十字に浅く切り込みを入れたり、肩の部分の土を優しく手でほぐしたりします。このとき、黒ずんで腐っている根や、異常に長く伸びすぎた古い根があれば、清潔なハサミで切り落とします。ただし、健康な白い根を傷つけないよう、根鉢を崩しすぎないことが重要です。
- 植え付け(高さ調整):掘った穴の底に、(2)で作った「植え付け用の土」を少し戻し、その上にガジュマルの株を中央に置きます。このとき、株の根元(幹と根の境目)が、周囲の地面の高さと揃うか、やや高くなるように土の量で高さを精密に調整してください。深植えは根腐れの大きな原因となります。
- 土を戻す:株の周囲の隙間に、残りの「植え付け用の土」をしっかりと入れ込みます。棒などで軽く突きながら土を入れ、根と土の間に不要な隙間ができないように密着させます。
- 水やり(水鉢):植え付けが完了したら、株の周囲に土手(水鉢)を作り、そこに水が溜まるようにします。そして、穴の底まで水が完全に染み渡るように、たっぷりと、2〜3回に分けて水を与えます。植え付け直後の数週間は、根が新しい環境に適応するまでの最も重要な時期です。土の表面が乾いたら水を与え、乾燥しすぎないように注意深く管理してください。(活力剤などを薄めて与えるのも回復を助けます)
剪定で大きさを調整するコツ
地植えにしたガジュマルは、根を自由に張れるようになるため、鉢植えの時とは比較にならないほどの旺盛な成長を見せます。そのため、大きさを適切にコントロールし、内部の風通しを良くして病害虫を防ぐためにも、定期的な剪定が不可欠です。
剪定の適期は、植え替えと同様に生育期である5月〜9月頃です。この時期であれば、多少強く枝を切り戻しても、すぐに新しい芽が出てきて樹形が回復します。逆に、冬場の剪定は株を弱らせるため避けてください。
剪定の基本手順と「忌み枝」
剪定は「不要な枝を取り除き、風と光の通り道を作ること」が基本です。
- (1)理想の樹形をイメージする:まず、最終的にどの程度の大きさと形にしたいかを明確にイメージします。
- (2)「忌み枝(いみえだ)」を切る:樹形を乱し、生育を妨げる以下の「忌み枝」を優先的に根元から切り落とします。
- 徒長枝(とちょうし):他より勢いよく真上に伸びる枝。
- 内向枝(ないこうし):幹の中心に向かって内側に伸びる枝。
- 交差枝(こうさし):他の枝と交差している枝。
- 下垂枝(かすいし):真下に向かって伸びる枝。
- 枯れ枝:枯れてしまった枝。
- (3)全体を整える:忌み枝を取り除いた後、理想のラインからはみ出して茂りすぎている枝の先端を、好みの長さで切り詰めて全体の形を整えます。
ここで重要な注意点があります。ガジュマルを剪定すると、切り口から乳白色のネバネバした樹液(ラテックス)が滴り落ちます。これはゴムの木の仲間特有のもので、体質によっては皮膚に触れるとかぶれ(アレルギー反応)を引き起こすことがあります。
作業中は必ずゴム手袋や園芸用の手袋を着用し、樹液が皮膚や衣服に付かないよう十分注意してください。もし付着した場合は、すぐに水で洗い流しましょう。
地植えで元気がない時の原因
期待して地植えにしたガジュマルの元気がない(葉が黄色くなる、葉が落ちる、しおれるなど)場合、環境が合っていないサインです。主に以下の5つの原因が考えられます。
1.寒さ(低温ダメージ)
最も可能性が高く、最も深刻な原因です。ガジュマルは寒さに極めて弱く、最低気温が5℃を下回る環境にさらされると、耐えられずに葉を黄色く変色させ、次々と落としてしまいます。霜や冷たい風に直接当たると、ダメージはさらに深刻になり、枝先から赤黒く枯れ込んでくることもあります。
2.根腐れ
植え付けた場所の水はけが悪く、土が常に湿った(過湿)状態が続くと発生します。特に、植物の活動が鈍る冬場に水分が多すぎると致命的です。
根が呼吸できずに腐り始めると、水や養分を吸い上げられなくなり、結果として葉がしおれたり、黄色くなったりします。幹を触ってみてブニブニと柔らかい感触がする場合は、根腐れの可能性が非常に高いです。
3.水切れ(乾燥)
地植えは鉢植えに比べて水切れしにくいですが、真夏の高温期に雨が全く降らない日が続くと、土壌が乾燥しすぎて水切れを起こすことがあります。葉に張りがなく、パリパリとした感触で落ちる場合は、水不足が疑われます。植え付け初年度は特に根の張りが浅いため、注意が必要です。
4.日照不足
ガジュマルはある程度の耐陰性(日陰に耐える力)もありますが、本来は日光を好む植物です。極端に日当たりが悪い場所(一日中日が差さない北側の壁際など)では、光合成が十分にできず、株が弱々しく徒長したり、葉の色が薄くなったり、葉を落としたりすることがあります。
5.病害虫
剪定を怠り、枝葉が茂りすぎて風通しが悪くなると、病害虫が発生しやすくなります。特に注意が必要なのは以下の2つです。
- ハダニ:高温乾燥時に発生しやすく、葉の裏に寄生して養分を吸います。葉にかすり傷のような白い斑点ができ、ひどくなるとクモの巣状になります。
- カイガラムシ:白い綿のようなものや、茶色い貝殻のようなものが枝や葉に付着します。排泄物が原因で葉がベタベタすることもあります。
これらの症状が見られた場合は、早急に適切な薬剤を使用するか、ひどい部分は枝ごと剪定して取り除く必要があります。
ガジュマルを地植えする時の判断基準
ガジュマルの地植えについて、そのリスクと管理方法を詳しく解説してきました。最後に、地植えを実行するかどうかの最終的な判断基準をリスト形式でまとめます。
チェックリスト
- ガジュマルの地植えは非常に強力な根が特徴
- 根が家の基礎やコンクリートを破壊するリスクがある
- 「家を壊す木」と呼ばれるため建物から十分な距離が必要
- 寒さに極めて弱く最低気温5℃が限界目安
- 関東など冬に氷点下になる地域での地植えは原則不可能
- 九州南部や沖縄などの霜が降りない温暖地でのみ可能
- 九州でも北部や内陸部は冬越しのリスクがある
- 地植えに適した品種として比較的耐寒性のあるパンダガジュマルなどがある
- ただし品種が本州での冬越しを保証するわけではない
- 植え付け場所は日当たりと水はけが良く北風を避けられる場所を選ぶ
- 植え替えの最適期は生育期の5月から7月
- 秋や冬の植え替えは枯れるリスクが高いため避ける
- 地植えは成長が早いため定期的な剪定が必須
- 剪定時の白い樹液は皮膚かぶれに注意し手袋を着用する
- 元気がない原因は寒さ・根腐れ・水切れ・日照不足などが考えられる
