
観葉スタイル・イメージ
パキラに栄養剤を与えたいけれど、パキラに適した肥料は何ですか?と疑問に思っていませんか。100均でも見かけますが効果があるのか、液体タイプが良いのか迷うこともあるでしょう。
また、パキラに栄養剤を与える時期はいつですか?というタイミングや、管理方法を間違えて枯れるのが心配な方もいるかもしれません。元気がないのは水不足なのか、それとも病気のサインなのか。弱ったパキラは復活しますか?と不安な時、思い切った剪定が必要なのかも気になります。
この記事では、検索ユーザーが抱えるそのような悩みに対し、おすすめのパキラ 栄養剤について、選び方の基本から弱った時の具体的な対処法まで、一歩踏み込んで詳しく解説します。
ポイント
- パキラに適した肥料と栄養剤(活力剤)の違い
- 液体と固形タイプのおすすめな選び方
- 栄養剤を与える最適な時期と頻度
- 弱ったパキラを復活させる対処法
コンテンツ
パキラの栄養剤について選び方の基本

観葉スタイル・イメージ
参考
- パキラに適した肥料は何ですか?
- おすすめの栄養剤はどれ?
- 液体肥料と固形肥料の違い
- 100均の栄養剤でも効果はある?
- パキラに栄養剤を与える時期はいつですか?
パキラに適した肥料は何ですか?

観葉スタイル・イメージ
パキラを室内で元気に、青々と育てていくためには、適切な栄養補給が欠かせません。ここでまず理解すべき最も重要な点は、「肥料」と「活力剤(栄養剤)」は法律上も役割上も明確に異なるものだということです。
結論から言うと、パキラの成長に不可欠なのは「肥料」です。肥料は植物にとっての「主食」であり、成長に必要な主要な栄養素を供給するものです。
一方、園芸店や100円ショップでアンプル型(土に挿すタイプ)などでよく見かける「活力剤」や「栄養剤」と呼ばれる製品の多くは、人間でいう「サプリメント」や「栄養ドリンク」に近い存在です。これらは植物の調子を整える補助的な役割を果たしますが、主食にはなりません。
肥料の三大要素(N-P-K)
植物の成長には多くの栄養素が必要ですが、特に大量に必要とされるのが「窒素・リン酸・カリウム」の3つで、「肥料の三大要素」と呼ばれます。市販の肥料パッケージには、多くの場合「N-P-K = 10-10-10」のように、これらの成分比率が記載されています。
- 窒素(N):葉や茎の成長を促進する栄養素です。「葉肥(はごえ)」とも呼ばれ、葉の緑色を濃くし、植物体を大きくする働きがあります。パキラのような葉の美しさを楽しむ観葉植物には特に重要です。
- リン酸(P):花芽の形成や開花、実つきを良くする栄養素です。「花肥(はなごえ)」や「実肥(みごえ)」と呼ばれます。観葉植物にとっては優先度がやや下がりますが、健全な成長にも関わります。
- カリウム(K):根や茎を丈夫にし、植物の体力をつける栄養素です。「根肥(ねごえ)」とも呼ばれます。寒さや暑さ、病害虫に対する抵抗力を高める働きがあり、パキラを健康に保つために不可欠です。
パキラのような観葉植物を育てる場合は、葉の成長を助ける窒素(N)の比率が多めに配合されているものか、あるいは各成分がバランス良く配合された「観葉植物用」と明記された肥料を選ぶのが最も基本的で安全な選択です。
化学肥料と有機肥料
肥料はその原料によっても、大きく2種類に分類されます。
- 化学肥料(無機質肥料):鉱物などを原料として化学的に製造された肥料です。成分が明確で、植物がすぐに吸収できる形で含まれているため、速効性があります。何より無臭で清潔なため、虫が湧く心配が少なく、室内で育てるパキラにはこちらが圧倒的におすすめです。
- 有機肥料(有機質肥料):油かすや鶏ふん、骨粉など、動植物由来の有機物を原料として作られた肥料です。土の中の微生物によって分解されてから植物に吸収されるため、効果はゆっくり(緩効性)です。土壌を豊かにする効果もありますが、特有の臭いがあったり、カビやコバエの発生源になったりするデメリットがあるため、室内での使用には高度な管理と注意が必要です。
肥料の定義について
日本では「肥料の品質の確保等に関する法律(旧・肥料取締法)」に基づき、成分(N-P-Kなど)の含有量が一定基準を満たし、国に登録・届出されたものだけが「肥料」として販売を許可されています。(参照:農林水産省「肥料制度」)
基準に満たないものは「活力剤」や「植物活性剤」などと呼ばれ、区別されています。
おすすめの栄養剤はどれ?
「栄養剤」という言葉は広い意味で使われますが、ここではパキラの成長に不可欠な「肥料」として、実績があり使いやすい代表的な市販品をいくつか紹介します。ご自身のライフスタイルや管理の頻度に合わせて選んでみてください。
液体肥料(速効性・追肥向き)
水やりの際に、規定の倍率(500倍や1000倍など)に希釈して与えるタイプです。根からすぐに吸収されるため効果が早く現れやすく、生育期にグンと成長させたい時の「追肥(ついひ)」として使うのに適しています。
最も代表的な商品としては「ハイポネックス原液」があります。
観葉植物専用の製品も販売されており、ハイポネックスジャパン公式サイトによると、観葉植物の生育に必要な窒素・リン酸・カリのバランス(N-P-K=8-8-8など製品による)が良く、さらに光合成を助けるマグネシウムや、植物の健康維持に必要な各種微量要素(鉄、マンガン、銅など)もバランス良く含まれているとされています。
使用方法は、水で500倍~1000倍などに正確に薄めて使用します。
液体肥料の注意点
速効性がある反面、効果の持続期間は1~2週間と短いため、生育期には定期的に与える手間がかかります。また、「濃すぎると肥料焼けを起こす」ため、必ず規定の希釈倍率を守ることが非常に重要です。
固形肥料(緩効性・元肥や置肥向き)
土の上に置いたり、植え替え時に土に混ぜ込んだりするタイプです。ゆっくりと時間をかけて溶け出し、長期間効果が持続するのが最大の特長です。
- 置肥(おきごえ):「プロミック観葉植物用」などが代表的です。これは錠剤や粒状の肥料を土の上にパラパラと置くだけで、水やりのたびに少しずつ成分が溶け出す仕組みになっています。メーカーの記載によれば、約2ヶ月程度効果が持続するとされており、手軽で肥料切れを防ぎやすいのが大きなメリットです。
- 元肥(もとごえ):植え替えの際に、新しい土に予め混ぜ込んでおく肥料として「マグァンプK」が非常に有名です。メーカーの記載によれば、根から出る酸や微生物の働きに反応して必要な分だけ成分が溶け出す仕組みのため、根を傷めるリスクが少なく、効果が約1年~2年持続するタイプもあります。植え替えの手間を減らしたい方に向いています。
補足:活力剤の活用法
前述の「肥料」とは別に、弱った時のケアとして「活力剤」を併用するのも効果的です。代表的なものに「メネデール」があります。これは鉄を二価イオン(植物が吸収しやすい形)で含んだ活力液で、発根を促進する効果があるとされています。植え替え後のダメージ回復期や、挿し木、元気がない時のサポートとして、肥料の代わりに使用します。
液体肥料と固形肥料の違い
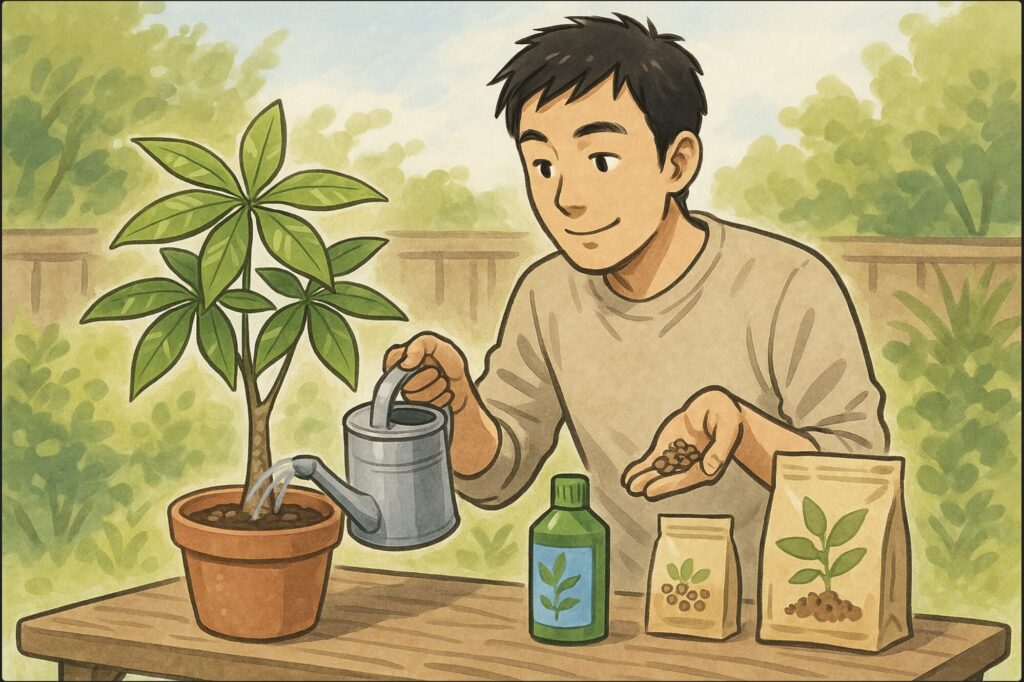
観葉スタイル・イメージ
液体肥料と固形肥料は、どちらが優れているということではなく、それぞれに明確な特性と適した使い方があります。目的に応じて正しく使い分けることが、パキラを上手に育てる近道です。
肥料は与えるタイミングによって「元肥(もとごえ)」「追肥(ついひ)」「お礼肥(おれいごえ)」などと呼ばれますが、観葉植物のパキラで主に使うのは「元肥」と「追肥」です。
- 元肥(もとごえ):植え付けや植え替えの際に、あらかじめ土に混ぜ込んでおく肥料。ゆっくり長期間効く「固形肥料(緩効性)」が使われます。
- 追肥(ついひ):植物の生育期間中に、不足する養分を補うために追加で与える肥料。すぐに効いてほしい場合は「液体肥料(速効性)」を、効果を持続させたい場合は「固形肥料(置肥)」が使われます。
それぞれのメリットとデメリットを以下の表にまとめます。
| 種類 | 特徴(効果の出方) | 持続期間 | 主な使い方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 液体肥料 | 速効性(すぐに効く) | 短い(約1~2週間) | 追肥 | ・生育期に「効かせたい」時に便利 ・濃度の微調整がしやすい | ・頻繁に与える手間がかかる ・効果が持続しない ・希釈を間違えると危険 |
| 固形肥料 | 緩効性(ゆっくり効く) | 長い(約2ヶ月~2年) | 元肥・置肥(追肥) | ・一度与えれば長持ちする(手間が少ない) ・肥料切れの心配が少ない ・効果が穏やかで根を傷めにくい | ・すぐに効果が出ない ・与えすぎた場合に取り除きにくい |
おすすめの使い分け(併用) 最も確実で管理がしやすいのは、両方の良いところを活かす併用です。
- 植え替えの時に、固形肥料(緩効性)を「元肥」として土に混ぜ込んでおく。
- さらに、春~秋の生育期には固形肥料(置肥)を土の上に置いておく。
- パキラの生育が特に活発になる初夏~夏場(5月~8月頃)にだけ、液体肥料を「追肥」として2週間に1回程度追加で与える。
このように使い分けることで、常に栄養が安定供給され、かつ成長期にはブーストをかけることができます。
100均の栄養剤でも効果はある?
100円ショップなどで手軽に購入できる、緑色やピンク色のアンプル型(土に挿すタイプ)の製品について、多くの方が「あれは効果があるのか?」と疑問に思っています。
結論から言えば、あれらの多くは前述した「肥料」ではなく「活力剤」です。
これらは、植物の成長に必要な窒素・リン酸・カリの含有量が、法律(肥料の品質の確保等に関する法律)で定められた「肥料」の基準値を下回っているものを指します。そのため、製品の裏書きを見ても「肥料」とは書かれておらず、「活力液」や「植物用栄養剤」といった表記になっているはずです。
主成分は鉄分やマグネシウム、各種ミネラル、ビタミン類などであることが多く、これらは植物の生理機能を助ける「サプリメント」としての役割を果たします。
もちろん、これらが全く無意味というわけではありません。例えば、土壌がアルカリ性に傾いて鉄分が不足し、葉の色が薄くなった(クロロシス)場合などに、鉄分を含む活力剤を与えることで葉色の改善が期待できる場合もあります。
しかし、パキラが幹を太くし、新しい葉を次々と展開するために必要な主要なエネルギー源(窒素・リン酸・カリ)を補給することはできません。したがって、これだけを挿して「栄養を与えている」と安心していると、パキラは徐々に栄養不足になってしまいます。
100均アンプル剤の正しい使い方 100均のアンプル剤は、あくまで「栄養ドリンク」のような一時的なサポートや、微量要素の補給として使うものです。主食である「肥料」は、別途必ず観葉植物用のものを与えるようにしてください。
パキラに栄養剤を与える時期はいつですか?

観葉スタイル・イメージ
パキラに肥料(栄養剤)を与えるタイミングは、1年間の管理の中で最も重要なポイントと言っても過言ではありません。このタイミングを間違えると、良かれと思ってやったことが、パキラを枯らす致命的な原因になりかねません。
結論は非常にシンプルです。「生育期(春~秋)」に与え、「休眠期(冬)」には絶対に与えないことです。
パキラは中南米の熱帯地域が原産の植物です。そのため、気候が温暖で(気温が15℃~25℃程度)、日照時間が長い時期に活発に成長し、気温が下がり寒くなると成長をピタリと止めて「休眠」します。この自然のリズムに合わせて栄養管理をすることが、失敗しない最大のコツです。
生育期(目安:5月~9月頃)
気温が安定して15℃を超えるようになると、パキラは休眠から目覚め、新しい葉を次々と展開し始めます。この時期は、成長のために多くの栄養(肥料)を必要とします。
- 液体肥料の場合:製品の規定に従い、2週間に1回程度、水やりの代わりに与えます。
- 固形肥料(置肥)の場合:製品の規定に従い、2ヶ月に1回程度、新しいものに交換します。
ただし、真夏日(35℃以上)が続く猛暑期は、パキラも夏バテを起こして一時的に成長が鈍ることがあります。その際は、液体肥料の頻度を少し控える(3週間に1回にするなど)配慮も有効です。
休眠期(目安:10月下旬~4月頃)
最低気温が15℃を下回り始めると、パキラは成長を止め、冬越しのために「休眠状態」に入ります。この状態になると、光合成の量も減り、水を吸い上げる力も極端に弱まります。当然、栄養もほとんど必要としません。
この休眠期に肥料を与えてしまうと、根が吸収できない肥料成分が土の中に蓄積します。それが土壌内の水分濃度を異常に高め、後述する「肥料焼け」や、余分な養分と水分で「根腐れ」を引き起こす最大の原因となります。
したがって、冬場は水やりの頻度を極端に減らす(土が完全に乾いてから数日後)とともに、一切の肥料・活力剤をストップしてください。これがパキラを無事に冬越しさせるための鉄則です。
パキラの栄養剤について弱った時の使い方
参考
- 栄養不足?根腐れなど病気のサイン
- 与えすぎで枯れる?肥料焼けとは
- 弱ったパキラは復活しますか?
- 復活のための剪定のコツ
- 栄養剤以外の基本的な管理方法
栄養不足?根腐れなど病気のサイン
パキラの元気がない時、「栄養が足りないのかな?」と直感的に考えがちですが、それは早計かもしれません。特に室内で育てている場合、その不調の原因が「栄養不足」である可能性は、他の原因(根腐れ・肥料焼け・日照不足など)に比べて高くありません。
むしろ、水やりの失敗による「根腐れ」や、逆の「肥料の与えすぎ」であるケースが非常に多いです。サインを正しく見極めて対処することが重要です。
栄養不足の主なサイン
本当に栄養が不足している場合のサインは、比較的ゆっくりと現れます。
- 葉の色が全体的に薄い、黄緑色っぽくなる。特に古い下の方の葉から症状が出始め、徐々に上に向かって広がります。
- 新しい葉がなかなか出てこない、または出てきても葉が小さい。
- 茎が細く、間延びしている(徒長)。(これは日照不足との複合的な原因が多いです)
これらのサインが、冬以外の「生育期」に見られ、かつ植え替えを2年以上していない場合に、肥料不足の可能性が考えられます。その場合は、規定通りに肥料を与えてみましょう。
根腐れ・病気のサイン
一方で、こちらの方が緊急性が高く、危険なサインです。
- 幹の根元、土に埋まっている部分を触るとブヨブヨ(ブニブニ)と柔らかい。(健康な幹は硬いです)
- 土が常にジメジメと湿っており、カビ臭い、または酸っぱいような異臭がする。
- 土の周りをコバエ(キノコバエ)が飛び回っている。(湿った有機物を好むため)
- 水やりをしても葉がしおれたままでハリが戻らず、葉が黄色くなる。(この場合、新芽や上の方の葉から症状が出ることが多いです)
最重要:根腐れ時の肥料は絶対禁止!
根腐れは、水のやりすぎや土の水はけの悪さで、根が呼吸できずに窒息し、腐っている状態です。根が機能していないため、水分も栄養も吸収できません。
この状態で肥料を与えると、腐敗した根にさらにダメージを与えることになり、ほぼ確実に枯れてしまいます。元気がないからと焦って栄養剤(特に肥料成分)を与えるのは、瀕死の人にステーキを無理やり食べさせるようなもので、逆効果です。
与えすぎで枯れる?肥料焼けとは

観葉スタイル・イメージ
「栄養剤(肥料)を与えすぎると枯れる」というのは園芸の常識ですが、そのメカニズムを知っておくことは非常に重要です。これは「肥料焼け」と呼ばれる現象が原因です。
植物の根は「浸透圧」という物理現象を利用して、土の中から水分を吸収しています。これは、水が「濃度の低い(水っぽい)方」から「濃度の高い(塩辛い)方」へ移動するという自然の法則です。
通常、土の中の水分濃度は、根の中の細胞液の濃度よりも低く(水っぽく)なっています。そのため、水は自然に土から根の中へと移動します。
しかし、肥料を与えすぎたり、冬場に吸収されない肥料が蓄積したりすると、土の中の肥料濃度が、根の中の細胞液の濃度よりも異常に高くなってしまいます。すると、浸透圧のバランスが逆転し、根の中にあるべき水分が、逆に濃度の高い土の方へ吸い出されてしまうのです。
野菜を塩もみすると水分が出てシナシナになりますよね?あれと同じ現象が、パキラの根で起こっていると想像してください。水やりをしているのに、根は水分を吸収できず、むしろ奪われて「脱水症状」を起こしている状態です。これが肥料焼けの正体です。
肥料焼けを起こすと、根がダメージを受け、水分を吸えなくなるため、葉が急にしおれたり、葉先やフチから茶色くパリパリに枯れ込んだりする症状が出ます。特に液体肥料を「濃い方が効くだろう」と規定より濃く作ってしまった場合に、即座に発生しやすい深刻なトラブルです。
弱ったパキラは復活しますか?

観葉スタイル・イメージ
パキラは原産地では高木になるほど生命力が非常に強い植物です。そのため、幹の中心部まで完全に枯れていなければ、原因に合わせた適切な対処を早期に行うことで、復活する可能性は十分にあります。
肥料焼けが疑われる場合
対処法:すぐに肥料成分を洗い流す(水洗)
液体肥料を濃く与えすぎたなど、急性の肥料焼けが疑われる場合の応急処置です。
簡単な流れ
- すぐに鉢を屋外やお風呂場に運びます。
- 鉢底の穴から水道水がジャージャーと流れ出るまで、普段の水やりの3~5倍量の水を惜しみなく与え続けます。
- これで土の中の濃すぎる肥料成分を強制的に洗い流し、薄めます。
- その後は、風通しの良い明るい日陰で、土が乾くまでしっかりと休ませます。
それでも改善しない場合や、固形肥料を与えすぎて長期間ダメージを受けている場合は、次の「植え替え」を行うのが最も確実です。
根腐れが疑われる場合
対処法:緊急植え替えと腐敗部の除去
これは発見次第、すぐに行うべき必須の手術です。
手順
- パキラを鉢から優しく引き抜きます。根が張っている場合は、鉢のフチを叩くと抜けやすくなります。
- 古い土をすべて丁寧に落とします。腐っている場合は土も異臭がするはずです。
- 根を水で洗い、状態を確認します。黒く変色したり、触るとブヨブヨと崩れたりする根が「腐った根」です。
- アルコールなどで消毒した清潔なハサミで、腐った根を全て切り落とします。少しでも残っていると、そこからまた腐敗が広がります。健康な白い根だけを残すようにします。
- 幹の根元がブヨブヨしている場合は、その部分もナイフなどで削り取ります。
- 傷口を数時間乾かした後、一回り小さな鉢(根の量に合わせて)に、新しい清潔な「観葉植物用の培養土」で植え替えます。この時、水はけを良くするために鉢底石をしっかり敷いてください。
植え替え後のケア(最重要)
植え替え直後のパキラは、人間でいえば大手術の後と同じで、極度に弱っています。このタイミングで「肥料」を与えるのは絶対に禁止です。
水やりは、土が乾いてから行いますが、その際に水やりの代わりに、発根を促進する「活力剤(メネデールなど)」を希釈して与えるのが効果的です。その後、最低でも2週間~1ヶ月は肥料を一切控えて、直射日光の当たらない明るい日陰で静かに休ませ(養生)ましょう。
復活のための剪定のコツ
パキラの元気がなく、枝がヒョロヒョロと間延びしている(徒長している)と、「スッキリさせて負担を軽くしよう」と焦って剪定(せんてい)を考えてしまうかもしれません。
しかし、弱っている原因が根腐れや肥料焼けである場合、その剪定が逆効果になることがあり、細心の注意が必要です。
植物は、葉にある「葉緑体」で光合成を行い、活動するためのエネルギー(糖)を自ら作り出しています。根がダメージを受けている(根腐れや肥料焼け)状態のパキラは、水や養分をうまく吸収できません。
このような危機的状況で、回復に必要なエネルギーを供給できるのは、今残っている健康な葉だけです。
このタイミングでエネルギー源である健康な葉まで大幅に切り落としてしまうと、パキラは根を再生させるためのエネルギーすら作れなくなり、回復が著しく遅れるか、最悪の場合、そのまま力尽きて枯死してしまうことがあります。
したがって、弱っている原因がはっきりしない場合や、ダメージが軽度(葉が少ししおれている程度)な場合の剪定は、最小限にとどめるのが基本です。明らかに全体が茶色くパリパリに枯れてしまった葉や、完全に黄色く変色して落ちそうになっている葉を取り除く程度にしましょう。
これらは既に光合成の能力を失っているため、取り除いても問題ありません。緑色が残っている葉は、たとえ小さくても貴重なエネルギー工場なので、できるだけ残してください。
例外:根腐れ処置で根を大量に切った場合
ただし、この「弱っている時は切らない」という基本ルールには、一つだけ重要な例外があります。それは、前述の「根腐れ」の処置で、腐った根を半分以上切り落とすなど、根の量を大幅に減らす外科手術を行った場合です。
この場合、植物は「吸う水分の量(根)」と「出ていく水分の量(葉)」のバランスが極端に崩れた状態になっています。
解説:根と葉の「蒸散」バランス
植物は、根から吸い上げた水分を、主に葉の裏側にある「気孔(きこう)」から水蒸気として放出(蒸散)しています。これは植物が生きる上で必要な生理活動です。
根を大幅に切った状態は、例えるなら「水分の供給ライン(根)が半分以下になっているのに、水分の放出口(葉)は100%のまま」という危険な状態です。
これでは、根が必死に吸い上げるわずかな水分を、葉が容赦なく放出してしまうため、パキラはすぐに水切れ(脱水症状)を起こしてしおれてしまいます。
この場合に限り、葉の量を減らして「出ていく水分」を強制的に制限し、少ない根でも維持できる「吸う水」とのバランスを取ってあげる必要があるのです。
この場合に限り、健康な葉や枝も剪定する必要があります。目安として、切り落とした根の量と同じ割合(根を1/3切ったら葉も1/3減らす、根を半分切ったら葉も半分減らす)で、枝や葉を剪定します。
具体的には、込み合っている枝を付け根から間引いたり、特に大きな古い葉を葉柄の部分からカットしたりして、全体の葉の枚数を減らして調整します。
これらの応急処置的な剪定を行った後は、パキラの回復を待ちます。元気を取り戻し、幹の節目などから緑色の小さな新芽が動き出したり、新しい葉が開き始めたりしたら、それが「回復のサイン」です。
そこまで回復して初めて、ヒョロヒョロと間延びした(徒長した)枝を好みの位置で切り戻したり、樹形を美しく整えたりするための「通常の剪定」を行うのが、最も安全で確実な手順となります。
栄養剤以外の基本的な管理方法
ここまで栄養剤(肥料)について詳しく解説してきましたが、これらはあくまで「補助」的なものです。パキラを元気に育てるには、日々の基本的な管理(水・光・温度)が何よりも重要です。これができていなければ、どんなに良い肥料を与えても効果はありません。
水やり
最も失敗が多いポイントです。基本は「乾湿のメリハリ」です。
「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与え、受け皿に溜まった水は必ず捨てる」。これが鉄則です。
指を土の第一関節まで挿してみて、中まで乾いているのを確認してから水を与える癖をつけましょう。「土が常に湿っている状態」が数日続くと、根が呼吸できなくなり、根腐れの最大の原因になります。
冬の休眠期は、土が完全に乾いてから、さらに数日~1週間待つくらい乾燥気味に管理します。
日当たり
パキラは日光が大好きです。耐陰性(日陰に耐える力)もありますが、暗い場所に長期間置くと、光合成ができずに葉の色が薄くなったり、茎が細くヒョロヒョロと間延び(徒長)したりします。
ただし、真夏の強すぎる直射日光は「葉焼け」の原因になるため、レースのカーテン越しの柔らかい光が一日中当たる、明るい室内が最も理想的な場所です。
温度
熱帯の植物であるため寒さに非常に弱いです。元気に育てるには最低でも10℃以上、安全に冬越しさせるにはできれば15℃程度をキープすることが望ましいです。5℃以下になると深刻なダメージを受け、枯れる危険性が高まります。
冬場は室内の暖かいリビングなどに置きますが、夜間の窓際は、外気で想像以上に冷え込みます。就寝時は部屋の中央に移動させるなどの配慮が必要です。また、エアコンや暖房の風が直接当たると、極度の乾燥で葉を傷めるため、置き場所には注意してください。
正しいパキラの栄養剤で元気に
この記事の要点をリストでまとめます。パキラの栄養管理は難しくありません。正しい知識を持って、適切なタイミングで与えることが大切です。
チェックリスト
- パキラの成長には「肥料」が不可欠
- 「活力剤」や「栄養剤」はサプリメントであり肥料の代わりにはならない
- 肥料には窒素・リン酸・カリの三大要素が含まれる
- パキラには窒素(N)が多めかバランスタイプがおすすめ
- 室内では無臭で清潔な「化学肥料」が使いやすい
- 液体肥料は速効性があり追肥向き
- 固形肥料は緩効性で元肥や置肥向き
- 100均のアンプルは肥料ではなく活力剤の場合が多い
- 肥料を与える時期は生育期の春〜秋(5月〜9月頃)
- 休眠期(冬)に肥料を与えると根腐れの原因になる
- 元気がない原因が「根腐れ」の場合、肥料は絶対禁止
- 幹の根元がブヨブヨしているのは根腐れのサイン
- 肥料の与えすぎは「肥料焼け」を引き起こし枯れる原因になる
- 肥料焼けは水で流すか植え替えて対処する
- 弱ったパキラは植え替えと根の整理で復活できる可能性がある
- 植え替え直後は肥料ではなく活力剤で休ませる
- 基本は水やり・日当たり・温度管理が最も重要
